橋場弦『古代ギリシアの民主政』
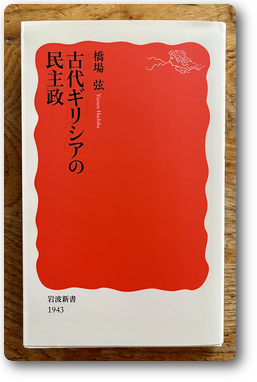
橋場弦『古代ギリシアの民主政』岩波新書、2022年9月刊、245頁+11頁、900円
目次は以下の通りです。
はじめに、
第1章 民主政の誕生
第2章 市民参加のメカニズム
第3章 試練と再生
第4章 民主政を生きる
第5章 成熟の時代
第6章 去りゆく民主政
おわりに
あとがき
図版出典一覧
関連年表
主要参考文献
本書は、近年の研究を踏まえて、古代ギリシアの民主政の誕生から、その終焉までが丁寧に描かれています。従来、アテナイ民主政は、前322年のラミア戦の敗北(マケドニアの支配)で終焉を迎えるというのが通説でしたが、著者は、ローマの支配(スラの占領)までを視野に入れています。つまり、古代民主政はヘレニズム時代を通じて、しぶとく生き残っていたことを(もちろん変質はしていますが)、碑文史料などからも説き明かしています。
また、古代民主政は政治理論を持たない、生きた民主政であることを、アテナイ民主政の政治参加のメカニズムを通して生き生きと伝えてくれています。
さらに、「おわりに」では、近代以降における民主政の受容というテーマを取り上げ、「衆愚政治」に代表される反民主主義の思想、「西欧思想における反民主主義の伝統」について、言及されており、我々が古代ギリシアの民主政を学ぶ意味についても考えさせてくれます。
最近の権威主義の高まる中国,ロシアなどの国家に対して、近代民主主義は、岐路に立たされているという報道も耳にしますが(賛否はともかく)、本書は改めて民主政治を考える上でも(その原点を考えるという意味で)一読の価値ある書物だと思います。
(2022/10/31)
栗原麻子『互酬性と古代民主制』
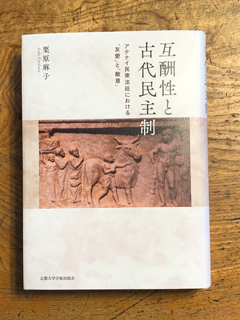
栗原麻子『互酬性と古代民主制―アテナイ民衆法廷における「友愛」と「敵意」』京都大学出版会、2020年4月刊、636頁、5,800円
本書は、著者がこれまで国内外で発表してきた諸論文に、新たに書き下ろした数編の論文を加えて一冊にまとめた600頁を超える大著です。
論文の初出は、初出一覧にまとめられています
目次は以下の通りです。
序論部 互酬性を飼い慣らす
第一章 アテナイ史と互酬性―アルカイックな傷跡かヘレニズムの先駆けか
第二章 友愛とポリスーアリストテレス『ニコマコス倫理学』
第三章 大きすぎるポリスの小さな法廷―民衆法廷の社会的性格
第一部 公的言論のなかの血縁ネットワーク
第四章 家族の肖像―前四世紀アテナイにおける法制上のオイコスと世帯
第五章 血縁と友愛―イサイオスの描く親族争議
第六章 獲得されるものとしての親族関係―前四世紀におけるソロンの遺言
の法の運用
第二部 公と私のはざまで
第七章 ヘタイレイアーの信義をめぐってー前四一五年のアンドキデス
第八章 被害者のための報復―「何人でも欲するもの」による訴追の運用
第九章 法廷における動議としての個人的敵意―公私の分離
第一〇章 法廷弁論における訴訟の動機と私的敵意―公私の連続
第三部 詩人たちの世界
第一一章 イディアイ・グラファイ(私的な公訴)―デモステネス『メディア ス弾劾』の場合
第一二章 アプラーグモシュネー(静謐主義)と市民性―リュシアスの描く「私人」たち
第一三章 ポリスへの参画―遊女ネアイラと市民女性
第四部 友愛共同遺体としてのポリス社会
第一四章 恩恵と哀れみー法廷における感情
第一五章 「レオクラテス弾劾」―リュクルゴスと互州的秩序
第一六章 リュクルゴスとヒュペレイデスー私人に対するエイサンゲリアー(弾劾裁判)をめぐって
第一七章 「禍根を残さない」誓いー前四○三年の和解と市民共同体の再生
結論部
初出一覧
あとがき
用語解説
参考文献表
索引(人名・出典・事項)
本書はアテナイの法廷弁論を史料として、古代アテナイを支えていた社会構造を社会史の立場から解き明かそうとする意欲作です。
以下、簡単に本書の目的と結論を述べます。
著者は、本書の目的は、ギリシア人の社会的正義の根底をなしていた「友愛」と「敵意」が、ポリス社会の秩序にどのように組み込まれていたのかを、アテナイ法廷弁論を史料として解き明かすこと、そして法廷戦略が前提としていた民衆法廷の社会的性格を描くことにあると述べています。
著者は、アテネの「互酬性」を軸として、序論部、第一部、第二部、第三部(全十七章)、そして結論部にわたって持論を展開しています。
結論として、著者はアテナイにおける紛争解決は、法廷外的紛争解決の志向性と、法廷弁論を支配する互酬的価値観により、社会関係から切り離されることはなかったと述べます。
そして、法廷で闘争するとは、私訴にせよ公訴にせよ、周囲の人間やポリスとの間に自分が形成してきた互酬的諸関係を、民衆に認証させると言うことであったということ。
さらに、古典期アテナイにおける互酬的ネットワークを概観することで、古典期のアテナイにおいては、市民間に互酬的な恩恵関係が張り巡らされており、それらがポリスの秩序を根底において担っていたこと。
また、市民の集合体としてのポリスもまた、市民個々人との間に、「友」としての関係を取り結ぶことで、互酬的ネットワークの一端を担い、民衆法廷での弁論と投票を通じて、友愛・敵対関係を正当化し、それを制御していた、という見取り図が示されると述べています。
最後に、互酬的諸関係は、古典期を通して、アテナイにおける秩序形成の主要な原理であり続けたこと。その際、誰をポリスの友とするのかを決定するのは、民衆法廷であった。そこに、アテナイ民主制の互酬的秩序があったと結んでいます。
(2021/09/22)
篠原道法『古代アテナイ社会と外国人 ―ポリスとは何か』

篠原道法『古代アテナイ社会と外国人 ―ポリスとは何か』関西学院大学出版会、2020年1月刊、370頁、3800円
本書は、著者が2011年3月に、立命館大学大学院文学研究科に提出した学位論文とその後の研究をまとめたものです。
目次は以下の通りです。
はじめに
凡例
地図1 前4世紀の東地中海とその周辺
地図2 前4世紀のギリシアとエーゲ海
序論
第1章 古典期アテナイにおける住民概念としてのアストス
第2章 前5世紀末アテナイにおける内乱と和解 ―社会への外国人の関与をめぐって
第3章 古代アテナイにおける市民団の一体性・平等性とその背景 ―民主政成立の画期に注目して
補論 前5世紀後半における国際関係とアウトノミア概念の展開 ―アテナイによる「帝
国」正当化の論理をめぐって
第4章 前4世紀におけるアテナイ社会と外国人 ―顕彰碑文の分析を中心に
第5章 前4世紀以降のアテナイにおける外国人の社会進出と自己実現 ―墓碑の分析を通じて
第6章 前5世紀中葉以降におけるアテナイ住民と名誉をめぐる社会規範 ―墓碑における戦死の表現に注目して
第7章 アテナイ住民の社会的機能の表現とその意義 ―前5世紀中葉以降の墓碑を資料として
結論
あとがき
初出一覧
略語一覧
参考文献
索引
英文要旨
まず、序論は、研究動向、そしてその評価と方向性、本書の概要と構成からなっています。そして、本書の目的は、市民と外国人の両者は双方の人間関係をどう認識し、両者は実際の行動の中でポリスのメンバーシップをどう理解していたかを通時的に分析することで、最終的にポリスの実像に迫ることであると述べられています。
本論は2部に分かれていて、前半は共同体メンバーに関わる市民意識の反映した語義・概念(アストス・ポリテスなど)をアプローチの視覚として、文献資料における市民意識の跡付けを行っています。
後半は、市民団の公式表現と外国人の私的表現から市民と在留外国人の関係性や距離感を図る議論で、碑文資料(顕彰碑文と墓碑)を分析し、市民団の方にも在留外人の方にも境界を越える意識が存在したと論じています。
結論として、アテネ市民団の閉鎖性や、一体性・平等性が強く意識されるのは、前5世紀中葉〜末の「アテナイ帝国時代」であり、その時代的背景にはアテナイの市民団が「他者を支配する特権集団」としての強硬な一体感を持ったこと。
次いで、第2次海上同盟結成後に対外支配の志向が高まった前4世紀前半。(著者は「想像の共同体」が前5世紀中葉以降に形成されたと論じています)
それ以外の時期は、状況に応じて市民と外国人双方が、住民意識を軸に開放的なメンバーシップに基づいて行動しており、多様な関係性と時々の状況によりメンバーシップのあり方が問い直された。
すなわち、こうした行動と意識の柔軟性がポリスを支える重要な要素の一つであった。
※ここでの本書の紹介は、先日(9/18)の西洋古代史サマーセミナー(オンライン)での合評会で、コメンテーターを務めた明治大学の古山夕城さんの「本書の構成と展開」(PDF)の内容の一部を引用させて頂いています。
(2021/09/20)
伊藤正『ゲオーポニカー古代ギリシアの農業事情』

伊藤正『ゲオーポニカー古代ギリシアの農業事情』刀水書房、2019年3月刊、306頁、5,000円
本書は、著者がこれまで国内外で公表してきた論文10篇に、新たに書き下ろした論文3篇と序文を附した論文集です。
3部で構成され、第1部は二つの章からなり、第1章では『ゲオーポニカ』についての書誌学的な考察が行われ、第2章では同書に現れる農家の一人、アナトリウスについて論じられています。
第2部は「農業と暦」と題され、七つの章からなり、第3部は「土地と耕作」と題して、四つの章からなっています。
目次は以下の通りです。
序文
第1部 『ゲオポニカ』とその著作家たち
第1章 鹿児島大学中央図書館所蔵のGeoponika(Geoponica)
第2章 On Anatolios in the Geoponika: one author or three?
第2部 農事と暦
第3章 ヘシオドスにおける農事暦
第4章 ホメーロスに見る農業
第5章 ホメーロスに見る牧畜
第6章 古典期ギリシアの農業
第7章 アッティカにおける穀物生産高
第8章 古代ギリシアの農業―段々畑は存在したか?
第9章 Irrigation Holes in Ancient Greek Agriculture
第3部 土地と耕作者
第10章 初期ギリシアにおける山林藪沢(山林原野)
―共有地(共用利用地)としてのエスカティア
第11章 Did the hektemoroi exist?
第12章 ホロイ、ヘクテーモロイおよびセイサクテイア ―ヘクテーモロイは隷属農民だったのか?
第13章 古典期アテナイの家内農業奴隷
あとがき
略語表
引用文献一覧
史料索引
ここでは、第2部と第3部の中から、新稿(第3章、第4章、第5章)と未紹介の邦文論文(第6章、第7章、第10章)の内容を簡単に紹介します。
なお、第8章、第12章、第13章の各論文は、HPの「論文紹介」で紹介していますので、そちらをご覧下さい。
第2部 農事と暦
第3章 ヘシオドスにおける農事暦(新稿)
本章では、ヘシオドスの『仕事と日々』に基づいて、まず「暦」について、我が国の四季とは季節感は異なっていたと思われるが、ヘロドトスは春夏秋冬の四季を認識していたことが説明されています。次に、「農事」に関して、穀物栽培、脱穀、ブドウ栽培、冬の仕事、木々の伐採が説明されています。そして、最後に『仕事と日々』383−617行に基づいて、「農事暦」の表が作成されています。
第4章 ホメーロスに見る農業(新稿)
本章では、ホメーロスの両詩篇を中心に初期のギリシアの農業について、栽培種(第1節)、農業技術(第2節)、穀物栽培(第3節)および果樹栽培(第4節)が考察されています。
まず、栽培種(第1節)に関しては、地中海農耕作物の特色として、一年生作物でありかつ冬作物であることが指摘されています。栽培品種としては、ピュロイ(パンコムギ)、ゼイアイ(エンマーコムギ)、クリー(クリティー:オオムギ)について、ホメーロスに現れる史料からその品種が詳しく説明されています。
そして、一般に栽培種の最古の物と見なされているオオムギが、史料の上からもコムギよりも重要な位置を占めていたことが指摘されています。最後に、キュアモス(ソラマメ)、エレビントス(ヒヨコマメ)など豆類にも言及しています。
次に農業技術(第2節)に関しては、農具の形態が耕耘用(犂、鍬および鋤)と収穫用(鎌)に分類されて、考古学資料(ブロンズ・テラコッタ像、壷絵など)を参考に考察されています。
そして、ホメーロス時代の農具はエジプトなどで見られる農具と大きな差異はなく、こうした農具を用いて行われた農業は集約的というよりむしろ粗放的であったと結論づけています。
農法については、ホメーロスの時代における農地利用の通常の形態が、1年交替で農地の半分を休ませる農法(栽培と休閑の交替)、すなわち「二圃式」であったこと、休閑地は秋には再び畑に戻され、栽培期は耕耘開始の11月から次の年の6月までの8カ月(休閑地の半分)であったことが説明されています。
また、施肥の重要性が認識されていたこと、灌漑(果樹園)設備があったことが述べられています。
次に穀物栽培(第3節)に関しては、「アキレウスの楯」の描写の解釈などから、耕耘(耕作)・播種・収穫(刈り入れ)の様子が詳細に説明されています。
さらに、脱穀についてはその形状と利用法が、ホメーロスの叙事詩からの知見により、説明されています。
すなわち、風通しの良い所に円形状に脱穀場が作られ、くびきにつながれた牛が円を描いて穀物の上を歩いて脱穀し、蓑を使って風選して殻やゴミをより分けられていたことが述べられています。また、そうした穀物はオオムギであったと結論づけています。
最後に、果樹栽培(第4節)に関しては、ブドウ栽培(ブドウ園;剪定と掘り返し;収穫;ぶどう酒製造;ブドウ酒)とオリーブ栽培(オリーブ樹と栽培法;オリーブの収穫と採油)、そしてその他の果樹(ナシ;リンゴ;イチジク)について、「アキレウスの楯」の描写、ヘシオドス、ホメロスの両叙事詩などを史料に詳細に描かれています。
著者は果樹の中でも、ブドウ、オリーブおよびイチジクが、主要な作物であったが、特にホメーロスの世界で最も盛んだったのはブドウ栽培であり、オリーブ・イチジク栽培が本格化するのはアルカイック期、アテナイで言えばソロンの時代であったろうと推測しています(79頁)。
第5章 ホメーロスに見る牧畜(新稿)
本章では、ホメーロスの世界における牧畜が考察されています。
以下、放牧と牧草地(第1節)、家畜類(第2節)、家畜飼養の目的と用途(第3節)について、簡単に紹介します。
放牧の実態は、原則として、牧草地と家畜小屋を往復する「日帰り放牧」であったこと。また、畜産は基本的に、自然の牧草に依存しており、ホメーロスの時代の牧畜は農業とリンクした小規模牧畜であったことが述べられています。(第1節)
家畜に関しては、牛、羊と山羊、豚、馬、ロバとラバ、犬、そして鳥類のそれぞれの実体がホメーロスの史料をもとに詳しく検討されています。(第2節)
そして、家畜の目的と用途については、牛(食肉と役益)、羊・山羊(羊毛生産・酪農・食肉)、豚(食肉)、馬(戦車を牽引)などについて、それぞれ詳しく述べられています。なお、養蜂に関しては、ホメーロス以降に行われたと推測しています。
第6章 古典期ギリシアの農業
本章では、第1節でクセノポン『オイコノミコス』を史料に、穀物栽培の休閑地および播種地における農作業の実態(播種・鋤入れ・刈り入れ・脱穀)と果樹栽培(ブドウ・イチジク・オリーブ)の実体が説明されています。
第2節ではテオプラストスを史料として、穀物と豆類の特徴などが検討され、アッティカではコムギにくらべてオオムギ栽培が優勢で、アテネではオオムギが主食であった可能性が高いことが推測されています。
第3節では公有地賃貸借関連の碑文(アモルゴス・アイクソネー区・ペイライエウス区・デュアレイス(フラトリア)・ラムヌース区・ヘラクレイア)等の史料の検討から当時の農法・農業の実態が考察されています。
結論として、ギリシアの農業は、ホメーロス以来、耕地は冬栽培と休閑を一年ごとに交互に行う二圃式輪作が行われており、休閑地に関しては三度すき返され、アルカイック期以降は緑肥が利用されたこと、施肥については家畜並びに人糞、また古典期には緑肥とともに焼き畑の技法が知られていたこと、農具に関しては、ホメーロスの記述により鉄製の農具の使用が想起されることが述べられています。また、ギリシアではホメーロスから古典期にかけて、農業技術の進歩・改良はあまりみられず、農業は集約的というよりむしろ粗放的であったと論じられています。
第7章 アッティカにおける穀物生産高。
本章では、碑文や文献資料から、古典期ギリシアの農法、前4世紀のアッティカの耕地面積と播種面積の割合、穀物の生産高、主食の問題が論じられています。
農法に関しては、二圃式輪作が一般的であったこと。それには二つのタイプ、(a)穀物と休閑の交互と(b)穀物と豆類の交互が存在したこと、また、そのシステムにより実際の播種面積は耕地面積の半分になることが述べられています。
また、エレウシスの会計文書(前329/8年)より、前329年のアッティカの生産高は、ジャルデの試算した合計211,319ヘクトリットル、うちコムギは20,534、オオムギは190,785ヘクトリットルが紹介されています。すなわち、コムギの生産高はオオムギのそれの1割程度に過ぎないことが述べられています。
また、アッティカの耕地可能な面積はアッティカの面積の20%、播種地は10%のジャルでの見積もりと、コムギ1ヘクタール当たり8−12ヘクリットル、オオムギ16−20ヘクリットルの推定を、妥当な数値と見なしています。
さらに、パイニッポスの地所(伝デモステネス42番)の検討から、著者はアッティカの穀物生産高は343,875ヘクトリットル、耕地可能な土地面積はアッティカ総面積の約20%と見なしています。
最後に、主食に関しては、前4世紀において、生産高(オオムギ:コムギ=10:1)、や、文献史料などから、アテネ人は貧富の差に関わりなく、オオムギを常食としていたことを結論づけています。
第3部 土地と耕作者
第10章 初期ギリシアにおける山林藪沢(山林原野)
―共有地(共同利用地)としてのエスカティア
本章では、ホメーロスの土地問題を皮切りに、初期ギリシアの土地制度のあり方が考察されています。
まず、最初にホメーロスにおける共同耕地制の存在について、「エピクシュノスアルレー(共有耕地)」の検討を中心に学説史が整理され、著者は「エピクシュノス アルレー」を「共有地」と訳出して、ホメーロスの時代にある種の共有地が存在していた可能性は大きいと推測しています。
次に、ホメーロスの時代の土地所有形態「テメノス(切り取り地)」と「クレーロス(割り当て地)」、そして「共有地」については、土地占取後、占有地は占有した共同体のものであり、共有物として共同体全員の手中に帰し、デーモスと呼ばれる「共同体成員」によって王や戦功ある功労者にテメノスが切り取られ、次に共同体の各成員にクレーロスが分配された。そして、この占有地のうち分配されなかった部分が共有地として残されたのではないかと推測しています。そして、未配分の土地=無主の土地=共有の土地という関係を想定しています。
最後に、著者はアリストテレスや碑文史料などの検討から、デーモシオス(公の)の観念は市民共同体としての都市国家(ポリス)成立後、具体的には前7・6世紀に現れ、デーモシオスの出現と共に「国家」の観念も明確化したと考えています。
そのことは、土地制度の上では、ホメーロスの時代に「共有地」と認識されていた土地が、ポリス成立以降は「公有地」と「ヒエラ(聖なる地)」として認識されたと推定しています。
「おわりに」で、著者は「公有地」という観念はホメーロスの時代にはまだ存在していなかった。それは、その時代にポリスとしての「国家」の観念が未発達の状態であったことと関係しており、それゆえ、ホメーロスの時代に「共有地」という語の使用は可能でも「公有地」の言葉は使用できないこと。
前7・6世紀におけるデーモシオスの語の出現は、「公」あるいは「国家」の観念の存在の証しであり、このときに「アクレーロス・エスカティア(未墾の無主地:共有地)」が国家のものであるという観念も出現したこと。
この観念の出現と前6・7世紀におけるポリスによる土地に関する共同体規制の出現とは、密接不可分の関係にあったと推定されると述べています。
(2021/04/20)
高畠純夫・齋藤貴弘・竹内一博『図説 古代ギリシアの暮らし』

高畠純夫・齋藤貴弘・竹内一博『図説 古代ギリシアの暮らし』河出書房新社、2018年11月刊、127頁、2,000円
本書で語られているのは、古代ギリシアの前5,4世紀の状況です。
特に、古典期アテナイの暮らしの諸相が、第1章「アテナイの景観」、第2章「アテナイ市民の一生」、第3章「ポリスに生きた人々」、第4章「日常の生活のなかで」と章立てられ、トピック(15のコラム)を挟みながら、詳しく描かれています。
本書の特徴は、「図説」とあるように、約200点にのぼる図版(陶器画を中心に、テラコッタ、彫刻、墓碑、顕彰碑など)です。
こうした図版は、当時のアテネの生活(衣食住、社会規範、娯楽、性愛、宗教、祭、死生観など)を我々に生き生きと見せてくれます。
眺めるだけでも楽しい本ですが、多くの古典史料(プラトンや、アリストパネスの喜劇、法廷弁論など)を引用しての市民生活の説明は、具体性に富んでいてとても興味深く読むことができます。
また、「度量衡・貨幣の一覧」(72頁―73頁)、「陶器の形状と名称」(107頁)、詳細な「アテナイの祭日の一覧」(120-121頁)なども利用するのに便利です。
(2020/04/29)
J.G.ゲイジャー編/志内一興訳『古代世界の呪詛板と呪縛呪文』

ジョン・G・ゲイジャー編/志内一興訳『古代世界の呪詛板と呪縛呪文』京都大学学術出版会、2015年12月刊、472頁、5,400円
原著は、John G.Gager,Curse Tablets and Binding Spells from the Ancint World,Oxford,1992 です。
目次
凡例
略語
はじめに
序章
呪詛板の素材
呪詛板に記されたメッセージ
神々、精霊(ダイモン)たち、死者の霊魂
人形、髪の毛、釘—呪詛板の付属品
小像の利用
頭髪と衣服の利用
丸める、折りたたむ、釘で封をする
呪詛板の安置
呪詛板の追求する効果
呪詛板は効果があったのか
呪詛板と法律との関係
「魔術」と「宗教」
ギリシア・ローマ時代以前および以後における呪詛
第1章 競技呪詛板—劇場や競争場で
史料の解説と翻訳(No.1〜17)
第2章 性愛の呪詛板—セックス、愛、そして結婚
史料の解説と翻訳(No.18〜36)
第3章 訴訟・政争—「法廷で舌が麻痺済ますように」
史料の解説と翻訳(No.37〜59)
第4章 ビジネス、商店、酒場での呪詛板
史料の解説と翻訳(No.60〜82)
第5章 正義と復讐を求める嘆願呪詛板
史料の解説と翻訳(No.83〜101)
第6章 その他の呪詛板
史料の解説と翻訳(No.102〜118)
第7章 護符、解毒呪文、対抗呪文
史料の解説と翻訳(No.119〜134)
第8章 文学史料、碑文史料の証言
資料の解説と翻訳(No.135〜168)
特殊用語解説
訳者あとがき
本文注
索引
内容
「訳者あとがき」に翻訳者の丁寧な本書の解説が載っていますので、以下、その一部を引用して、内容の紹介に代えさせて頂きます。
本書は、古代ギリシア・ローマ世界におこなわれた「呪い」について伝える代表的な史料、全168点が、理解の助けとなる解説や文献とともに紹介されています。
本書のテーマは、名もなき一般人が製作した(あるいは、製作させた)、古代ギリシア・ローマ時代の「呪詛板curse tablet」、および彼らの強い思いが託された「呪詛呪文binding spell」です。
古代世界の呪詛板のうち、約1600点がいまに伝わっています。
そもそも呪詛板とは何なのかについて、本書の初めで、こう定義されています。
「他の人間や動物に対して影響を及ぼしてもらおうと、超自然的な力を招来するために用意された、たいていが小さくて薄いシート状の、文字の刻まれた鉛の簿片」。
さて、その内容ですが、日本において「呪い」は超自然的な力を及ぼして「呪い殺す」など、相手に危害を加える努力とイメージされるのが普通です。
しかし、本書に収められた事例は、多くの場合に願われていたのは、相手を傷つけることより、むしろ「呪縛」することでした。
自分の願いや欲望がかなえられるようにと、その妨げとなる他者、あるいは思いを寄せる人の行動や心を、呪詛板に書かれた呪文の力で縛りつける。
そうして呪縛された相手をコントロールし、自分にとって望ましい未来が手に入るようにする。
このように呪詛板には、おもに誰かを縛りつけることを願う「呪縛呪文」が記されていたのです。
次に、呪詛板の歴史については、自分を訴えた敵対者の舌を法廷で縛り、自由にしゃべれなくすることなどを願う「訴訟・政争呪詛板」(本書第三章)として始まると理解されています。
その後、さらに別の対象へと用途が拡張され、本書では、各種の競技会において、ライバルの身体の動きや戦意などを呪縛し、勝利を手にできるよう願う「競技呪詛板」(同第一章)、恋がたきや恋の相手を呪縛し、自分の望むような性愛関係が生まれるよう願う「性愛呪詛板」(同第二章)、さらには商売上の競合相手を呪縛し、自分の利益確保を願う「商売呪詛板」(同第四章)として分類されています。
そして、該当する事例が、それぞれ一章にまとめられています。
「その他の呪詛板」(同第六章)は、呪詛の背景が不明なために分類できない事例です。
「正義と復讐を求める嘆願呪詛板」(同第五章)は、呪詛板の歴史の中では比較的あとになって登場しており、そこでは自分に対する不正に関し、その補償、ないしは犯人への処罰がなされるよう、神に対して嘆願されています。
一方、呪詛板の効力を解いたり、あるいは返しの呪文で対抗したりするための、様々な「護符・お守り」が数多く発見されており、それらもまとめて紹介されています。(同第七章)
また、古代世界で記された文学作品の中にも、呪詛板についての数多くの言及があり、そうした証言についても豊富に紹介されています(同第八章)
次に、そもそも呪詛板には効果があったのかという問題について、本書の著者ゲイジャーは、この問に対して果敢にもこう断言します。
「呪詛板には効果があった。あるいは効果があると信じられていた。そして、効果があることと、効果があると信じられていたこととは、結局同じであると。」
では、何を根拠に、呪詛板が効いたと断言できるのでしょうか。
その一番の理由として指摘されているのが、呪詛に関する証拠の、約1200年以上(紀元前5世紀初頭〜紀元後8世紀頃まで)という時間的広がりです。
呪詛板に効果があったとする以外に、こうした行為をこれほど長く続けた古代人の、このあくなき非合理性をどう説明できるだろうかと、筆者は問いかけています。
だとすると呪詛板は、どのように効果を発揮できたのでしょう。著者はまず、言葉の持つ力に古代人がよせた全幅の信頼について指摘しています。
言葉は不思議な力を持ち、その力は人間界の境界を越えて「あちら」の世界にさえも届くという信頼感です。(例えば、日本語の「言霊ことだま」という言葉は、その信頼感の名残なのかもしれません)
そのうえで、著者がもっとも重視するのが、1世紀後半の博物学者、大プリニウスによるこの証言です。「呪詛板によって呪縛されることを恐れない人はいない」(本書No.146)。
社会的エリートにして当代最高の知識人である大プリニウスを含め、社会階層を問わずあらゆる人が、呪詛板で呪縛されることを恐れていたのです。
呪縛されることを恐れる「心的風土」が、社会の成員の間に「満場一致」で共有されていた時代。呪詛板は効くと誰からも信じられていた。だから、呪詛板は効いた(あるいは効いたと信じられた)。その信頼ゆえに、呪詛板は1200年にわたって利用され続けた。
著者はそのように考えています。
最後に、「宗教」と「魔術」との関係という問題に言及しなければなりません。
つまり、呪詛板をもちいてほかの人を呪縛しようとする古代人たちの努力は、宗教とはまったく相容れない、非合理的で迷信的な「魔術magic」の一種として理解されるのでしょうか。
著者がこの点についてとっていたのは、「人間の経験を定義する分類項目としては、<魔術>という項目は存在しない」との立場です。
著者は、理想的な「宗教」と相容れない要素のためのゴミの山。それが、「魔術」という言葉だと言います。もちろん、著者は「魔術」という言葉をそうした意味で使うことに強く反発しています。
著者は本書で、宗教と魔術との間に伝統的に引かれてきたこの境界線を、懸命に乗り越えようとしているのです。
(2018.8.20)
高畠純夫『ペロポネソス戦争』

高畠純夫『ペロポネソス戦争』東洋大学出版会、2015年11月刊、239頁、2200円
本書は、「トゥキュディデスの史料に依拠して、そこに語られるエピソードを再構成し、それに関わる人間の心理を推測し、そうした行動を取らせたポリスのあり方を探りだそうとするもの。」(「はじめに」)であり、トゥキュディデスの『歴史』(以下、史料)に基づき、「ペロポネソス戦争」のいくつかの主要なテーマが、従来の研究書や著者の実際の現地での踏査も踏まえて記述されています。
本書の構成は、以下の通りです。
はじめに
第一章 アルキダモスの苦悩
第二章 プラタイアの場合
第三章 アテナイ開戦
第四章 ペリクレスの思い
第五章 ミュティレネの場合
第六章 ケルキュラの場合
第七章 シケリア遠征
第八章 終章
あとがき
使用文献
関連年表
索引
以下、簡単に、各章の内容を紹介します。
第一章 アルキダモスの苦悩
本章では、ペロポネソス開戦に至るスパルタ王アルキダモスの演説(前432年)(史料:Ⅰ80—87)から、彼の心理や当時のスパルタの状況が読み解かれています。
ギリシア人の気質に関して、アテナイ人は俊敏で進取の気性に富む」が、スパルタ人は「鈍重で臆病」といったトゥキュディデスの議論を、その証拠はないと否定しますが、ただ、そのポリスの気質の存在という事実は、「ギリシア人と言う意識があるとしても、各人はそれぞれのポリスの独自性を負った人間であって、気質の議論は彼らの独自性を高める一方で、彼らをそれぞれのポリスに押し込める役割も果たしていただろう。(22頁)、と述べています。
第二章 プラタイアの場合
本章では、ペロポネソス戦争の開戦の契機となった、テーバイ人のプラタイアイの攻撃(前431年)(史料:Ⅱ2-6)から筆を起こし、前429年のスパルタ王アルキダモスのプラタイア攻城戦、ならびに包囲戦が描かれています。(史料:Ⅱ71−78)
結局、プラタイアはスパルタに降伏し、裁判では「スパルタに何か良きことをした者だけが正義として」降伏者は処刑されます。
著者は、こうした過酷な措置が取られた背景として、スパルタの事情、みせしめとしての効果の期待、土地の使い道などを挙げ、「かくて、小さな国プラタイアに起こったことは、その他の小さな国に起こるだろうことを象徴して、ペロポネソス戦争の一つの側面を示した。」と結んでいます。(45頁)
第三章 アテナイ開戦
冒頭、スパルタ王アルキダモスの、オイノエの要塞の攻撃に始まる開戦(前431年)(史料:Ⅱ18−23)、そしてそれに続くアテナイのペロポネソス半島を周航する遠征(Ⅱ23、24−33)の戦闘が語られています。
ペロポネソス戦争の開戦1年目の戦争の特色として、実際の戦闘の少ないこと、戦争は、相互の略奪・破壊という面が強かったことが述べられ、続いて、当時のアテナイを理解する上に重要な鍵となる、有名なペリクレスの葬送演説が一節ごとに訳されて、解説されています。
著者は、葬送演説での「民主政(デーモクラティア)の政体」(史料Ⅱ37)、「都市の魅力」(史料Ⅱ38)、「開放主義」(史料Ⅱ39)、「アテナイ人の気質」と「国家の性格」(史料Ⅱ40)などは、ペリクレスによるアテナイの理想化にすぎず、その変節は目前に迫っていたと述べています。
第四章 ペリクレスの思い
本章では、疫病によって亡くなるペリクレスの最後の演説(史料Ⅱ63)から、彼の「栄光のアテナイ」の思いが述べられています。
彼の思いは、ペリクレス死後のデマゴーゴイの一人であるクレオンによって拡大引き継がれ、「戦争を長引かせた一つの原因は、アテナイを長く縛りつけることとなった彼の思いにあったであろう。」と結んでいます。(109頁)
第五章 ミュティレネの場合
本章は、前428年のデロス同盟の同盟国であったミュティレネのアテネからの離反、そして、その後のアテネによる鎮圧とその結末が述べられています。
鎮圧後のミュティレネの処遇をめぐる、アテナイでの有名なミュティレネ論争、
すなわち、クレオンの主張した前日の決議(すべての成人したミュティレネ市民の処刑、女子供は奴隷。)に対して、再度民会が開かれ、処刑を主張するクレオン(史料Ⅲ37−40)と処刑に反対のディオドトス(史料Ⅲ42−48)両者の論戦が論じられています。
結局、前日の決議がひっくり返り、急ぎ別の船が仕立てられ新しい知らせの船が送られます。
ミュティレネでは、先の知らせにより、処刑が実行されようとしているまさにそのときに、次の船が到着し処刑は阻止されます。
その情景が想像豊かに描かれています。
第六章 ケルキュラの場合
本章では、前427年のケルキュラの内乱について、史料(Ⅲ70—85)に基づいて記述されています。
トゥキュディデスの利益論について触れられ、そしてケルキュラの党派争いの具体的状況が描かれています。
そして、ケルキュラの事例が示唆するのは、国制の重要性を認識したから人々が変革を求めたわけではなく、各派のおのおのは、自らの権力を確立するために国制が重要だったから体制の変革を求めていった、と指摘しています。
著者は、ケルキュラ内乱について、「国内の小さな対立が、スパルタとアテナイとの敵対関係を背景に、「寡頭派」と「民主派」という明確な敵対勢力に整序されて、ついには憎悪渦巻く殺しあいへと発展する、それがこの戦争(ペロポネソス戦争)が多くのポリスにもたらしたことであった。」(169頁)と述べています。
第七章 シケリア遠征
本章では、ペロポネソス戦争で最大の悲劇と言われた、シケリアの悲劇が史料(Ⅶ21-87)に基づいて描かれています。
最初に遠征の悲劇の概要、さらにその遠征の背景などが述べられて、著者によるアテネ民会の気まぐれとそれに対応した将軍ニキアスの性格・心理などが分析されています。
終章 結末
本章では、クセノフォン『ヘレニカ』の史料により(トゥキュディデスの『歴史』は前411年夏で突然終わっており、その後をクセノフォンが記述)、ペロポネソス戦争の結末、アイゴスポタモイの戦いの敗戦を契機としたアテナイの降伏が描かれています。
最後に、「アテナイが降伏条件を認めたのが前404年の4月初め、そしてリュサンドロス(スパルタ将軍)がアテナイにやってきたのがアテナイのムニュキオン月16日でそれは4月25日か26日頃にあたると計算されている。
前431年3月のテーバイ軍のプラタイア進撃から始まった戦争(第二章)は、前404年4月初めまで「わずかの日を別にして」(Ⅴ26.3)ちょうど27年間続いたことになる。」と締めくくられています。(203—4頁)
本書の特徴は、各章の冒頭、並びに本文の随所に、史料に即した「物語」が想像豊かに語られて、「ペロポネソス戦争」が手に取るように生き生きと描かれていることです。
物語としても面白く、研究書と一般書の間のような印象を受けましたが、トゥキュディデスの『歴史』の格好の入門書・手引き書になると思います。
なお、「あとがき」によりますと、この本は著者の勤め先の東洋大学に出版会ができ、公募による最初の公刊書とのことで、個人的には出版までに至るいきさつも興味深かったです。
(2016.9.9)
阿部拓児『ペルシア帝国と小アジア』

阿部拓児『ペルシ帝国と小アジア —ヘレニズム以前の社会と文化ー』京都大学学術出版会、2015年1月刊、322頁、4800円
本書は、「あとがき」によると、著者が2008年に京都大学大学院文学研究科に提出した学位論文「ペルシア帝国期小アジアにおける文化・社会・歴史叙述」の前半部をもとにしています。
目次は、以下の通りです。
序章
第一章 ペルシア帝国と小アジアの「首都」サルディス
第二章 第二の総督区「首都」ダスキュレイオン
第三章 小アジアの辺境リュキア
第四章 カリアとヘカトムノス朝
第五章 ヘロドトス時代のハリカルナッソスの言語状況
第六章 キュプロス島とサラミス王エウアゴラス
終章
あとがき
初出一覧
参考文献
略語一覧
索引(人名・事項)
序章
本書の課題が、序章で次のように述べられています。
「ペルシア帝国支配(とペルシア人入植者)に対する地域社会。文化の反応を小アジアの北端(ダスキュオン)から南端(カリア・リュキュア)、さらには海を越えたキュプロス島までを対照とし、総合的・横断的に比較考察することを目標に掲げる」と。(3頁)
以下、各章の「おわりに」を中心に、内容を簡単に要約し紹介します。
第一章 ペルシア帝国と小アジアの「首都」サルディス
本章では、都市サルディスの都市景観の概観に始まり、ギリシア語碑文・リュディア語碑文の分析がなされています。
そして、「ペルシ帝国期のサルディスにおいては、日常業務(行政・商取引)や婚姻関係などの接触・交流を通じて、本来は他者のものであった宗教や言語をお互いに受容していくことにより、リュディア人、ギリシア人、ペルシア人という移住当初の自他の境界線が曖昧になったこと」、が結論づけられています。(64頁)
第二章 第二の総督区「首都」ダスキュレイオン
本章では、ダスキュレイオンの都市の景観とアクロポリスから出土した封泥の分析がなされています。
まず、都市の景観は、その発掘調査からサルディスとは違って、総督府、文書館、火祭壇を備えた聖域、城壁、パラディソス(樹木や動物に満ちた庭園)といった、ペルシア人入植者が統治の際に作り上げた施設群が見いだされること。
そして、封泥の分析からは、そこに含まれる大量のペルシア大王の銘は、ダスキュレイオン総督と大王の太いパイプと都市の重要性が示唆され、そこに含まれる少なからぬアラム語の人名は、そこでの行政が入植者によって独占されていたことが推測されています。
また、封泥に描かれた、アフラマズダ信仰やパラディソスでの狩りなどの図柄からは、ペルシア人達の生活様式が再確認にされ、入植者たちが帝国中央で送っていた生活をそのまま持ち込んだ結果を反映していると考えられています。
(93頁)
第三章 小アジアの辺境リュキア
本章では、小アジアの辺境リュキアについて、主に墓碑銘の分析を通して、外国の支配・干渉とその文化的な影響が論じられています。
リュキアにおける外国支配の実態は、時系列的には、ペルシア支配のもとでの自治、それに続くアテナイの支配(ギリシ語の流入)、アテナイのデロス同盟政策失敗後のペルシアの再統治と続きます。
しかし、ギリシア人・ペルシア人共に入植者の規模はきわめて小さく、人名の分析による限りでは、リュキア人が入植者や彼らが持ち込んだ文化と長期的、日常的に接触する機会は限られていたために、外新の新勢力による在来の文化に対する影響は、表面的な段階にとどまっていたと推測されています。(127−28頁)
第四章 カリアとヘカトムノス朝
本章では、ペルシア帝国期カリアにおいて、前四世紀初頭のヘカトムノス朝の成立を一つの画期に据えたクロノロジカルな分析が試みられています。
まず、ヘカトムノス朝は、カリアにおいて盛んであった排他的なゼウス・カリオス信仰ではなく、自身終身祭司を務めるゼウス・ラブラウンドス信仰に背極的に関与して、ラブラウンダ聖域を整備しカリア内に広く浸透させ、同時に、ハリカルナッソスに首都を移し、そこをカリア第一の都市とすべくさまざまに手を加えます。(マウソロス廟の建設など)
ハリカルナッソスにおいては、名望家であるヘロドトスの出身家系や不動産売買に関する二つのギリシア碑文から明らかなように、すでに前五世紀の段階で先住のカリア人と入植者ギリシア人の共同体間で、積極的に通婚がおこなわれており、また、隣接するカリア人居住地であったサルマキスとも政治的に協力していましたが、しかしその二つの政治共同体は以前併存状態でした。
しかし、ヘカトムノス調は、ハリカルナッソス周辺のカリア人都市(6都市)を吸収合併し、それに対応して併存していた二つの共同体(ギリシア人とサルマキス人)を包み込むように城壁を建設し、街道で東西を結ぶなどの都市計画を経た結果、碑文からは従来の二分された(ギリシア人とサルマキス人)共同体の消滅が読み取れます。
以上の分析から、著者はペルシア帝国期カリアにおいては、ヘカトムノス朝成立以前から先住共同体(カリア人)と移住共同体(ギリシア人)間の文化的差異が薄弱になっていたこと、そしてヘカトムノス朝が総督位を世襲すると、彼らがなした種々の業績によりこのような傾向が一層加速したと結論づけています。
ただし、著者は、サルマキスの解体などの政策は、ヘカトムノス家の「カリアの国民統合」などの政治的意図を読み取らずに、むしろ別目的で行った副産物であったと理解しています。(176—177頁)
第五章 ヘロドトス時代のハリカルナッソスの言語状況
本章では、ヘロドトスはサモス島にてイオニア方言を習得したという『スーダ辞典』の記述と、イオニア方言で書かれたハリカルナッソス出土の「リュグミダス碑文」の矛盾をいかに解消するかという課題から論を起こしています。
著者は、この問題に対して、公的/書かれた文書と日常/話し言葉の差異を認め、またイオニア方言が単一性/均質性を保ってはいなかったことから、「ヘロドトスは若かりし頃ハリカルナッソスのイオニア方言を用いており、しかし長じてサモス島にて「模範的な」イオニア方言を習得した」、と単純明快な結論を導き出しています。
また、ハリカルナッソスの言語状況については、時系列に沿って、次のようにその発展が論じられています。
ヘロドトスより数代前、ギリシア系の植民者たちは、ドーリス方言を話していた。
しかし、ハリカルナッソスがドーリス系の都市同盟から追放される前後、近隣のイオニア系都市から徐々にイオニア方言が流入した。
都市建設以来、彼らギリシア人の言語は、カリア系住民との通婚、もしくは日常的接触・交渉により、カリア語によって影響を受けたであろう。
しかし、その一方でハリカルナッソスでは、カリア語が廃れることなくヘロドトスの時代まで生き延びていた。
そして、日々のコミュニュケーションのために新言語が必要とされ、今日のヘロドトスのテクストから想像するのとはかなり異なったイオニア方言が創出された、と論じています。
なお、最後に著者は、ヘロドトスのカリア語の知識について、ヘロドトスにとってカリア語は従前の研究者たちが想定した以上に身近な存在であり、あまりにもなじみ深いトピックスであったかゆえに、わざわざ取り上げるに値する程の対照とは思わなかった(史書で三度しかカリア語に言及していない)のであろうと補足しています。(211—13頁)
第六章 キュプロス島とサラミス王エウアゴラス
本章では、前六世紀の中頃からペルシア帝国の版図に入ったキュプロス島の社会・文化について、ペルシア帝国の統治政策によるギリシア人とフェニキア人の「民族対立」という図式を批判的に検討し、以下のような新たな歴史像が示されています。
まず、陸軍国家であったペルシア帝国にとって、海洋国家の集団であるキュプロス島の支配は容易ではなく、また海軍力の供給地であったことから、大量入植は控え、ある程度、島内の都市王朝(サラミスなどのギリシア系都市、キティオンなどのフェニキア系都市など)は自治を認められていた。
そして、ギリシア系・フェニキア系の各都市王朝は、離散集合を繰り返し、ペルシア帝国はその都度、利害を一致する都市と手を組み、ペルシア帝国=フェニキア系都市キティオンという構造的同盟関係は、そこには見いだせない。
さらに、キュプロス出土の碑文からは、ギリシア人とフェニキア人との文化的対立は存在、あるいは鮮明であったとは想定しがたいが、結局、島外のギリシア人にしてみれば、島内のギリシア人もフェニキア人も、いずれも「バルバロイ」であった。
前四世紀前半にアテナイと交流を保ちながら活躍したサラミス王エウアゴラスが、キュプロス音節文字に代わってギリシア文字を最初に採用したことは、それまで島内にはほとんど浸透していなかった文化形態(ギリシア語)を、はじめて公的・政治的に導入し推進したのであり、イソクラテスが、「バルバロイ生まれの市民をギリシア人に変えた」(頌詞『エウアゴラス』)と主張するのは、彼エウアゴラスがサラミス住民(あるいはその先にあるキュプロスの住民)を「ギリシア人に戻した」のではなく、「ギリシア人に変えた」ことを意味した。しかし、ギリシア語文字の採用は、エウアゴラス死後は結局、深く根付くことはなかった。(252—53頁)
終章
本章では、これまで論じられてきたペルシア帝国に組み込まれた小アジアの各地域(前六世紀半ば〜前四世紀後半)を比較しながら、これまでの考察がまとめられています。
まず、中央から総督が派遣されたサルディスとダスキュレイオンに関しては、
前者では、日常業務(行政・商取引)や婚姻関係をなどの接触・交流を通じて、リュディア人、ギリシア人、ペルシア人という移住当初の自他の境界線が曖昧になっていったこと。
後者では、その社会生活がペルシア人を中心とした入植集団とその子孫によって主導されていたこと、が想定されています。
そして、著者はその両都市間の差異は、ペルシア帝国領に組み込まれる以前の、両都市の発展段階の違いによってもたらされたと考えています。
次に、ペルシア帝国の支配の影響が認められる典型とされるリュキアとキュプロスに関しては、前者では、ギリシア、ペルシアの外来の新勢力による在来の文化に対する影響は、表面的な段階にとどまっていたこと。
後者に関しては、従来想定されていた島内のギリシア系住民とフェニキア住民(と彼らを支持、利用していたとされるペルシ人)との構造的な社会的・文化的対立は認めることができなかったこと。
島外からの影響に関しては、ペルシアについてはその影響は少なかったこと。そしてエウアゴラスがギリシア文字を公的に採用したことは、島外からの文化的影響と見ることが出来るが、ギリシア文字の採用は深く根付くことはなかったこと。
また、これらの二地域は自治が許されていたが、ペルシア帝国の版図に組み込まれたことで、アテナイ海上帝国とペルシア帝国との駆け引きの渦に飲み込まれて、さまざまな反応をみせたことが指摘されています。
最後に、独自の展開を見せたカリアに関しては、ハリカルナッソスにおける言語状況の分析から、ギリシア人とカリア人の自他の境界線は、加速度的に曖昧になっていったこと。
前四世紀に入り、在地の支配者のヘカトムノス家が総督に任命されることにより、カリア全域にわたる改革、ならびにハリカルナッソスの都市開発が進められ、そこにギリシア人の植民活動と先住カリア人の記憶が不可分に結びついた都市の物語が誕生したこと。
そして、ペルシア帝国がヘカトムノス家を総督に指名したのも、前五世紀末の小アジアへのアテナイとスパルタの拡大施策という、小アジア西部の情勢不安によるものと指摘されています。
最後に、著者は、本書刊行の前年に出版されたE.R.M.デュシンベリーが、小アジアの地域的多様性を無視し、小アジアを一つの地域として見て、「ペルシア帝国期に小アジアが見せた社会・文化の変化とは、帝国による支配(上から下への作用)と地域の自治(下から上への抵抗)とのせめぎ合いであった。」という結論を、地域ごとの特徴なり特殊性を無視することはできないと批判して、広い文脈において、本書の結論を、以下の三つのパターンに類型化しています。
(1)ペルシア人入植者が帝国中央での生活をそのままのかたちに近い状態で持ち込めた地域(ダスキュレイオン)。
(2)ペルシア人の集団入植がなされず、しかしペルシア帝国の版図に置かれたという事実によって間接的に変化をこうむった地域(キュプロスとリュキア)。
(3)その中間にあって、ペルシ帝国の一領土であったゆえに、既存社会内、あるいはペルシア人入植者を受け入れた新たな社会において自他の境界線が大いに揺さぶられた地域(サルディスやカリア)。
そして、これらの類型を決定づけていたのは、ペルシア時代以前からの状況(サルディスとダスキュレイオンの差異)、ペルシア帝国統治にとっての重要性(前記二都市とリュキア・キュプロスとの差異)、および主にペルシア帝国とアテナイ(あるいはアテナイと覇権を争ったスパルタ)間の国際的な力関係(デロス同盟期以降のカリア、リュキア、キュプロス)などの要因であったと、説明されています。(263—71頁)
(2016.8.25)
周藤芳幸『ナイル世界のヘレニズム』
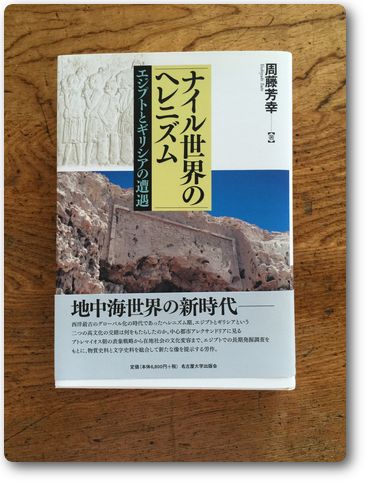
周藤芳幸『ナイル世界のヘレニズムーエジプトとギリシアの遭遇—』名古屋大学出版会、2014年11月刊、423頁、6800円
「あとがき」によれば、本書は、著者が15年余りエジプトで行ってきた現地調査を踏まえて、これまでの研究成果をまとめたものです。
既発表の論文に関しては、「あとがき」で初出が明記されていますが、全体として書き下ろしの著作となっています。
本書は、5部17章から構成されています。
目次は、以下の通りです。
序章
第Ⅰ部 ヘレニズム史の再構築に向けて
第1章 プトレマイオス朝エジプト史研究の新展開 –「オリエント的ディスポティズム」を越えてー
第2章 アコリス遺跡の考古学 —ヘレニズム時代を中心としてー
第3章 ヘレニズムへの道 —アレクサンドロス以前のナイル世界とエーゲ海世界—
第Ⅱ部 ナイルのほとりのヘレニズム世界
第4章 都市アレクサンドリアの成立 —ヘレニズム文明の磁場の創造—
第5章 セーマ・大灯台・図書館 —表象とモニュメントの世界—
第6章 初期プトレマイオス朝の宗教政策 —支配者崇拝から王朝祭祀へー
第Ⅲ部 領域部の文化変容
第7章 プトレマイオス朝とエジプト領域部の開発 —ファイユームの水利事業を中心としてー
第8章 採石場のヘレニズム —ニュー・メニア古代採石場の調査成果からー
補論 ローマ帝政期の軍団と採石場
第9章 ケファラスの子ディオニュシオスとその世界 —前二世紀末エジプト
在地社会の一断面
第Ⅳ部 在地エリートの対応
第10章 トゥナ・エル・ジェベルの「ペトシリスの墓」 —イメージの文化変容
第11章 ヘルモポリスのアーキトレイヴ碑文 —王権・軍団・在地エリートー
第12章 ヘルモゲウスの子ハコリスの磨崖碑文 —甦る在地エリートの素顔—
第13章 ロゼッタ・ストーン再考 —王権と在地神官団との相互交渉—
第Ⅴ部 東地中海とナイル世界
第14章 初期プトレマイオス朝とエーゲ海世界 —ギリシア諸都市との関係を中心としてー
第15章 地中海の構造変動とナイル世界 —南部エジプト大反乱をめぐってー
第16章 地中海の海上交易とナイル世界 —アコリス遺跡出土アンフォラからの考察—
第17章 東地中海コイネー文化の成立 —物質文化のヘレニズムをめぐってー
終章
あとがき
注
参考文献
図版一覧
索引
本書は、初期プトレマイオス朝の時代に注目し、ヘレニズム時代の現象が首都アレクサンドリアだけではなく、内陸のナイル川流域に生きる人々の文化をどのように変えていったのか、またその変化の契機となったのは何だったかを、中エジプト・アコリス遺跡の現地調査の成果に基づきながら明らかにしています。
「序章」に読者の理解を助けるための簡潔な本書の概要が記されています。
また、そこでは著者によって、本書がプトレマイオス朝エジプト史のトピックを網羅的に検討することを目的とするのではなく、議論の対象も、あくまでアコリス遺跡における現地調査の過程で解明を迫られることになった個別の問題に限定されているが、それらはいずれもヘレニズムという複雑な歴史現象を考える上で看過することが出来ない問題である、ことが述べられています。(p.7)
以下、その概要なども参考に簡単に本書の内容を紹介します。
第Ⅰ部「ヘレニズム史の再構築に向けて」
第Ⅰ部は導入部となっています。
第1章「プトレマイオス朝エジプト史研究の新展開」ではプトレマイオス朝を研究することの現代的意義の確認、近年の研究動向の再検討がなされ、それを受けて第2章「アコリス遺跡の考古学」では著者の現地調査(アコリス遺跡)の概要が紹介され、第3章「ヘレニズムへの道」ではエジプトとギリシアとの文化交流のあり方を相対化するために、ヘレニズム時代以前の歴史(第二中間期から末期王朝時代)が通時的に検討されています。
第Ⅱ部「ナイルのほとりのヘレニズム世界」
第Ⅱ部では、プトレマイオス王朝の形成過程に関して論じられています。
まず、第4章「都市アレクサンドリアの成立」ではアレクサンドリアがヘレニズム時代の中心として発展していた経過が、その都市プランを中心に論じられ、第5章「セーマ・大灯台・図書館」ではポリス世界からヘレニズム世界へと移行する大きな流れの中で、独自の表象とモニュメントの役割としてのアレクサンドロス大王の墓(セーマ)、大灯台、図書館及びムセイオンなどの検討がなされ、そして第6章「初期プトレマイオス朝の宗教政策」では宗教の領域において、初期プトレマイオス王朝がギリシア的な支配者崇拝の振興、新たな神(サラピス神)の導入、王朝祭祀の確立という三本柱のもとに推進されたことを明らかにしています。
第Ⅲ部「領域部の文化変容」
第Ⅲ部では、プトレマイオス朝の確立にともなってエジプト領域部で生じた文化変容の実体が考察されています。
第7章「プトレマイオス朝とエジプト領域部の開発」では、ファイユーム盆地の水利事業などによる耕作地の拡大、及びギリシア人の入植に伴う領域部の農業面(オリーブ・ブドウ栽培)並びに、ギリシア人役人による行政面での文化変容について述べられています。
また、第8章「採石場のヘレニズム」では、中エジプトのニュー・メニア古代採石場での現地調査の成果をもとに、プトレマイオス二世の末から三世にかけての時期のギリシア語及びデモティックの二言語併記の考古学的分析より、ギリシア語が記録的用語としての地位を獲得していく過程、すなわちデモティック単独使用からデモティックとギリシア語の併用、さらにギリシア語単独使用へと推移した過程を明らかにしています。
さらに、補論「ローマ帝政期の軍団と採石場」では、ゼウス神への奉納碑文が刻まれた祭壇の再発見による詳細な観察結果をもとに、ローマ帝政期のアコリスでのローマ軍団と採石活動(採石場の監督など)の関係が論じられています。
第9章「ケファラスの子ディオニュシオスとその世界」では、ケファラスの子ディオニュシオスに関する家族文書集積(ギリシア語とデモティックの二言語併用テクスト)を考古学的調査の結果に照らしながら検討されています。
著者は、考古学的証拠からのアブダクション(仮説による推論)の方法論を用いて、ケファロスのワイン購入ならびにディオニュシオスによる小麦の賃貸に関する史料の検討により、ディオニュシオスの二つの顔、「ギリシア人」の世界と「エジプト人の世界」の両世界を介しての経済活動を明らかにしています。
さらに、後1世紀において、補論でのアコリス周辺の採石場における採石作業にローマの軍団が深く関与していることから、この軍団もまた、ディオニュシオスのような人物を在地社会の仲介者としながら、採石場を中心とするローカルな経済活動に関与していたのではないかと推測しています。
第Ⅳ部「在地エリートの対応」
第Ⅳ部では、ヘレニズムの波の中で隠然たる力を保ち続けた在地エリートの姿を追っています。
第11章「ヘルモポリスのアーキトレイヴ碑文」では、前三世紀半ばのヘルモポリスの建築物のアーキトレイヴ(ギリシア建築の梁の部分)碑文から、在地社会における王権、ギリシア人駐屯軍団、エジプト人在地エリート(神官団)の関係を考察しています。
著者は、この碑文がプトレマイオス三世の行幸に対するヘルモポリスのギリシア人騎兵隊、およびエジプト人の神官団の対応として成立した可能性を認め、王権に対する自らの地位と特権の保全を求めた神官団、すなわち隠然たる力を保ち続けた在地エリートの姿を明らかにしています。
第12章「ヘルモゲウスの子ハコリスの磨崖碑文」では、関連するパピルス文書とこの磨崖碑文のコンテクストの検討、ならびにこの碑文のモニュメンタルな性格、さらにテクストの分析ならびに、奉納の主体であるハコリスのプロソフォグラフィの検討などがなされています。
著者はこの磨崖碑文が南部大反乱の際にプトレマイオス王朝と経済的な関係を勢力基盤とする在地エジプト人エリート・ハコリスが、危機の時代のさなかに王権との同盟関係を強くアッピールする目的で制作したものであると論じています。
さらに、「おわりに」で、ギリシア語の奉納碑文の形態とエジプトの神々の像などの図像的エレメントを持つ磨崖碑文の形態が、ギリシアの碑文文化とエジプトの碑文文化の接触によって起こった産物であり、この時期のダイナミックな文化変容は、この碑文を刻ませた在地エリートのハコリスとその一族を取り巻く社会環境を特徴付けるものであったであろう、と推測しています。(p.250)
第13章「ロゼッタ・ストーン再考」では、エジプト人神官団とプトレマイオス王朝との相互産物である神官団決議、ロゼッタ・ストーンを中心に、同じ史料類型に属する他のテクストが比較検討されています。
著者は、神官団決議の史料的限界を指摘し、両者の基本的な協力関係の持続を認めた上で、この史料を同時代の時代状況に最定位することによって、前三世紀後半から前二世紀前半にかけての王権と神官団との力関係のバランスの変化、すなわち王権の優位性から神官団の自立性の高まりへの変化を論じています。
第Ⅴ部「東地中海とナイル世界」
第Ⅴ部では、エジプト在地社会の文化変容に関する諸現象が、地中海世界の国際情勢と緊密に結びついていたことが論じられています。
第14章「初期プトレマイオス朝とエーゲ海世界」では、海上帝国としての初期プトレマイオス王朝の対外政策の展開、とりわけエーゲ海のギリシア都市との関係が考察されています。
著者は、プトレマイオス朝と深く関与したアテネのカリアス、クニドスのソストラトス、サモスのカリクラテス、マケドニアのパトロクロスなどの活躍を検討することで、エーゲ海世界に関しては、プトレマイオス王朝の海外領支配は、王朝とギリシア諸都市のエリートとの互恵的な協調関係によって実現されていたこと。すなわち、制度による支配ではなく、人を介した相互交渉こそが、初期ヘレニズム時代の「海上帝国」プトレマイオス朝の繁栄の基盤であったと結論づけています。(p.310)
第15章「地中海の構造変動とナイル世界」では、これまで、しばしばプトレマイオス朝の衰退の原因であり、国内の「支配層であるギリシア系王権」と「被支配層エジプト在地民」とのエスニックな対立の産物と見なされてきた南部大反乱(前206年〜前186年)について、同時代の東地中海情勢の展開に再定位することで、この反乱に新たな解釈を提示しています。
著者は、ここで同時代の地中海世界の国際関係の変遷が、すなわちローマの進出とマケドニア、シリアの情勢の変化が南部大反乱の展開と密接に連動していたと論じています。
第16章「地中海の海上交易とナイル世界」では、著者はアコリス遺跡から出土したロドス産のアンフォラのスタンプの分析により、ロドス産アンフォラは前210年頃から約100年間にわたって搬入され、そのピークは前150年頃と推定し、ヘレニズム時代にナイル中流域の一村落であるこの地域が、アンフォラを介してアレクサンドリア及び東地中海と密接に結びついていたことを明らかにしています。
第17章「東地中海コイネー文化の成立」では、物質文化の均一化に裏付けられた東地中海コイネー文化の成立が論じられています。
著者は、アコリス遺跡出土の飲食用土器、ならびに他の遺跡からの飲食用土器の形態の検討から、東地中海世界の生活文化の画一化を指摘しています。
著者は、エジプト領域部の農村社会の住民が、ロドスを中継点としたエジプトと東地中海地域との国際交易関係、ならびにアレクサンドリアとの都市=農村関係という二重の関係の変化に対応を余儀なくされ、その過程で、急速に東地中海コイネー文化として装いを新たにしたギリシア文明(精神・物質文化において、ナイル世界からの文化的影響を受けた)へ同化していったと結論づけています。(pp.354 -55 )
「終章」では、まず、ヘレニズムという概念の確立と普及に貢献したドロイゼン(オリエントの在地文化に対するギリシア文化の圧倒的な優位性を前提とした上で、ヘレニズム時代をギリシア文化が普遍性を獲得して行く過程と位置づけた)や、それに続く研究者らのプトレマイオス朝のコロニアルな理解、ならびに第二次大戦後、それに代わる新たなメタナラティブ(参照枠)を獲得した分離主義のモデル(プトレマイオス朝の支配下に置いては、ギリシア人はギリシア人の、エジプト人はエジプト人の文化的伝統を保持しつつ併存していて、両者の間の相互交渉を通じた文化変容は最小限にとどまった)、という両説を、以下の二点を挙げて批判しています。
著者は、まず第一に、ナイル世界のヘレニズムを牽引した社会的メカニズムとして、この時代のナイル世界のモビリティの高さを挙げています。
すなわち、ナイル世界と地中海世界とを結ぶアレクサンドリアとギリシア都市との関係、プトレマイオス朝の「海上帝国」としての性格、あるいは、アレクサンドリアとナイル流域在地社会との人や物の移動、さらには地中海世界との連動を指摘しています。
第二に、ナイル世界におけるギリシア系の入植者と在地エジプト人との物質的な近接性、考古学調査による彼らの協同関係を指摘しています。
特に、エジプト人の在地エリートの社会的諸関係、その時々の政治状況への対応を優先して、強化されることのあったアレクサンドリアとの王権との関係が、在地社会のヘレニズムの進展に貢献したと論じています。
最後に、在地社会のヘレニズム現象の諸側面の検討によるギリシアからの影響の強調は、当時のナイル世界の人々がギリシア文明の卓越性を無条件に受容していたことを意味するのではないこと、ごく例外的ではあれ、ギリシア系の出自であったのにもかかわらず、積極的にエジプト文化を受容していった人々もいたこと(エジプト風の石棺の被葬者の例)、を忘れてはならないと付言されています。
(2016.4.25)
手島謙輔 『ギリシア文明とはなにか』
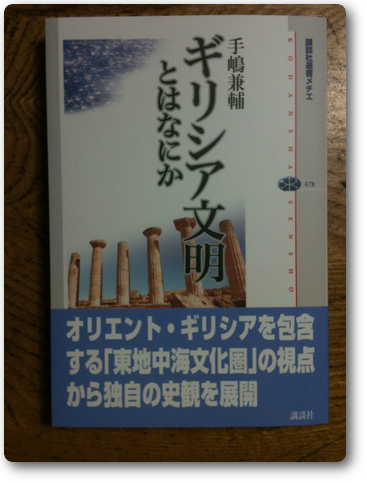
手島謙輔 『ギリシア文明とはなにか』講談社,2010年8月刊,249頁,1600円
本書は、著者によれば、20代後半と30代後半、それぞれ数年ずつをギリシアのアテネで暮らした現地体験が発想の源にあります。
「古代ギリシア」と「現代ギリシア」を繋ぐ糸はどこに隠れ、どこに見いだされるのか。それ以前に、そもそも「古代ギリシア」と「現代ギリシア」には連続性など初めから想定可能なのだろうか。(「おわりに」から。)
本書の主題は、「東地中海」を主な舞台として、古代に展開されたギリシア民族とギリシア文化圏の消長です。
著者は、まず、ともすれば「西」に組み込まれ混同される事が多いが、実際には終始「東」であり続けたギリシア、という点にこだわり、古代におけるギリシア民族の東方先進世界との関係やその位置づけの再検討を行っています。
そして、「ギリシア・ローマ」という呼び名を、より正しくは「ギリシア」と(対)「ローマ」と見なし、その両者を地中海を二分する「東地中海世界(東地中海文化圏)」と「西地中海世界(西地中海文化圏)」と位置づけています。
本書の特色として、古典学者である著者は各章で多くの古典文献を比較引用し、新たな歴史像を描き、特にヘレニズム期に関しては、ギリシア本土やエーゲ海沿岸を中心とする「旧いギリシア」とシリア・エジプトに広がる「新しいギリシア」という二つの文化圏を描いています。
本書の内容はヘレニズム期前後の東地中海を中心としていますが、一方で、中東からヨーロッパにまたがる地域の古代から現代にいたる歴史的展開が視野に入れられています。
本書の構成は、以下の通りです。
はじめに
序章 地中海の古代—ペルシア戦争前—
第一章 ギリシア対エジプト・ペルシア
第二章 アレクサンドロス
第三章 ギリシア対ローマ
終章 生き残る文化圏 —西と東のローマ
おわりに
参考文献
関連年表
(2016.3.31)
伊藤正『ギリシア古代の土地事情』
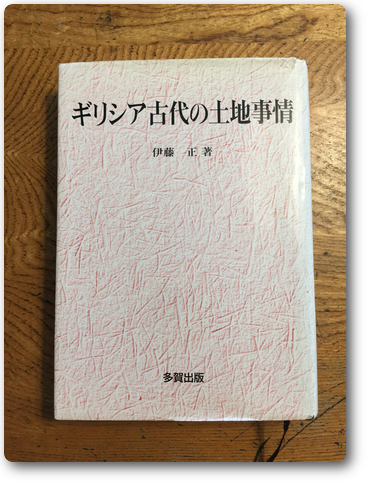
伊藤正『ギリシア古代の土地事情』多賀出版,1999年2月刊,436頁,6,600円
本書は新刊ではありませんが、私の友人の著書で、ここに私の記録を兼ねて、以下、簡単に概要を紹介します。
本書は、1982年から1994年までに公表された論文9編と新たに書き下ろした7編に「はじめに」と「おわりに」を付して成立した論文集です。
本書の構成は、以下のようになっています。
はじめにー研究の視点
序章 κλἢροςに対する共同体的規制について
捕章一 プルタルコス『テミストクレス伝』第18章8節をめぐる諸問題
—土地譲渡可能か否かの観点からー
捕章二 イッサ碑文について
第一部 ソロンと土地
第一章 ソロン、土地、収公
第二章 ソロンの詩篇におけるπολυδένδρεοςの意味
第三章 ソロン及びペイシストラトスの土地政策
捕章三 土地の再分配について
捕章四 二つの書評
—Oliva P.とAnhalt E.K.の近業を中心にー
補章五 ソロンの詩篇の翻訳の試み
第二部 土地と財政
第四章 古典期アテナイの公有地貸借人
—その社会的地位についてー
第五章 ヘカトステー碑文再考
—売却か賃貸借かー
第六章 前四世紀後半アテナイにおける土地と財政
補章六 再びヘカトステー碑文
—Rosivach説についてー
第三部 公有地私的蚕食
第七章 神殿領私的蚕食の実態
—ヘラクレイア碑文の分析を中心としてー
第八章 公有地私的蚕食の実態
—ゼレイアの場合
第九章 アテナイその他のポリスにみられる公有地私的蚕食について
おわりにー結論
あとがき
引用文献
略語表
索引(史料、研究者)
「はじめに」
「はじめに」の冒頭で、本書の目的が次のように述べられています。
「ポリス社会の盛衰の問題を社会経済史的な側面、なかんずく土地制度の観点から明らかにすることである。」
序章 「κλἢροςに対する共同体的規制について」
本章では、ポリス社会の古拙期から前4,3 世紀にまたがる文献及び、碑文資料の吟味からκλἢρος(持分地)の共同体の規制に関して、前6,7世紀と前4世紀初頭の二つの重要なエポックを想定しています。
前者における土地の自由処分に対する共同体的規制の出現は、市民権と土地所有が結びついた市民概念に基づくポリス社会を形成する際の布石となった蓋然性が強いということ。
後者における出現は、市民権と土地所有との結びつきの弛緩を防止すべき意味を持つと解釈されると論じています。
捕章一
補章一において、土地に関しては、ペロポネソス戦争に至るまでは譲渡が可能であったが、実際上土地の譲渡は極めて稀であったこと。土地所有はかなり安定した情況であったことが補足説明されています。
捕章二
補章二において、イッサ碑文についての学説が比較整理され、碑文の解釈、翻訳が試みられています。
第一部 ソロンと土地
第一章 「ソロン、土地、収公—ソロンの詩篇の分析を中心としてー」
著者は古典期アッティカの本質的特徴として、「分割地」と「共有地」との並立的存在が土地所有上の構造であると指摘した上で、その構造がいつ頃、どのようにして成立したのかを問うています。
本章ではこの問題をアッティカに限定して、ソロンの改革との関連で考察しています。
まず著者は、議論の前提条件として(1)ソロンの改革時、すでに広範囲に中小農民は存在していた。(2)土地は譲渡可能であった。という二点を認めた上で議論を進めています。
まず、ヘシオドスの『仕事と日々』などから、中小農民が父祖伝来の農地を主な経営的基礎としつつも、家畜放牧地並びに森林などの共有地を実体的に利用していた生活の実態、並びにソロンの詩篇の吟味から貴族の不正の実体を明らかにしています。
具体的には、ソロンの断片四、並びに断片三六の検討から、ソロンは貴族が共有地を私的に蚕食し、その所有権を明示すべく不正に設けたホロイ(境界票)を撤廃し、共同体の管理下に収公したと論じています。
つまり、ソロンは共有地の私的蚕食—自由な土地獲得—の再発を防止し、大土地所有制への発展の萌芽を摘み取り、国防の主体である中小農の没落の原因を断ち切ったと推定しています。
結論として、ソロンの政策は、当時生じていた共有地問題を是正し、村落の共同体的秩序を回復すると共に、共有地用益秩序の確立に努めようとしたのではないか。
さらに、冒頭に問題とした古典期アッティカの本質的特徴とも言える、「分割地」と「共有地」の並立的存在、という土地制度上の構造を作り出す上での基となったのではないか、と推定しています。
第二章 「ソロンの詩篇におけるπολυδένδρεοςの意味」
本章では、前7世紀のアッテイカ農業における、小農の没落の原因を穀物栽培からオリーブ・ブドウ栽培への転換に帰そうとする「農業革命説」の有効性を検討するために、ソロンの詩編(断片13)に現れるπολυδένδρεοςの意味を問うています。
著者は、まずπολυδένδρεοςの実体として「やぶ、茂み、雑木林」を示すのではなく「果樹」を意味しているとし、この詩編の箇所を間作による農法の描写であると見て、果樹はオリーブないし無花果で間作には小麦ないし大麦が栽培されたと推測しています。
さらに、前4世紀の後半の南イタリアのヘラクレイア碑文ならびに紀元後1世紀のローマのコルメラの『農業論』を史料として、1ヘクタールあたりの麦畑の
土地にオリーブ40本程が間作されていたことを明らかにしています。
結論として、小農の没落の原因として、以下の2点が挙げられています。
(1)前7世紀の間作農法によるオリーブ栽培の発達は、大きな資本を必要としたことから、どちらかと言えば小農に不利に作用した。
(2)貴族は大規模なオリーブ樹栽培のため、資本の投下先としての土地を求め、共有地の私的蚕食を行い、共有地に多くを負うていた小農に大打撃を与える結果となった。
第三章 「ソロンおよびペイシストラトスの土地政策」
本章では、ソロン改革後の無産市民の経済的境遇、それに対するソロン・ペイシストラトスの政策が論じられています。
まずソロンに関しては、プルタルコス『ソロン伝』ならびにガイウスのディゲスタの中のソロンの法とヘラクレイア碑文の比較検討から、彼はオリーブ栽培の促進という路線をポリス共同体の管理下のもとで行ったと推定しています。
著者は、ソロンの農業に関する諸規定の中に、共有地用益秩序の確立の意図を読み取り、このことが後の「共有地」の利用に大きな方向性を与えたと想定しています。
次に、ペイシストラトスの勧農策については、小農・無産市民に対し、ソロンの政策によって収公された共有地を貸与し、前貸金や耕牛、種もみを支給して農業で生活できるようにしたと推定し、さらに、その土地の開墾は果樹化を意味しており、ペイストラトスの指導の下、アッティカの農業開発がオリーブ栽培の促進に向けられたと考えています。
結論として、著者は(1)前7世紀、無主で未墾のエスカティア(辺境の土地)は原則共有地であり、村落共同体の慣行で共同利用された。(2)ソロンの改革前に貴族が共有地の私的蚕食を行い、小農が没落した。(3)ソロンは、貴族の共有地の私的蚕食を阻止し、ポリス共同体の管理下に収公し、共有地の用益秩序の確立に努めた。(4)ペイシストラトスは、ソロンの方向性を維持し、無産市民に共有地を貸与し、財政的援助を行った。と推測しています。
つまり、著者はソロンとペイシストラトスの土地政策に連続性を認め、その政策の中に古典期アッティカの土地制度上の「共有地」賃貸システムの萌芽を見いだしています。
補章三 土地の再分配について —Solon F34 (West)をめぐる諸問題—
ここでは、ソロンの断片34に示されている土地の再分配の問題について、近年のロージバックの解釈—土地の分配を要求したのは富裕な土地持ちのカコイ(劣者:少数の富裕な非貴族)の正当性を、ソロンの詩編に立ち返って吟味・検討しています。
著者は、ソロンの詩編に現れるkakoi,agatoi(esthloi)の用語の検討から、ロージバックのkakoiを「少数者の富裕な非貴族」とみる解釈を否定して、ソロンの断片34をソロンは民衆、とりわけ貧民への土地の再分配を拒否したこと、
ソロンがそれを拒否したのは、土地の再分配は暴力を伴い、法をそこなう支配のしるしであったと彼が見なしていたからと論じています。
補章四 二つの書評 —OlivaとAnhalt E.Kの近業を中心に
ここでは、ソロン研究の概説書であるOlivaの10のテーマごとの内容の紹介とソロンを詩人として位置づけようとしているAnhaltの著書に対して、著者の私見を交えた書評がなされています。
補章五 ソロンの詩篇の翻訳の試み
解題に続いて、現存するソロンの詩篇(断片40)がエレゲイア(ヘクサメトロス「六節」とペンタメトロス「五節」からなる二行連詩:F1〜30)、ヘクサメトロス(F31)、テトラメトロス(トロカイオス「四節」:F32〜34)、トリメトロス(イアンボス「三節」:F36〜40)の順に翻訳されています。
第二部 土地と財政
第四章 古典期アテナイの公有地賃借人 —その社会的地位についてー
本章では、前四世紀アテナイにおける公有地賃借人が、当時のアテナイ社会においてどのような地位の人々であったのか、を問うています。
著者は、ウォールバンクによって公にされた聖財賃貸借碑文、ならびにヘカトステー碑文に現れる人物の吟味によって、公有地の賃貸借人が比較的富裕な人々であったことを明らかにしています。
そして、前四世紀後半の公有地の貸借権の賦与が、特権賦与的性格を備えていたこと、並びに公有地賃貸の目的が、国家の財源確保が第一義の目的であったこと、さらに、賃貸者である富裕者は公有地の賃借人となって、そこに致富の源泉を見いだしたと結論づけています。
著者はそこにポリスを衰退に導く一要因を見いだしています。
第五章 ヘカトステー碑文再考 —売却か賃貸借か
本章では副題にあるように、従来一般に公有地の売却をしるしたと解釈されている史料であるヘカトステー碑文(『ギリシア碑文集成(IG)』第2巻第2版本第1594番—第1603番)を改めて検討して、売却か賃貸借の碑文であるかを再考しています。
著者は先行研究を整理し、ヘカトステー碑文の吟味から、従来の売却碑文の考えを退け、公有地賃貸借に関わる史料と見なしています。
すなわち、ヘカトステー碑文に現れる数字の大部分が12.5で割り切れるという周期性を認め、ヘカトステーが売買価格の百分の一ではなく資産評価の1%で、支払われた額は資産評価額の8%と推定したオズボーン説に依拠して、古典期アテナイの賃貸借における地代が試算評価額のほぼ8%に当たるところから、ヘカトステー碑文は売却を扱ったものではなく、賃貸借を扱ったものと推定しています。
つまり、ヘカトステー碑文は、区などの土地所有団体が賃貸借人から8%の地代を徴収し、そのうちの1%にあたる額(地代の8分の1)を国庫に納入したその記録であると見なし、ヘカトステー碑文には国家の取り分(百分の一)とその算定の基準となる資産評価額が記されていたと考えています。
さらに、著者は国庫収入の増大のために、賃貸借により生ずる地代収入の8分の1(資産総額の百分の一)を国庫に納入させるような方策が講じられ、ヘカトステー碑文は、前4世紀後半のエイスフォラ(臨時税)徴収のための記録ではないかと推定しています。
第六章 前四世紀後半アテナイにおける土地と財政
本章では、国家が国庫増収の目的で公有地の売却や賃貸が本格的に行われるようになるのはいつ頃か。つまり、国家が公有地の売却や賃貸借より生じる収益に本格的に頼るのはいつ頃かを問題にしています。
著者は、ヒエラ・オルガス(アテナイとメガラの国境にある神域)に関して、その土地を賃貸に出すことの提案が、当時の国家財政の指導者エウブーロスによってなされたこと、さらに、前四世紀後半の財政難の時代、国家がすべての神々の聖地を管理下に置き、神殿領を貸し出すことによってポリスの財源確保に役立てようとする共同体の志向がなされたと考えています。
そしてそのことが、前四世紀後半における神殿領を含めた公有地賃貸の急増を結果として引き起こしたと推定しています。
さらに、聖財賃貸に関する碑文史料の吟味から、公有地賃貸が前四世紀後半のアテナイの国家財政にとって、少なくとも歳入面で一定の役割を演じていたと論じています。
補章六 再びヘカトステー碑文 -Rosivach説についてー
本章では、偶然著者と同時期に発表されたヘカトステー碑文についてのロージバック説の紹介と、両者の見解の相違点が述べられています。
ロージバックは、著者と同じくヘカトステー碑文を賃貸借に関わる史料と見なしたものの、碑文に現れる金額は著者の言う物件の資産評価額ではなく、賃貸価格(地代)と推測しています。
著者は、ロージバック説を吟味し、地代と見るには高すぎること、数字の周期性についての説明がなされていないこと、地代に課される1%税なるものが賃貸借関係の碑文及び文献資料に現れていない点などを挙げて、彼の説に疑問を呈し、現在のところ、自らの説が有利であると感じていると述べています。
第四部 公有地私的蚕食
第七章 神殿領私的蚕食の実態 —ヘラクレイア碑文の分析を中心としてー
本章は1732年に南イタリアで発見された二枚のヘラクレイア碑文の分析を通して、この二碑文に記されているディオニソス及びアテナ・ポリアス神殿領が、いつどのような背景と原因によって私人による私的蚕食が生じたのか、さらに収公後貸し出されることになった両神殿領について、その地目、地代、賃貸期間、賃貸者の権利、義務の問題などを検討し、神殿領を再建によってポリス共同体が達成しようとした目的は一体何であったのかを考察しています。
まず、碑文年代に関しては、多くの碑文学者や歴史家の見解に従い、両碑文を前四世紀末乃至前三世紀初めに置き、私的蚕食の実態が述べられています。
著者は、絶え間のない戦争状態において、私人が未耕作の神殿領の一部を横領し耕し、平和の時代が到来したときにポリス共同体が失われた土地の取り戻しと神殿の秩序の回復に乗り出したと推定しています。
そして、平和の一時期をアレクサンドロスの遠征とそれに続く時期と見なしています。
さらに、神殿領の再建と管理に関しては、両神殿領の賃貸契約の取り扱いの相違を二つの地所の異なる状況に起因していることを明らかにし、ディオニソス神殿領のように粗悪で開墾を必要とする領域が永久賃貸として貸し出される傾向が強く、これに対して、アテナ・ポリアス神殿のように耕作に適した地域は短期賃貸(5年)の対象となるケースが一般的であったと推定しています。
最後に、神殿領再建の目的と意義に関しては、本来神殿の金庫と国庫とは別物であると認められていたが、神殿領の真の所有者はポリスそのものであったこと。
国庫と神殿のそれの一本化は「財政頻拍の時代」に端的に表れた現象と考えられ、ポリスは財政窮乏の際に、神殿領から上がる地代収入を国庫収入として確保しなければならず、そのためには神殿領の保全と管理に心がける必要があったこと。つまり、神殿領を外敵や共同体内部の私的蚕食から守らなければならなかった。
さらに、ポリスは財政難の時代に、神殿領を含む公有地などの「目に見える財産」に財源を仰ごうとしたのではないか。そして、これはポリスの下部組織である小共同体にもある程度当てはまることであり、前四世紀後半=財政逼迫時代の一般的傾向ではなかったか、と推定しています。
第八章 公有地私的蚕食の実態 —ゼレイアの場合—
本章では、前章のヘラクレイア碑文と同様、ゼレイア出土の碑文を検討して、公有地の私的蚕食の問題を検討しています。
まず、著者はこの碑文の表面乃至裏面の吟味から、以下の3点を明らかにしています。
1. ゼレイアというポリスは、アレクサンドロス大王の東征に関わる前334/3 年頃の政変で、僭主ニカゴラスを追放し、そのとき亡命した人々の土地を没収して公売に付した。
2. 同じ時期のゼレイでは、没収された土地財産乃至フリュゲイス(隷農フリュギリア人)の土地がポリスに対して功績のあった新市民や外人に贈与された。
3. 僭主政転覆後のわずかの間に他の公有地が私人によって不正に占有された。これに対して、ポリスは公有地を復旧するというのではなく、それを売却するという方法で問題を解決した。
さらに、著者は、スタシス(政変)により生じた没収財産が、ポリスの共有財産とみなされた事は明らかであり、その管理についてキオス碑文を参考にして、ポリスによる没収から売却に至までの管理の一方式を明らかにしています。
最後に、公有地の私的蚕食がおこる一つの状況として、政変などの動乱の時代が想定できること。
そして、公有地の私的蚕食がおこった場合、土地の収公を行うのが常であり、その土地の再建や管理に関しては、ポリス間で相違が見られること。
すなわちヘラクレイアにおいては、土地は収公後貸し出され、ゼレイアにおいては売却されていること。
それは、前者が公有地を維持し、復旧しようとする意識がきわめて弱く、後者はその意識が非常に強いということ、を指摘しています。
第九章 アテナイその他のポリスにみられる公有地私的蚕食について
本章では、前章に続いて、前4世紀後半のアテナイや他のポリスにおいて、公有地の私的蚕食の実態が考察されています。
まず、碑文資料として、以下の11例が列挙されて吟味されています。
前述のヘラクレイア碑文1例、ゼレイア碑文1例、アテナイに関して5例、アテネ以外のポリス4例(ロドス島カミロス1例、カリア地方のテルミッソス1例、カリア地方の旧都ミュラサ2例)が検討されています。
結論として、公有地私的蚕食について、アテナイに言えることは、前4世紀中葉に公有地蚕食の問題が顕在化していたこと、私的蚕食の対象となったのは神殿領と公有地であり、時代的に前4世紀の中頃に比べ前1世紀には私的蚕食の規模が大きくなったことが指摘されています。
次に、アテナイ以外の6つの碑文資料(顕彰碑文)からは、神殿領が私的蚕食の対象になっており、私的蚕食の長期化や規模の拡大は神殿や国家財政に大きな打撃を与えることになり、蚕食されている土地の収公は、歳入の増加、すなわち財政再建の目的で行われたと推定されています。
また、上記の史料全体を通して、収公後の管理方法と収益の用途に関しては、賃貸借か売却、祭祀のための費用に当てられるケースが一般的であったこと。
戦争、スタシス、国境紛争、一大事件、政治的激変などのいわゆる混乱期が、私的蚕食にとって好機であったと推定されています。
さらに、著者は史料に共通して言えることとして、顕彰碑文の顕彰事由として、公有地再建の仕事がその人物の功績として挙げられていることから、このことは、当時公有地の私的蚕食が深刻な社会問題になっていた事を反映しており、この種の顕彰決議はアテナイにとどまらず、時代的にも広範囲に現れるという事実の中に、ヘレニズム期に見られる公有地の私的蚕食の一般化の傾向を認めることができると考えています。
また、公有地の私的蚕食の問題の解決として、公有地の復旧に関わる役人が、時代的に異なる複数のポリスに共通して現れるという事実は、前4世紀後半以降における公有地の私的蚕食の一般的傾向と何らかの相関関係にあるのではないかと推測しています。
最後に、公有地の私的蚕食が公的土地所有に与えた影響については、国家が収公出来ずに終わる場合や、復旧に成功しても財産が売却されれば、結果的には公有地の減少を余儀なくされ、ヘレニズム期に見られる公有地の私的蚕食の一般化傾向は公有地の本来の姿を変貌させる上で、一定の役割を演じたと言うことができると結論づけています。
おわりに —結論
最初に、「共有地」の変貌について、全体的な見通しが述べられています。
まず、ホメーロスの社会において、土地の共有制や定期的割替制といったものは確認されないこと。
ホメーロスの詩篇における共有地とは無主のまま放置されている森林や荒蕪地並びに放牧地で、これらの土地はエスカティアと呼ばれ、共同体成員は平等にその用益権を享受し得、平等に無主物先占権occupatioを有しており、「私的」に占有し得た。
このような共有地利用のあり方は、ヘシオドスの世界においても、またソロン以前のアテナイにおいても原則的には同様であった。
共有地の不平等利用を促すoccupatioに制限を設けようとする動きは、恐らく前7,6世紀に現れた。
アテナイにおけるソロンによるホロイ引き抜きも私有化されていた共有地を元に戻す役割を果たし、ソロンの土地最高限度を定めた法も、occupatioに制限を設ける意味を持った。
このようにして、ギリシア諸ポリスは、ポリス成立期の早い時期にoccupatioに制限を設けることに成功し、平等な共有地用益権を確立することで、ローマのような大土地所有制の発展の道を封じることができた。
さらに、前5世紀の中葉以降、共有地の賃貸借が確認され、所有団体に関しては、前5世紀にはポリス、部族、区が現れるのに対し、前4世紀にはポリス、部族、トリッテュス、区、並びにゲノス、オルゲオネス、フラトリアなどを確認することが出来る。
また、共有地の利用形態は、アルカイック期において「共有地」は既存の村落共同体の慣行に基づいて共同利用されていた。
特にエスカティアは共有放牧地として無償で共同利用された。
前5世紀中葉、このような土地の一部がポリス、部族、区によって「畠地(コーリオン)や園地(ケーポス)」として貸し出されるようになり、前4世紀になるとこの土地の多くの部分が、「畠地や園地」として賃貸耕作されたばかりではなく、従来共同利用されていた放牧地もしだいに地代を取って貸し出されるようになり、純然たる共同利用の形態は排される方向に向かった。
次に、著者は「共有地」の変貌に決定的役割を演ずる「共有地」の売却について、ランバートのヘカトステー碑文を売却契約に関する碑文と見なす近業を紹介・批判しながら、次のように彼の説を退けています。
ヘカトステー碑文を賃貸借に関わる史料とみなしている著者(自分)にとって、ランバートの結論は次のように良い改めることが出来ると思う。「在来小共同体の構成員は共有地を平等に利用する権利を有していた。前4世紀後半に小共同体は共同利用されていた森林、放牧地などの共有地をその構成員に使用料(地代あるいは税)をとって利用させること(貸し出すこと)にした」と(p.399)
そして、このような共有地利用形態の変化が起きた状況を、前章で考察したように共有地の私的蚕食の事実に対応するという一面があったのではないかと、さらに、共有地の私的蚕食の事実が、結果として、共有地売却や賃貸借のきっかけを創り出したのではないかと推測しています。
最後に、「共有地」と「公有地」の二つの言葉の使い分けについて説明がなされています。
著者は「共有地」を、その土地を実体として、入会地的性格の地代ないし使用料を必要としない共同体全員に開放されている共同(利用)地として理解し、「公有地」を、その土地を実体として、ポリスやその下部組織である小共同体が賃貸契約に基づいて地代ないし使用料をとって貸し出している土地と理解しています。
従って、実体として同一の公地が、利用形態の相違によって、共有地として存在する場合と、公有地として存在する場合があり、時には共有地から公有地へ、あるいは逆に変化する場合もあり得たと見なしています。
そして、この公地における二つのカテゴリーは、その割合は、時代が下がるに従って共有地から公有地へと移っていたと推定しています。
そして、ポリスの衰退の問題について、土地所有所上の観点からは、以下の二つの段階を想定しています。
まず、第一段階は公地の「共有地」から「公有地」への変化であり、第二段階は、「公有地」から「私有地」への変化であると。
著者は、アテナイにおいて、以下のように結論づけています。
「それはまず、共有地私的蚕食をきっかけにして、前4世紀後半に公有地賃貸借の大規模な実施(共有地から公有地への変化を意味する)という形をとっておこり、それは次に前3世紀初頭に公有地売却の一般化(公有地から私有地への変化を意味する)という形をとって進展したと思われる。」
「そして、それがポリスの衰退の一因となったことは、まず間違いのないところであろう。」(p.401)と結んでいます。
(2016.3.30)
澤田典子著『アテネ民主政ー命をかけた八人の政治家』
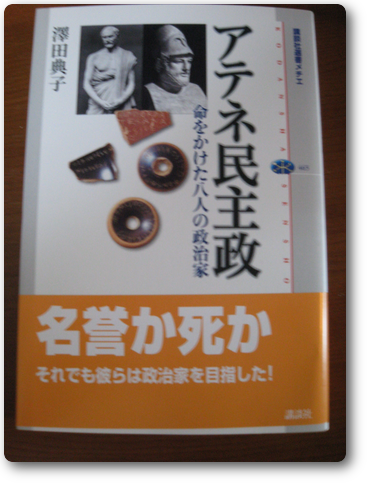
澤田典子著『アテネ民主政ー命をかけた八人の政治家』講談社 2010年4月刊 278頁 1700円
本書はアテネ民主政の草創から終焉までの180年の歴史を、八人の政治家に焦点を当てて民主政の歩みを描いています。
本書の目的は、直接民主政のもとにあって、その時々に市民達に必要とされて頭角を現したリーダーを追うことによって、民主政の姿を浮かび上がらせることにあり、
彼らの生の軌跡から見えてくるアテネ民主政とは何かを問うています。
さらに、民主政を「人」から見ることによって、何が言えるのかを考察しています。
本書の構成は、以下の通りです。
はじめに
序章—アテネ民主政という世界
名門貴族の時代
第1章 僭主の香りする勇士 ミルティアデス
第2章 一匹狼の策士 テミストクレス
第3章 貴族のなかの貴族 キモン
弁論術の時代
第4章 最後のカリスマ指導者 ペリクレス
第5章 典型的なデマゴーグ クレオン
英雄不在の時代
第6章 民主政復興の英雄 トラシュブロス
第7章 したたかな名将 イフィクラテス
マケドニアの時代
第8章 反マケドニアの闘士 デモステネス
終章
主な参考文献
図版出典一覧
あとがき
関連年表
人名索引
吉田伸之・伊藤毅編『権力とヘゲモニー —伝統都市2』
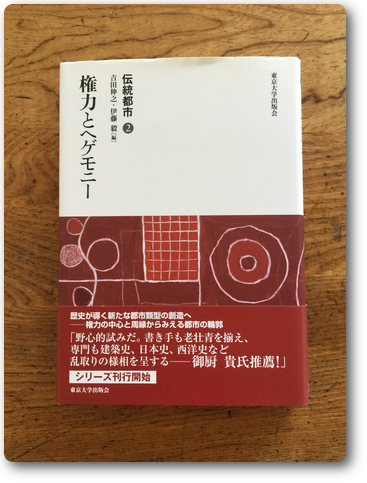
吉田伸之・伊藤毅編『権力とヘゲモニー —伝統都市2』東京大学出版会、2010年5月刊、292頁、4800円
本書のテーマは、伝統都市における権力や社会的権力(=ヘゲモニー主体)の具体的な様相を取り上げて、都市権力論をめぐる方法や論点を、比較類型論的に把握することにあります。
本書の構成は、第Ⅰ部「ひろげる」に三つの総論、第Ⅱ部「考える」には五つの各論、さらに第Ⅲ部「さぐる」では四つの萌芽的研究からなっています。
目次は、以下の通りです。
序 都市の権力とヘゲモニー …… 吉田伸之
Ⅰ ひろげる
1 武士と都市 …… 五味文彦
2 都市法 …… 塚田孝
3 革命前夜のベルリン …… 山根徹也
Ⅱ 考える
1 アテナイ民主政の警察機能と市民 …… 橋場弦
2 君主制フィレンツェの都市構造 …… 野口昌夫
3 都市周辺の権力 …… 高橋慎一朗
4 解体される権力 …… 横山百合子
5 近代中国の租界 …… 吉澤誠一郎
Ⅲ さぐる
1 バグダードー宗教街区騒乱と二重権力 …… 清水和裕
2 ペテルブルクー宮廷の絢爛と都市や会の喧噪 …… 青島陽子
3 長岡と蔵王—近世後期の地域間ネットワーク …… 式部愛子
4 軍都金沢—権力による都市空間の再編 …… 本康宏史
橋場弦「アテナイ民主政の警察機能と市民」
ここでは上記の一論文を簡単に紹介します。
論文は、「はじめに」、第一章「一般市民による警察機能」、第二章「「居合わせた人々」の役割」、「おわりに」という構成からなっています。
著者は、「はじめに」で、アテナイ民主政の特徴として、権力が特定の個人ないし機関に永続的に集中することがなく、つねに分散ないし細分化して存在していること、つまり「権力の偏在」を挙げています。
そして、なぜアテナイにおいて官僚組織や警察のような権力機関が存在しなかったにもかかわらず、無政府状態にならずに社会秩序が維持できたのかと問うています。
つまり、著者の主たる関心は、どのようにして一般市民が警察組織などの強制権力なしに、公的な事件や私的紛争の解決に関与していったのか、ということであり、著者によればその問はとりもなおさず、かれらがどれほど自律的・能動的にポリスとの公共圏と関わっていたかの問題意識と重なると述べています。
まず、第一章では、「官僚制の不在」、「警察権力の不在」がアリストテレス『アテナイ人の国政』などを史料として論じられています。
例えば、現在の警官に近いスキタイ人の弓兵(国有奴隷)なども、常に評議会や役人などの指示を待って行動する受動的役割しか果たさず、犯罪防止や犯人の捜査、逮捕あるいは訴追に重要な役割はほとんど果たして折らず、決して独立した権力の主体になり得ないことが述べられています。
また、現在の公安事件にあたるような「非常時の警察機能」に関しては、前415年の夏起こった石柱像破壊・秘儀冒瀆事件(Thuc.6.27)を例にとり、強制力を発動した国家機関は評議会であったが、その評議会でさえも、武装して自発的に集まった一般市民の治安維持機能に依存していたと論じています。
さらに、犯人の捜査、逮捕、判決の執行などの「平時の警察機能」に関しては、V.J.ハンター、M.H.ハンセンの研究に依拠して、私的イニシアティヴによる紛争解決の諸相を整理しています。
結論としては、アテナイにおいては基本的に警察機能を担っていたのは、非常時であれ平時であれ、ほかならぬ一般市民の自発的行為であったと論じています。
次に、第二章の「居合わせた人々」の役割では、いわば善意の第三者としての立場にある市民たちが重要な役割を果たしていたと指摘しています。
ここでは、法廷弁論に現れる「居合わせた人々」、「通りすがりの人々」などと呼ばれる利害当事者でない市民たちが、紛争解決に積極的にコミットしているいくつかの事例が紹介されています。
そして著者は「ソロンの民衆訴追主義」に言及して、近年のアテナイ法の「当事者主義的傾向」を強調する意見には同調せず、ここでの「居合わせた人々」の行動を分析する限り、彼らはポリス市民としての立場から他人の紛争解決に説教的に参加していたと思われ、彼らの公共心を過小評価すべきではないと述べています
「おわりに」では、著者は今までのアテナイ民主政における警察機能と紛争解決の諸相についてまとめています。
簡単に要約・引用すると、「アテナイ民主政は、警察機能・官僚制を有してはおらず、国有奴隷からなる警察は脆弱で、権力主体としての独立性を持っていない。非常時には、五百人評議会が公安警察としてのイニシアティヴを執ることがあったものの、日常的な秩序維持に関しては、能動的役割を果たすのはつねに一般市民であった。紛争解決に際して重要な役割を果たすのは、利害当事者としての私的イニシアティヴを執る市民たちであったが、「居合わせた人々」がポリスとしての公的な立場から参加したことも見逃すことはできない。」(pp.120-21)
最後に、著者は大まかな見通しとして「市民個人の私的利害の総和を超えた、それとは別の原理で働く何らかの公共圏の存在を、市民たちが日常的に強く自覚していたからこそ、アテナイ民主政における社会秩序が官僚制・警察権力なしに維持されていた」と結んでいます。(p.121)
(2016.3.30)
佐藤 昇『民主政アテナイの賄賂言説』

佐藤 昇著『民主政アテナイの賄賂言説』(山川歴史モノグラフ 17)山川出版社 2008年10月刊 256頁 5000円
本書は、古典期のアテナイ民主政の賄賂をめぐる「言説」(賄賂言説)を分析することによって、賄賂を贈るに値する「権力者」とは誰か、そして彼らを権力者たらしめる政治構造、政治文化とは何であったのかを考察した労作です。(橋場p.93)
本書は、課程博士論文をもとにしたもので、構成は以下の通りです。
はじめに
序章 賄賂への目差しー問題の所在と学説史
1 賄賂の普遍性と多様性
2 学説史と考察の視角
第一章 公職者と賄賂
1 五世紀後半の当番評議員
2 四世紀の法と知識人
3 弁論史料の中の公職者収賄
4 称えられる「賄賂に手を染めない」公職者
5 公職者の位置づけ
第二章 国内政治家を結ぶ賄賂 —パトロネジ関係をめぐって
1 パトロネジ関係をめぐる研究動向
2 公的手当とエラノス –ミレット説の検討
3 パトロネジ関係の具体例
4 パトロネジの政治的機能
補論 贈賄と貧富
第三章 賄賂言説とアテナイの対外交渉
1 賄賂言説と国際関係
2 使節の権限、影響力
3 外交交渉と私的接触
終章 賄賂言説と政治・社会
付表 賄賂言説事例一覧
あとがき
索引
参考文献
注
はじめに
「はじめに」で、全体の議論の方針が表明されています。
まず、前5、4世紀の民主政アテナイにおいて、社会的「権力」について、賄賂という現象を手がかりに考察を進めていき、賄賂の分析から当時のアテナイ市民が目のあたりにしていた「民主政」の実相を照らし出すこと。
さらに、制度的側面のみならず、社会的状況や文化的側面にも目を向け、同時に、同時代のアテナイ市民の価値観の有様にも光を当てていくことが述べられています。
次に「序章」において、著者はヘシオドスの『仕事と日』と伝クセノフォン『アテナイ人の国政』の二つの賄賂をめぐる史料に関して、その背景を既観し、ある特定の時代、社会においてなされた賄賂に関わる言説(本書では、これを「賄賂言説」と呼びます)は、時代、社会ごとに異なる権力の在り方、権力に対する見方を映し出していると指摘した上で、四世紀アテナイ民主政を経験した一般の市民たちが、いかなる権力観を共有していたのか。
そうした権力観が生み出される背景にはいかなる政治的、社会的、文化的状況があったのか。
以上の点について考察を行うことで、アテナイ民主政を実相において捉えようとする試みであると、問題の所在を明らかにしています。
そして、著者は先行する学説史を整理紹介し、史料中の賄賂非難の言説について、
「たとえ根拠のない中傷であれ、収賄を指摘されるとすれば、その人物は、司法や行政などの分野で、何らかの特別の影響力、権力を行使することが可能な存在」として一般市民に認識されていた事になると述べ、「賄賂の真偽や多寡よりもむしろ、こうした、アテナイ市民の「権力観」を探っていくことにしたい」という見通しを立てています。(橋場、p.94)
そしてさらに、前四世紀のアテナイ民主政において、「賄賂言説が頻出するならば、そこには具体的に、いかなる文化的背景、社会的状況があったのだろうか」と問うています。(同上)
最後に、本書で扱う史料として、五世紀末から四世紀にかけての弁論史料を用い、一つは公的な活動に関しての贈賄に関する言説(贈賄言説)、そしてもう一つは収賄に関する言説(収賄言説)を扱う事とすると述べられています。
以下、各章を簡単ではありますが、概観してみます。
第一章 公職者と賄賂
本章では、五世紀後半から四世紀にかけて、アテナイで一般公職者(使節や将軍以外)に対していかなる賄賂言説が向けられていたのかを、その傾向と背後にある歴史的状況に考察が試みられています。
著者は、まず、第1節において五世紀後半の当番評議員(プリュタネイス)に収賄言説が集中していることに着目します。
その権限として、民会及び評議会の審議内容の事前選択、票決に付す権限は、民衆によりポリスの政治に決定的な影響を及ぼすものと見なされていたと論じます。
そして、四世紀初めの新しく議長職を務めることになった幹事役(プロエドロイ)の設置は、当番評議員の事実上の権限の大きさを意識し、買収などの外的影響力排除の目的で(一面では負担の分散で)なされたと推測しています。
そして、第2節では四世紀アテナイの公職者収賄に対する、法的措置と知識人の態度を考察し、公職者一般が収賄を強く懸念されていたことを明らかにしています。
しかし、著者は次節で、四世紀を通じて、弁論史料中に確認できる公職者の収賄言説が、政治家に対するものと比較して明らかに少ないこと、また強い非難の事例が少ないことを考えれば、一般市民にとっては、一般公職者が彼ら以上に大きな「権力」を行使するものとは認識していなかったと論じています。
つまり、多くの弁論史料が示唆しているように、アテナイ市民にとっては、一般公職者は自分たちと同質の存在であり、共感の対象であったこと。
そして、こうした態度が、一般公職者を権力者と見なさない事に繋がったこと。
さらに、一般公職者の収賄が、大きな問題とならなかったのも、こうした公職観が反映した結果だと結論づけています。
最後に、著者は、「公職者一般に対する賄賂言説の少なさ、弱さは。四世紀のアテナイにおいて、公職に幅広い社会層が参加していたこと、民主政の行政機関に広範な層の市民が参与していた、当時の社会状況の反映でもあったと言えるのではないか」と本章を結んでいます。
第二章 国内政治家を結ぶ賄賂ーパトロネジ関係をめぐって
本章では、同胞市民から渡されたとされる賄賂言説に注目し、五世紀末から四世紀のアテナイにおける政治活動について、市民同士によるパトロネジ関係という概念を利用して、民主政下におけるその機能、意義について考察が加えられています。
まず、最初にパトロネジ関係について次のように説明されています。
「パトロネジ関係とは、人間関係の一形態を指す。その要件を記せば、(1)私的な関係であること(すなわち、基本的には、公的、制度的な関係ではない。)(2) 両者の間に対等ではない関係(本書ではこれを非対称的関係と呼ぶ)が成立していること、(3)その関係が制度や暴力、債務債権等の外的な強制力によらずに結ばれていること、その代わり、(4)当事者間には、関係を形成、あるいは維持するにあたり、物品や奉仕を媒介とした互酬的な交換が成立していること、以上の点が挙げられる。」(pp.78-9)
第1節では、こうしたパトロネジ関係に関して、フィンリー以降の研究動向が述べられています。
さらに、第2節では民主政アテナイには、公的手当やエラノスと呼ばれる無利子融資が存在し、富の再分配機能を担い、それ故こうした諸制度がパトロネジ関係のような私的関係を抑制する機能を果たしていたというミレット説を検討しています。
著者は、結論として、エラノスは、身体の危機や身請けと言った特殊な状況においてなされており、一般市民に対する日常的な相互扶助の的経済支援とは考えが難く、エラノスがパトロネジ関係のような経済的利益を仲立ちとした関係の形成を抑制していたというミレット説に異議を唱えています。
続く第3節では、以下のパトロネジ関係の具体例が挙げられています。
「クレオンとその周辺」「アルケデモス」「ティモクラテス」「ステファノス」「アイスキネス」「軍事指導者達」「『雇われる』人々」など。
著者はこうした弁論史料の分析を通して、経済的恩恵の返報として、利益供与者の意向に従い、動議や告発などの政治活動に従事する者が日常的に見られることを明らかにしています。
そして、五世紀末から四世紀のアテナイにおいて、パトロネジ関係の形成、およびその政治的利用が、日常的にあり得るものだった蓋然性は高いと結論づけています。
第4節はパトロネジ関係の政治機能が考察されています。
まず最初に、古典期アテナイ社会におけるパトロネジ関係は、経済格差、情報格差により恒常的には政治活動に参加が難しかった中下層の市民に対して、政治活動に参加するための、有効な機会を提供する機能を果たしていたと論じた上で、次にパトロネジ関係の上位者はこの関係をいかなる目的で利用したのかを問うています。
著者は、
第一に、有力者たちの狙いは、政策の円滑な遂行であったこと。
第二に、代理告発および代理提案という政治戦略。
第三に、応援演説などによる補助的な政治協力。
第四に、顕彰決議の提案を挙げています。
こうした点から、パトロネジ関係は、五世紀末から四世紀にかけて、民主政下のアテナイにおいて、有効な政治戦略として政治指導者に利用されていたと推察しています。
ただし、著者はパトロネジ関係の政治利用が、民会あるいは陪審廷での投票行動を直接に拘束し、左右するものとならず、パトロネジ関係が支配階層を形成するような大規模な政治改番にはならなかったこと、こうした側面は軽視されるべきではないと注意を促しています。
つまり、パトロネジ関係がアテナイ政治に対して有した意義を、不当に高く評価することを慎むべきと。
その上で、著者はフィンリーの「指導者達の抗争対立(アゴン)を経た上で政策を決定することこそが、実際にアテナイのデモクラティアという政治システムを構成し、活性化させていた。」を引用し、「政治家達によってアゴン的な論争が繰り広げられ、その議論を通じて市民団は説得され、票決をなす。こうした手続きを経て政策決定がなされる、五世紀から四世紀にかけてのアテナイ民主政において、パトロネジ関係の政治利用は、アゴン的な民主政システムの維持、活性化の役割を、あるいは少なくともその役割の一部を担っていたと考えられるだろう。」(p.117)と結んでいます。
本章には、「贈賄と貧富」と題された補論が添えられています。
ここでは、「富裕者の贈賄が、一般市民の懸念や非難の対象となっていたことは間違いないが、残存史料からは一般富裕者が贈賄により、政治決定に陰から影響力を及ぼすことは、糾弾の対象とはなっていないことを挙げ、一般富裕市民による政策決定課程への影響力行使に対して、市民団はあまり強い警戒の目を向けることはなかった」、と論じています。
つまり、「政治家とは見なしがたい一般の富裕者達が、私財を利用して政治家達に働きかけ、外側からポリスの意志決定過程に影響力を行使すること自体は、一般の市民にとって、ある程度受け入れられる事態と見なされており、強い疑念を間断なく向けられてはいなかった」と推察しています。
(本章は、佐藤昇「民主政アテナイにおけるパトロネジ」『史学雑誌』110−7:1−34を加筆修正したものです。)
第三章 賄賂言説とアテナイの対外交渉
本章では、外交交渉に関わる政治家と収賄言説との関係に関して考察が加えられています。
第一節では、賄賂言説と国際関係と題して、史料中に目の引くペルシア王及びマケドニア王からアテナイ人政治家にもたらされた賄賂の事例について分析がなされています。
著者は、この両国関連の賄賂言説が多く見られる理由として、アテナイ市民一般および政治家達の国際情勢認識の在り方が、ある程度反映していると考えられると述べています。
つまり、四世紀のギリシア、エーゲ海情勢の中で、マケドニアおよびペルシア両国の存在は、アテナイにとって外交上、きわめて大きな地位を占めていたこと。
そのため、その他の諸勢力との関係以上に両国との外交関係に目が向けられ、注意が払われるようになり、その結果、両君主国からの賄賂言説が弁論史料中に高い頻度で現れることになったと推測しています。
すなわち、賄賂言説の頻度、傾向は、アテナイの置かれた国際的な関係に対応していること。
そして、その時々の国際情勢の認識と外交に関わる賄賂言説との間には、密接な関係が認められると論じています。
第2節では使節の賄賂言説について、考察がなされています。
特に、使節の賄賂が一般アテネ市民に強く懸念され、厳しく非難された理由について、使節が制度上備えていた権限や政策決定に及ぼす影響力といった側面から考察がなされています。
著者は史料から使節の任についた者達が、制度的には再任され、政治的発言の重要性という観点からも、他の一般公職とは異なる大きな権限、影響力を有していたと推測しています。
そして、こうした権限、影響力が他の国の指導者にとって十二分に贈賄に値するものであり、一般市民にとってそうした事態を懸念するに十分であり、そのためにこそ、一般の公職者達には向けられていない、激しい収賄非難が、使節たちに向けられることになったと論じています。
第3節では、外交交渉と私的接触と題して、まず贈与を伴う使節歓待の在り方やプロクセニア制度が考察されています。
そして、一応の結論として、4世紀のアテナイでは、外交交渉に関わる収賄言説が頻繁に確認されるのは、外国人歓待という場のみに還元されるべきではなく、共同体の枠組みを超えた政治家同士による、非公式の私的な直接交渉が活発に行われていたことの表れであったと論じています。
すなわち、4世紀のアテナイでは、一方では民主政システムが発達し、使節や政治家による意見陳述、公開討論に大きく依存しつつ、他方では政治家間の私的紐帯を通じた私的空間での外交交渉という、古代ギリシア世界の伝統的な外交交渉文化の中に組み込まれていたこと。
こうした政治構造、政治文化が背後にあったが故に、外交に関わる政治家達は、必然的に自ら直接、外国勢力と私的に接触せざるを得ず、その結果、同胞市民に収賄懸念を持たれることが不可避の状態であった。
換言すれば、外交関連の賄賂言説の頻出は、ギリシア世界に浸透していた伝統的外交文化と、アテナイに誕生した民主政との矛盾をはらんだ共生関係の表れと見なすべきではないかと論じています。
最後に、著者は4世紀のアテナイの対外交渉の中心は、新興の富裕層か、中下層の出身者によって担われており、こうしたアテナイ政治家と各国の君主や要人との関係は、同胞市民の目には、不均衡な状態と映り、疑念や反感を招き、蓄財目的を疑われたこと。
外交関係における多くの収賄言説において、アテナイ政治家達が「雇われ者」「追従者」として非難されるのも、彼らと贈賄側との非対称的な関係を、市民が感じていたことの表れであり、ギリシア世界に私的紐帯に基づく伝統的な外交交渉文化が存続していた一方、民主政アテネではそうした交渉を担う層が確実に変質していたこと。
すなわち、外交に関わる収賄言説の頻出と、その描写の在り方は、こうした社会的な流動性の表れとして理解することも可能ではないかと結論づけています。
終章 賄賂言説と政治・社会
本章では、これまでの各章の論点が確認され、最後に各内容を相互に関連づけて結びとなっています。
第一章での公職者の収賄言説についての分析では、一般公職者の収賄が、ある程度許容、黙認されていたこと。
それは、彼らが「権力者」として認識されずに、一般市民とアイデンティティを共有するような存在であったこと。
すなわち、公職者収賄の言説の少なさ、非難の弱さは、行政機構への市民参加が広範な社会層まで及んでいたという当時の政治状況の表れとも考えられること。
第二章でのアテナイ国内での政治活動に関する収賄言説では、パトロネジ関係が取り上げられ、非対象的な市民間の私的関係が、つまりパロネジ関係を利用した政治文化が、当時のアテナイ政治において、十分に機能していたこと。
第三章の外交交渉に関する収賄言説の分析では、まず、外交に関わる収賄非難には国際的な政治状況が影響を及ぼしていたこと。
次に、使節に関しては、自主裁量権を有し、ポリスの政策決定権にも大きな影響力を有し、一般の市民から「権力者」と見なされ、収賄を危惧されたこと。
プロクセニア関係など私的紐帯を結んでいたこと、そして、かれらが伝統的な家柄の出身者ではなく新興の富裕層の市民が中心を担っていたが故、アテネの政治家と海外の要人との私的紐帯は、アテネ市民の目には、上下関係、従属関係と理解され、しばしば「雇われ政治家」と非難されるようになったこと。
そして、4世紀のアテナイでは、一般公職者とは対照的に、国内の政治活動に従事する「政治家」たちが収賄を贈られる相手として懸念されました。
著者は、最後に本書を以下の文章で閉じています。
「市民団が最終決定権を握るアテネ民主政は、その決定に重大な影響を及ぼす政治家の意見陳述に二念なき誠実性を求めていた。
その一方で、政治家達が国内外に私的紐帯を有し、接触し交渉する文化が存在していた。
賄賂非難が頻出していた背景にはこうした理念と文化の共存が確認できる。
また賄賂言説には政治の世界に新たな社会層が参与しているダイナミズムが反映していた。
賄賂言説は、こうした民主政アテネの政治的、社会的状況を映し出していたと考えられる。」
(なお、本書に関しては、橋場 弦氏が『史学雑誌』第120篇第9号(2011年)p.93〜p.99(「書評」)において詳細な紹介と批評を行っています.)
橋場 弦『賄賂とアテナイ民主政—美徳から犯罪へ』
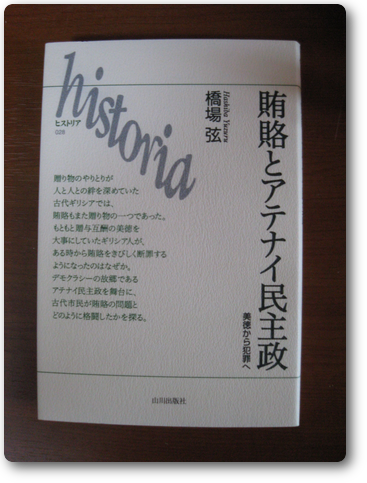
橋場 弦著『賄賂とアテナイ民主政—美徳から犯罪へ』山川出版社、(「ヒストリア」28号)2008年11月刊 189頁 1500円
本書は、山川出版社の「ヒストリア」シリーズの第28号として、書き下ろされたものです。
本書の構成は、以下の通りです。
「目次」
1 賄賂と贈与
2 贈り物は神々をも説得する
3 ペルシア戦争という転機
4 さまざまな賄賂
5 罪と法
6 賄賂と民主政
あとがき
参考文献
図版出典一覧
1賄賂と贈与
最初に、本書の目的が述べられています。
贈与と賄賂の問題をめぐって、古代ギリシア人がどのような価値規範を育て、それに対処していったか、その問題がポリス民主政という仕組みとの関わりのなかで、どのような意味を持っていたのかを探求することにあると。
舞台は前5世紀から前4世紀のアテナイ民主政(前508年〜前322年)。
本書での探究を通して、古代ギリシ市民と我々の価値観のどこが共通し、どこが相違するか、自ずと明らかになるであろうと述べられています。
著者は、アテナイ民主政が参政権の平等が徹底した、アマチュアの政治システムであると述べます。
アテナイの政治家は、最高決議機関である民会に登場して動議を提出し、決議として成立させる能動市民、ないしその協力者でした。
立法・行政・司法のあらゆる面から専門家が排除されていて、そこに参加する政治家や役人たちには、公務員のような倫理ははじめから期待されていませんでした。
彼らは、親族友人のしがらみ、伝統や習慣、社会的価値観、現実の生活に根ざす条件に縛られていて、そしてそこに、彼らの行動に賄賂という習慣がまとわりつく土壌があったと指摘されています。
さらに、アテナイ民主政の政治や裁判に関わる史料からは、賄賂を厳しく非難する言説と、ひかえめながら賄賂を容認する態度も見受けられると述べられます。
著者によれば、前近代社会一般に見られるように、古代ギリシア社会では、何かを贈られれば同等のものをもって返礼すべしとする原則が支配的でした。
この原則を互酬性(レシプロティ)の原理と呼びますが、互酬性を規範としていたギリシア人が、賄賂について「悪いけれどもよい」という両価的な態度をとっていたことは、ある意味で当然な帰結であったと述べます。
そのようなダブル・スタンダードを端的に示すのは、賄賂についてのギリシア人の用語法です。
「贈収賄」という犯罪行為を意味するギリシア語として、もっとも一般的な単語は「ドーラ」といいますが、この語はそのままで「贈り物」を意味していました。
ギリシア人にとって、たとえ犯罪行為として非難する場合であっても、賄賂は贈与の一種にほかなりませんでした。
では、賄賂について何を問うかを、最後に著者は問題にします。
まず、賄賂がアテナイで実際にどれだけ広がっていたのかを、古典史料に基づいて客観的に確かめるのは、事実上不可能であるばかりではなく、不毛であること。
さらに、賄賂というものが、当事者であったアテナイ市民にとって、きわめて概念の曖昧な犯罪であったこと。
結局、古代ギリシア人が、どれだけ賄賂に手を染めていたかは解答不能であり、問題は、賄賂に対するアテナイ人もしくはギリシア人一般の価値観や態度が、どのように形成されていったのか、彼らにとって、何が許される贈与で、何が許されない贈与だったのか、ということであろうと述べられています。
そもそもギリシア人は、贈与あるいは賄賂に対して、どのような価値観を生み出していったのか。
そしてもともと美徳であった贈与が、いつから犯罪としての賄賂という烙印を押されるようになったのか。
彼らはどのような経緯を経て、賄賂に対するきびしい社会的態度や価値観を育て、どのような予防措置や制裁手段を用意するようになったのか。
これらの問題を、最近の研究成果をふまえながら、歴史的背景と共に考えてみることにしよう、と本章は結ばれています。
2.贈り物は神々をも説得する
本章では、最初にギリシア人の贈与文化が述べられています。
贈与(ギフト)とは、返礼を期待した財・サービスの給付のことであり、贈り手と受け手との間になんらかの社会的結合関係を生み出すことが特徴であると定義されています。
古代ギリシアにあって、贈与交換の果たす役割は現代と比較にならぬほど重要であり、M.I.フィンリーによれば、アルカイック期ギリシア社会での交換の基本的な方法とは贈与交換であり、それこそが社会を組織化する重要なシステムでした。
こうしたギリシア社会にあって、贈与がその役割を果たすのは、「経済」に限られていたわけではなく、政治・外交・軍事そして宗教も互酬性を重要な原則として営まれており、宗教の中心となる供儀もまた、人間が神々に与える贈与にほかなりませんでした。
神々もまた、受け取った贈り物に対しては何らかの返礼(ご利益)を人間にもたらすことを期待されました。
こうした贈与互酬の慣行に生きていたギリシ人にとって、贈与はそれを取り交わす当事者の間に濃厚な人間関係を成立させ、あるいは補強し更新しました。贈与は人と人とを結びつける重要な要因であり、逆にそれを拒否することは、人間関係の断絶を意味しました。
次に、著者はクセニア(一種の賓客関係)と賄賂の問題についてのハーマン説を論じます。
G.ハーマンによれば、クセニア関係とは、異なる共同体に属する個人と個人の間に財とサービスの交換を契機として成立する結合の一種と定義されています。
異民族をふくめた広い範囲の、社会の上層階級相互の間で取り交わされた社会関係が、クセニア関係でした。
クセニア関係で結ばれる個人の間の相互の歓待と互恵の関係は、基本的には個人間に成立するものですが、一過性のものではなく男系を通じて子孫に世襲されました。
クセニア関係は、本来の血縁・縁戚関係とならんで、国際政治における連合関係を形成する重要な手段の一つでした。
ハーマンは、政治家の賄賂の問題になる構造を、ポリス成立以前から存在していた伝統的な互酬性の価値観と、ポリス共同体の利害を優先する新しい倫理との衝突という点から説明しました。
つまり、彼はクセニアによる友好関係の絆を優先するペルシアやマケドニアの王は、ギリシアの有力者に対しても、慣行として個人的な贈与を行うことがあり、それは、共同体内の平等という新たなイデオロギーを掲げるポリス市民団の立場からは、共同体にとって危険な贈与と見なされるようになり、ここから賄賂という犯罪概念が発生したのだと、説明します。
著者は、こうしたハーマン説に対して、賄賂という概念の発生過程にアウトサイダーという視点を導入した点は魅力的であり、また理論的に明晰であるが、他方で具体的・実証的検証の裏付けがない一つの仮説モデルの域にとどまっており、ギリシア人がポリス世界に住むようになってからも、決して贈与交換のルールに従わなくなったわけではないと、彼の説を批判しています。
そして、次に、著者の関心の賄賂という概念の発生過程を、具体的・歴史的文脈に見いだすために、ギリシア人がいつから賄賂を犯罪と見なすようになり、厳しい社会的態度を育てていったのかを、時代を追って論じていきます。
まず、ホメロスにあっては、犯罪としての賄賂の言葉は一度も登場しません。
ヘシオドスに賄賂を非難する言葉が最初に登場しますが、彼の政道批判は、モノをもらったらしかるべき形で返礼せよという伝統的な互酬性の倫理観が見て取れ、賄賂非難と互酬賛美が、同じ文脈のなかにあらわれていることからも、単純に、贈与を美徳とする伝統的な倫理観に身を浸していました。
また、ソロンは貴族と民衆との間の調停者という立場から、法的強制力で貴族を処罰することはできなく、立法によっては賄賂を断罪できませんでした。
著者は賄賂に対する最古の公的な制裁装置は、むしろ宗教的抑制力に期待した宣誓のようなものではなかったかと考え、ソロンがアルコンの宣誓文中の「役目柄収賄することもせず」という句を採用したと推測しています。
最後に、クレイステネスによって民主政はスタートして、賄賂に対する厳格な態度が醸成される一つの条件を提供したかもしれないが、公的な立場から厳しく制裁を加えるようになるためには、さらにもう一つの段階を経る必要があったと結んでいます。
3.ペルシア戦争という転機
本章では、賄賂に対するギリシア人の態度に転機をもたらしたのは、前5世紀初頭のペルシア戦争であることが述べられています。
アルカイック期の賄賂非難は、贈与互酬の美徳を善とする立場そのものが根拠になっているのが特徴でした。
しかし、ペルシア戦争の戦いに直面し、ある種の賄賂が公共性にとって破壊的な結果をもたらしうることに気づいたとき、ポリス共同体、あるいはギリシア人の連合体という公共の立場から、賄賂をはっきりと断罪しようとする姿勢があらわれるようになったと言います。
ペルシア戦争を境に、賄賂に関するヘロドトスの史料記述に、新たな様相が加わります。
ヘロドトスの史料からは、ペルシア王が賄賂を使うことによって、ギリシア連合軍のなかから寝返りを誘おうとしているという、一種の危惧感の存在を示すものが少なくありません。
すなわち、戦略としての賄賂です。
また、アテナイ市民団が収賄行為に公的制裁を加えた最初の事例として、ヘロドトス『歴史』9巻5章に描かれた、ペルシアからの和議の提案の受け入れを発議した評議員リュキデスの石打の刑が挙げられています。
さらに、弁論家の引用ですが、前470〜460年代の民会決議には、ペルシアからの収賄行為(と思われる)仲介者アルトミオスに「法の保護停止」という苛烈な制裁を科したという史料が残っています。
著者はこうした史料から、賄賂に対するギリシア人の態度が、ペルシア戦争を契機に不寛容な物に変容したという図式が見えて来ると述べます。
さらに、これときわめてよく似た図式が、ギリシア人の異民族(バルバロイ)に対する態度にもあてはまります。
古典期のギリシア人は、言語学的な差異で、ギリシア語を話さない民族のすべてを「バルバロイ」としてひとくくりにとらえていました。
このような集団的他者認識の型を、P.A.カートリッジは、「両極対立」(ポラリティ)という概念で説明します。
さらに、E.ホールは自己(ギリシア人)と他者(異民族)の関係を両極対立的に、しかも優劣の序列をつけて考える異民族間は、ギリシア人が当初から抱いていたものではなく、異民族を見下ろすイデオロギーの変容は、ペルシア戦争で、ギリシア人がペルシア人の侵攻を撃退したことによってもたらされたと主張しています。
著者は、ペルシア戦争を画期として、異民族観と賄賂観の変容が、それぞれ「隣人から他者へ」、そして「美徳から犯罪へ」という、寛容から不寛容への不可逆的な態度への変化を特徴としている点で共通していると指摘します。
そして、この二つの意識変容は無関係ではなく、ペルシア人に代表される異民族が、うさんくさい他者として認識されるに従って、彼らの贈与も危険な、否定的な価値づけを被るようになったと推測しています。
つまり、贈与を美徳としてきた伝統的価値観が、異民族の「他者化」を通して変容を迫られるプロセスを見て取ることができると。
最後に、
実際に、賄賂を表面上非難しながら、裏では社会生活上必要と見なす両価的態度が支配的になると同様に、異民族を表面上は他者として排除しながら、裏ではなお隣人として交流するという態度も存在し続けたこと。
こうしたことから、古典期に入ると、犯罪としての賄賂と他者としての異民族とが、顕在化した表の価値判断を伴ってあらわれる一方で、美徳としての贈与と隣人としての異民族とが、潜在化した裏の価値判断を伴って伏在するようになったこと。
つまり、互いに密接に関わり、一方の価値観が表面に表れると同時に、他方が裏に隠れるところの二重の両価性、二つのダブル・スタンダードが成立したと結ばれています。
4.さまざまな賄賂
本章では、アテナイ人の賄賂認識の拡大と多様化が論じられています。
ペルシア戦争の勝利の後、デロス同盟が結成され、盟主であるアテナイは、同盟金庫をデロス島からアテナイに移すことで帝国主義化していきます。
この国際政治におけるアテナイの帝国化と、国内における民主政の進展は密接不可分の関係にありました。
民主派の指導者ペリクレスは、貴族派の首領キモンの影響力を排除するために、敵国マケドニアからの買収という罪状で告発します。
裁判の詳細は不明ですが、このキモンの収賄事件も、やはりペルシア戦争の収賄事件と同様の系譜上に位置づけられます。
ここではペルシア内通と関連づけられた賄賂類型から一歩進展し、ペルシア以外の敵から買収されてアテナイの対外拡張政策を損なうような将軍の行為が、告発されるようになっています。
ただし、ここでもギリシア世界の外からやってくる賄賂が問題になっている点が注目されます。
また、これとは逆にアテナイが敵国の将軍を買収したとされる場合もありました。
ただし、こうした贈賄行為は非難された痕跡がなく、一般に、収賄が厳しく断罪されたのに対して、贈賄を罰する価値観の登場は遅れるようです。
さらに、ペロポネソス戦争勃発後、ペリクレスの死後にデマゴーグと呼ばれるクレオンのような新しい行動様式の政治家が登場すると、彼らを収賄者と想定する新たなタイプの賄賂認識が生まれてきます。
すなわち、アテナイの政治家が「アテナイ帝国」の支配権を背景に、デロス同盟諸市民から受け取っているとされる賄賂の類型です。
ここでは、収賄者として将軍ではなく政治家が、また贈賄者として敵国ではなくむしろ同盟国の市民が、それぞれ想定されていることが特徴です。
アリストファネスの喜劇からは、前420年代、デロス同盟の支配、特に貢租取り立てをめぐって、アテナイの政治家や役人が同盟市民から賄賂をとっていると疑われ始めたことがうかがい知れます。
また、こうした種類の嫌疑は、評議会の役職者に対しても向けられ始めます。
前426/5年説が有力になっている、いわゆるクレニアスの民会決議には、裁判の開始手続きを怠った当番評議員に、有無を言わさず収賄の罪が着せられ、それに高額の罰金が科されています。
この当番評議員の怠慢行為を、収賄の罪に直結させる姿勢は、「公職者が同盟市民から賄賂を受け取って、貢租納入に関して不正な手心を加えているのではないか。」という市民の警戒心を想定させます。
さらに、前411年の400人の寡頭政権の首領フュリュニコス暗殺に関与したトラシュブロスの市民権授与の決議とエウディコスの追加動議からは、市民権授与に際して、外国人からアテナイ人の政治家に賄賂がわたり、その結果評議会ないしは民会において不正な提案・決議がおこなわれることへの、極度の警戒心がうかがえます。
すなわち、外国人が市民団の有力者に贈賄して市民権授与を不正に働きかけているのではないか、またその働きかけに応じて私腹を肥やす政治家がいるのではないかという、アテナイ市民団側の猜疑心がその背景にあります。
また、買収行為に関しては、前409年のアニュトス裁判が、史実性に疑問が残りますが、陪審員を買収して無罪を勝ち得た例と言われています。
因果関係は別として、この事件前後から、民衆法廷の抽選手続きをより厳格にし、事前買収をほぼ不可能にする制度改革が進行していったこと、また同時に、法廷を買収しようとする物を厳しく処罰する法律が制定されたことは確かなようです。
最後に、著者はペロポネソス戦争は、アテナイに敗北と政治的混乱をもたらしたが、同時に賄賂についての上で述べた様々な認識の展開を生み出したと述べます。
そして、どのようなタイプの賄賂について、犯罪としての認識が成立していったかという問題を、社会規範の変化として考え、ペルシア戦争以後前5世紀までの社会規範の変容を以下のようにまとめています。
(1)最初に、ペルシア戦争中にギリシア連合軍の一員が、ペルシア王から収賄して敵に内通するという認識。
(2)次に、将軍が敵国から収賄して不当に撤退するという認識
(3)政治家がデロス同盟貢租の取り立てや査定をめぐって同盟国から賄賂を受け取っているという認識。
(4)市民権を不正に取得するために外国人が評議会ないし民会に賄賂をばらまいているという認識。
(5)アニュトスのような法廷買収の認識。
こうした認識がそれぞれ成立し、人々はそれらのパターンの賄賂に警戒心をいだくようになり、おそらく、この社会規範の変容が、一連の法制度という形に結晶化していったのだと思われる、と結ばれています。
5.罪と法
本章では、最初にD.M.マクダウェルの贈収賄に関する法制史研究が紹介され、その法制度がどのような歴史的経緯によって成立したかが問われています。
まず、マクダウェルの前四世紀後半の贈収賄罪に対する訴訟手続きと法が以下のように列挙されています。
(1)役人の収賄罪に対しては、「執務審査」(エウテュナイ)という手続きがあり、これによって有罪になった場合の刑罰は、収賄額の10倍の罰金であった。
(2)評議会や民会における動議提案者の収賄罪に対して、「贈収賄に対する公訴」(グラフェー・ドーロン)があり、刑はやはり10倍の罰金。
(3)将軍や動議提案者による国事級の収賄罪に対して、「弾劾裁判」(エイサンゲリア)があり、刑は死刑。
(4)同じく国事級の収賄罪に対する「アレオパゴス評議会による捜査報告」(アポファシス)があり、刑はやはり死刑。
以上の手続きの他に、
(5)贈収賄罪関連の法律として、民衆裁判所関連の買収罪に対する「法廷買収罪関連法」。
(6)全般的にすべての贈収賄行為を犯罪として処罰する「一般贈収賄関連法」の二つの法があった。
ここでは、(1)執務審査、(3)弾劾裁判、(5)法廷買収罪関連法、および、(6)一般贈収賄関連法について、それぞれの概要と成立史が整理して述べられています。
まず、役人の収賄罪に対して、もっとも一般的に用いられたと思われる「執務審査」に関しては、その第一段階は、会計検査で、役人は在任中に支出した公金の使途について、会計報告書を会計検査官(ロギスタイ)に提出し、審査を受けます。
ここで摘発される行為は、公金横領、収賄、および欠損などの過失の三点セットです。
不正行為があった場合は、会計検査委員はその役人を法廷で追訴し、収賄罪で有罪になると、収賄した額の10倍が科され、支払い能力がなければ、市民権が停止されます。
第二段階は、金銭関係以外の不正行為の摘発で、執務審査官(エウテュノイ)という役人が担当しました。
著者は、「執務審査」に関しては、公金横領、収賄、欠損の過失が三点セットとして認識され、その形態が整うのは前403/2年直後と推定しています。
政治家や将軍など、国家の指導者を告発するために用いられた訴訟手続きが「弾劾裁判」です。
通常、民会によって弾劾裁判開始の決議の後に、民衆裁判所ないしは民会自らが審判を担当し、有罪の場合は死刑の判決がくだります。
著者は、弾劾裁判の起源は、クレイステネスの改革時に、民主政防衛の手段として導入されたと推定しています。
また、前5世紀の末になると、弾劾裁判もこれと別種の収賄行為にまでその適用範囲を広げます。
前410年頃作られたと考えられている「弾劾法」の第三条には、評議会や民会での提案者(レートール)による「金で買われた発言」を国事級の犯罪と断定し、弾劾裁判の適用を命じています。
著者は、このことは前420年代以降の新興政治家の台頭につれ、彼らがデロス同盟から賄賂をとっているという認識が市民の間に拡がっていったことと無関係ではないこと。
さらに、シチリア遠征の失敗、400人寡頭制への反省から、評議会や民会での政治指導者の無責任な行為を、法律的にも厳しく罰しようという機運が高まり、このような立法に結実したと推測しています。
「法廷買収関連法」に関しては、前420年代にはすでに訴訟が市民達の日常的な紛争解決の手段となっていたこと。
民衆裁判所での紛争解決が普通になってくると、賄賂が訴訟の場に持ち込まれる可能性も増大していったこと。
こうしたことから、著者は「法廷買収関連法」は前5世紀末頃に制定されたと推定しています。
最後に、デモステネスの第21弁論『メイディアス弾劾』の一節に記された「一般贈収賄関連法」について論じられています。
この法は、あらゆる種類の収賄行為を、贈賄も収賄も共に処罰すべし、と定める厳格さが最大の特徴です。
マクダウェルは、この法の成立を前6世紀と推測し、増収賄に対する一連の法制度の中で最古の立法と位置づけ、その後の諸制度発展の出発点になったと考えました。
著者は、マクダウェル説に反論します。
この法の成立年代に関して、刑罰を定めた後半は前5世紀半ば以前に、犯罪行為を特定した前半は、前5世紀半ば以降に、それぞれ別の時期に成立したと論じます。
そして、この法の原型の成立をペルシア戦争末期、ないし直後と推測し、後に前5世紀末の法改正の際に、その前半のみが改正され、あらゆる贈収賄行為に法の適用範囲が広げられ、その刑罰は公民権停止という温和なものとなったと結論づけています。
つまり、著者はマウダウェルとは逆に、アテナイ人は、各種の賄賂行為に対して、個別に法律や訴訟手続きを制定することで対処してきたが、次第に困難になり、前5世紀末に、この一般収賄関連法を完成することで、あらゆる贈収賄行為を摘発しようとしたと推測しています。
そして、その推測のほうが、ギリシア人の贈与と賄賂に対する両価的な態度とその克服という、かれらの社会規範がたどった苦難の過程をよりよく説明できると結んでいます。
(「あとがき」によりますと、この章はHasiba,Y.,’Athenian bribery reconsidered:some legal aspects’,Proceedings of the Cambridge Philological Society(Cambridge Classical Journal)52,2006,62-80.の論文を核としています。)
6. 賄賂と民主政
本章では、アテナイ人の贈与互酬の原理をふまえて、賄賂とアテナイ民主政との関係を論じています。
著者は冒頭、前4世紀に入ってからも、法廷弁論という形で、さまざまな賄賂非難の言説が生み出され、賄賂事件に対して裁判も数多く起こされたが、賄賂に対するアテナイ人の社会規範と法制度は、前5世紀末までには、その基本的な姿の完成を見たと述べています。
そして、前322年に、民主政に終止符が打たれるまで、アテナイ民主政は安定した体制を維持しており、そこでの賄賂非難のパターンは、前5世紀と同様、非難の対象は将軍や政治家が敵国から賄賂を取って私服を肥やし、ポリスの安全を脅かす行為であったと述べています。
さらに、アテナイ市民の贈収賄に対する意識の変化を追ってみると、そこで問題視されている賄賂が、現代的な汚職の構図とは、かなり異質であった指摘しています。
つまり、官僚組織も巨大な企業も存在しなかったアテナイ民主政では、ポリス全体を揺るがすほどの重大な対内的贈収賄罪は、事件として発生しなかった。
アテナイ民主政で重大視された贈収賄事件とは、何よりもポリスの外からもたらされた賄賂、すなわち対外的贈収賄をめぐるものであったと。
これに対し、唯一、例外的に制裁を受けた対内的贈収賄が、法廷買収罪でした。
この種の賄賂に対しては、アテナイ市民は贈賄側、つまり陪審員に賄賂をわたす同胞市民に対して、厳しい処罰感情を向け、一連の訴訟手続きや法律を制定しました。
贈収賄といった公職者の罪を告発する事が、一般市民に可能になったのも、民衆がエリートの犯罪を裁く事ができる民主政の世の中になってこそであり、賄賂に対するきびしい社会規範や法的訴訟制度の発展は、やはり民主政の完成を前提条件としたものであったと結論づけています。
著者は、次に「賄賂はなぜ悪なのか」という問題を論じています。
著者は、前4世紀末にいたってもなお、賄賂に対する「悪いけれどもよい」という両価的な態度をアテネ人は完全に克服できてはいない点。
彼らの賄賂に対する社会規範は、依然として近代的基準から見れば寛容であり、その両価性は、アテナイの民主政の歴史を通して決して消滅はしなかった点を指摘しています。
これに対して、賄賂がなぜ民主政にとって悪なのかについて、デモステネスの説明を挙げています。
彼は、第21弁論で一般贈収賄関連法案を引用する際に、富裕者が富の力によって正義をゆがめることこそ、賄賂が悪であるゆえんであると述べています。
つまり、贈収賄が富の力によって市民団の意思決定を歪曲することであるならば、それを放置することは、貧富に関わらず全員が均等に政治参加の権利を与えられるという民主政の根本原則を揺るがす事になる。
だからこそ、アテナイ民主政は贈収賄に対して、厳しい態度を決して緩めなかったと結論づけています。
最後に、民主政と互酬性の問題について論じています。
著者は、贈与互酬は、古代ギリシア社会を成り立たせている重要な原理の一つであり、アテナイ民主政もその枠内で動いていること。
賄賂に対して依然寛容な態度が存続したのもその表れで、その一方で、民主政が互酬性の原理をうまく自己のシステムに組み入れることに成功したと指摘しています。
その例として、富裕な市民、非市民の国家に対する有形無形の贈与に対する名誉の顕彰、返報を挙げています。
外国人への市民権授与、富裕市民の公共奉仕(富裕車と国家との間に取り結ばれた贈与互酬関係)への名望家としての地位と名誉。
このように、一方で贈収賄をきびしく摘発・処罰しながら、他方でこのように互酬性原理をシステムに組み込むことによって、アテナイ民主政は贈与文化をうまくコントロールしていたと述べています。
結論として、
「贈与互酬は、つねにギリシア文化の重要な一部であり、大切なのはギリシア人の文化を彼らの文脈の範囲内で理解する事であり、アテナイ民主政を動かしていたのは、啓蒙主義以降の西欧近代に確立されたような政治理論ではなく、古代ギリシア人の心性を深いところで支えていた文化的・社会的な力学であった。
そして、むしろ注目すべきは、賄賂に対して両価的な態度をもっていたにもかかわらず、アテナイ人が収賄の危険性についての意識を育て、非難の言説と処罰の制度を発展させたことである。
民主政が民主政であり続けるためには、賄賂との格闘をやめるわけにはいかず、その格闘の中で育てていった意識と社会規範こそ、民主政の発展史において古代ギリシア人が達成した一つの成果であるといえるだろう。」(pp.178-180)
と結んでいます。
ポール・カートリッジ著『古代ギリシアー11の都市が語る歴史』

ポール・カートリッジ著、橋場弦監修、新井雅代訳『古代ギリシアー11の都市が語る歴史』白水社、2011年8月刊、235頁、2600円
本書は、Paul Cartledge, Ancient Greece: A History in Eleven Cities, Oxford 2009の全訳です。
著者のポール・カートリッジは、1947年生まれ。オクスフォード大学ニュー・コレッジで学位を修得し、1979年よりケンブリッジ大学で教鞭を執り、古典学部長などを歴任した後、現在同大学のA・G・レヴェンティス財団ギリシア文化教授、およびクレア・コレッジ古典学フェローの地位にあります。
本書の構成は以下の通りです。
まえがき
第1章 序論
第1部 先史時代
第2章 クノッソス
第3章 ミュケナイ
第2部 歴史時代初期 前500年までー暗黒時代とアルカイック期
第4章 アルゴス
第5章 ミレトス
第6章 マッサリア
第7章 スパルタ
第3部 古典期 前500年—前330年
第8章 アテナイ
第9章 シュラクサイ
第10章 テバイ
第4部 ヘレニズム時代
第11章 アレクサンドリア
第5部 回顧と展望
第12章 ビュザンティオン
第13章 エピローグ
付録 全ギリシア的な神域、ギリシアの貨幣、距離の単位など
序論では、本書の狙いが述べられています。
古代ギリシア文明史という、複雑で多様性に富むテーマについて、過度に単純化することもなく、平易で高度に刺激的な入門書を提供すること。
また、目次であげた11の都市の歴史を通して、古代ギリシアの政治・交易・旅・奴隷制・ジェンダー・宗教・哲学・歴史学など様々なテーマに光を当てることで、ギリシア世界を理解してもらうことに本書の狙いはあるといいます。
最後に、千を超えるポリスから、11の都市を選んだ理由が述べられています。
本論では、アテナイなど11のポリスの盛衰をスケッチすることで、各々がギリシア世界で果たした役割を明らかにして、ギリシアの時代の流れを描き出しています。
ここでは、監修者のあとがき(215頁〜217頁)の一部を引用して、簡単にこの本を紹介させていただきます。
「本書は、十一のポリス(都市国家)の盛衰史を横糸におりこみながら、ミュケナイ時代からヘレニズム時代までの古代ギリシア史を、一般読者向けにわかりやすく物語る入門書です。
単に11の都市の歴史を羅列するのではなく、それぞれがギリシア史という大きな舞台にどのような役割をもって関わったかを描くことによって、全体がひとつながりの通史として完結しています。
各章では、各都市の興亡史が、神話と伝説、考古学的遺物、古典史料などを平易に紹介しながら描かれています。
また、時代的にも地理的にも、従来よりはるかに広い範囲にわたって古代ギリシア世界が描かれている点も注目されます。
だが、何より本書が他の類書と違うのは、古代ギリシア文明に対する著者自身の基本的な態度です。
著者は、ギリシア文明を近代西欧文明の輝かしい祖先として称賛する立場に、はっきりと別れを告げます。
本書の『エピローグ』でも、古代ギリシアが近代西欧とは決定的に異なる「他者」であるとの主張を繰り返します。
著者が強調したいのは、西欧中心主義的な価値観を古代ギリシアに投影することの危うさです。
その上で、彼は、政治的議論の「開放性」こそギリシア人からわれわれに手渡されたよき遺産です、と結ぶのです。」
ロビン・オズボン/佐藤昇訳『ギリシアの古代』

ロビン・オズボン著/佐藤昇訳『ギリシアの古代—歴史はどのように創られるか?−』刀水書房、2011年6月刊、261頁、2800円
本書は、『刀水歴史全書—歴史/民族/文明—』の81巻として出版されました。
原書は、Robin Osborne, Greek History, Classical Foundations Series, London,(2004)です。
著者のロビン・オズボン氏は、イギリスの古代ギリシア史研究家であり、現在ケンブリッジ大学古代史教授です。
最初に、「日本語版によせて」という著者の短いコメントが載せられています。
そこでは、この書物が、いわゆる前古典記と古典期(紀元前800年頃から前300年)のギリシア史の入門書であると同時にギリシア史研究の入門となることを意図していることが述べられています。
そして本書の狙いは、ギリシア史の魅力、ギリシア史の様々な文字史料や考古学史料が、どういったものなのか、そうした史料から歴史的なイメージを紡ぎ出す際に、どのように分析したらよいのか、その雰囲気を味わってもらうことにあるとあります。
目次は以下の通りです。
日本語版によせて
謝辞
はじめに
第1章 馴染み深く、異質なるギリシア
第2章 ポリスを創る
第3章 ギリシアの人口とサヴァイヴァル
第4章 法、僭主、そして政治の創造
第5章 敵対する
第6章 自由と抑圧の都市
第7章 ギリシア都市、斉一性と多様性
第8章 アレクサンドロスーギリシア史終幕?
訳者後書き ー解題に代えて
文献一覧
碑文集・断片集
読書案内
索引(人名・地名・事項)
以下、各章ごとに簡単に要約をしてみます。
はじめに
冒頭に、本書の性格が記されています。
つまり本書が収められているシリーズのタイトル『古典学の基礎』に言及し、この分野の基礎であると述べられています。
そして、次に歴史学の基礎とは何かと問いかけ、各章のトピックと叙述の方向性が示されています。
最後に、本書はギリシアの地図であり、ギリシア史研究者たちが取り組んでいるさまざまな問題を見通すための地図となることを意図したものであると結ばれています。
第1章 馴染み深く、異質なるギリシア
著者は、スポーツ競技から話を始めます。
陶器画にはスポーツ競技の選手たちが描かれています。
近代オリンピックの円盤投げ選手さながら……。
ところが、近代西洋社会と大きな違いがあります。
古代ではおなじみミュロンの「円盤投げ(ディスコボロス)」は裸体像です。
著者は、このことは大きな問題だと指摘します。
つまり、自らの文化を他の文化と区別する際の重要な境界線の一本が、近代西洋社会とは異なるところに引かれていたということになるからです。
古代ギリシアの場合、同性愛は通常の風習でした。
共和政ローマの政治家にして散文家のキケロは、「成人男性と少年の情愛は体育訓練所(ギュムナシオン)で始まる、そこでは同性愛の情事が許され、止まることを知らない。」とギリシアのその風習を道徳に反するものと批判しています。
こうした、成人男性と少年の間に成立する性的関係と、スポーツの結びつきについての言及はローマならず、ギリシアの詩人テオグニスにも有り、また、スポーツと愛の結びつきは、アテネの赤像式陶器に数多く描かれています。
アテナイの同性愛関係に関する美術史料では、十代初めの少年とあごヒゲを蓄えた年長の男性との関係が中心的位置を占めています。
格闘技教習所(パライストラ)は若者たちがたむろする場所であったのかもしれませんが、しかし、スポーツ競技会の方は何か別の、とりわけ宗教的な祝祭に属していたと述べられています。
よく知られているように、古代のオリュンピア競技祭で勝利しても商品はオリーブの冠だけでした。
しかし、実際は、諸都市が副賞を「上積み」していましたし、スポーツ競技での勝利は、優勝者に栄誉(キュドス)を与え、彼はそれによって軍事上の要職を任されたり、あるいは半神として崇められたりするようになりました。
また、逆に、精神は肉体に優越するという考えに由来する、一種の知的スノビズムからのスポーツに対する反発もあったようです。
著者は述べます。
「私たちがギリシアの美術や文学の中で出会う、活動なりモチーフなりに、すぐに親しみを感じてしまい、理解しやすいと思ってしまうからこそ、私たちにはギリシア史が必要なのです。
あのなじみの円盤投げ選手が住んでいた世界では、スポーツ選手として成功した少年が、年長の男性と性的関係を楽しみ、成長すれば、病を癒す力を持つものとして崇められたり、外敵から自国を守る力があると信じられたりしていたということを、私たちは常にわきまえておかねばらならいないのです。(36頁)」
つまり、著者は、私たち自身の文化とよく似た文化、「栄光の古代ギリシア」が、実は、私たち自身が持っている価値観に、少なからず異議を申し立てるものであるという事実に向き合わねばならないと結んでいます。
第2章 ポリスを創る
本章以降は、各章の冒頭に訳者によって、本文の理解のために簡単な前書き(解説)が導入として置かれています。
以下、要約に当たって、各章の冒頭の「本章では、うんぬん」の各文章は訳者の前書き(解説)の一部を引用させてもらいます。
本章では、紀元前8世紀頃から紀元前6世紀頃、ギリシア人によって行われた植民地活動に焦点が合わされて論じられています。
ナポリ湾沖に浮かぶイスキア島に、紀元前8世紀の半ば頃に植民されたピテクサイは、発掘された墓の数などから、人口は5000〜1万人ほどと推定さています。
大量のコリントス産、エウボイア産、ロドス産陶器が出土していることから、国際色豊かな混成共同体であったことが考えられます。
一方で、住民の出身地がどこだったにせよ、墓地の様子から、一定の慣習を共有し、一つの共同体として振る舞っていたようです。
著者は、いくつものギリシア人共同体がそれぞれ、同胞のためだけに植民市建設を決定し、創建者(オイキステス)を選定し、その人物が計画を立てて新居住地の土地分割を行う、そんな筋書きはもはや信用できなくなっていると述べます。
「植民というものは、これまで考えられてきた以上にずっと場当たり的で、日和見的な行動だったとみなすべきでしょう。
例えば、進取の気性に富んだ人々が現状に何らかの不満を抱き、海外植民に関わる諸々のリスクも厭わずに、場合によっては戦闘にまで参加するつもりで、各地から個人として参加してくる、植民とは、そういったものだったかもしれません。」(54頁)
最後に、初期ギリシアを綴るにあたって、前5世紀以降の文献史料が、実際歴史を反映しているといよりは、むしろ「創りだして」いる点を理解して、史料にあたるべきだと述べています。
第3章 ギリシアの人口とサヴァイバル
本章は、古代ギリシアの人口論から講義が始まります。
舞台は、前章で登場したピテクサイです。
ピテクサイは、前8世紀の終わり頃に、5000〜1万人に上る人口を抱えていました。
より正確には、著者は、古代エジプトの「モデル生命表」などのデータを参考に、墓の埋葬品,副葬品に用いられた陶器から、後期幾何学文様期Ⅰ(前750年〜前725年)と後期幾何学文様期Ⅱ(全725年〜前700年)に分けた場合、前者の人口は、2500人ないし5000人であり、後者の人口は7360人ないし1万4720人と成長していたと推測しています。
年齢別人口構成については、乳幼児や子供の墓が、全体の中で高い割合を占めています。
そのことは、ピテクサイが「前線」の一時的な居留地ではなく、家族を構えていた定住地であったことを示しています。
彼らはどのような暮らしをして、これだけの人口を支えていたのでしょう。
著者は、ピテクサイの可耕地から食料がまかなえるのは、人口の半分ないし4分の1、少なく見積もれば8分のⅠないし4分の1と計算しています。
残りの住民のためには食料輸入が不可欠で、ピテクサイの住民は、交易船が定期的に往来することに確信を抱いていたと述べています。
著者はピテクサイが輸入穀物に大きく依存しており、そして交易ネットワークに深く関わっていたことを、人口と農業生産力に関するデータから推測しています。
本章の後半には、アテナイが登場します。
著者は文献資料などから、アテナイの総人口を30万人程度と推測しています。
そして、ギリシア・ローマ世界は「相互に依存した複数の市場の巨大な複合体」でがなく、むしろ自給自足を目指し、分業も最小限にとどまるもの。というフィンリーの主張を批判しています。
すなわち、生産地が明白なアンフォラに関する知見から、この容器にオリーブや葡萄酒を詰めて、様々な方面に広範囲に輸送されていたことが明らかになっています。
また、前4世紀の法廷弁論などからも、当時の国際的な海上輸送の充実ぶりがありありと伝えられています。
著者は、早くも前700年の段階で、ピテクサイの住人が生活物資を確保するのに十分なほど、都市間の物資輸送が発達していたと結論づけています。
第4章 法、僭主、そして政治の創造
紀元前8世紀末以降、地中海世界の各地にポリス(都市国家)と呼ばれる共同体が成立します。
本章では、こうした共同体の紛争解決、統治のあり方を巡って論議されています。
ギリシア語で「アゴン」は、「競い合い」を意味し、スポーツの競い合いを指すこともありますし、訴訟で争うことを意味することもありました。
紛争解決に関わる議論や、訴訟を指す用例は、すでに最古期の作品、二大叙事詩『イリアス』と『オデユツセイア』、また詩人ヘシオドスの『仕事と日』に見られます。
著者は、ここでは、法が問題になっているのではなく、長老やバシレウス(王)が扱うのは、紛争解決にあたっての公正原理だったと述べます。
現存するギリシアの明文法のうち、最も早いものは前7世紀に記録されています。
そして、前700年以後1世紀の後半のうちに、アテネのドラコンの法、スパルタのレトラなどの法がギリシア各地で制定されました。また、これらの初期の法は手続きに執着していました。
紛争や問題を解決する手段として、武力もしくはカリスマ性を持った個人の裁定が念頭に浮かびます。
古代ギリシアでは「僭主」と呼ばれる人々が各地で権力を握ります。
コリントスでは前7世紀に僭主キュプセロスが、アテネではペイシストラトスが登場します。
従来、重装歩兵密集隊の登場と僭主政の成立を関連づける見解がありましたが、著者は戦術の変化は決定的な要素ではないと、そうした見解には否定的です。
また、僭主政の成立を可能にした政治的圧力は何だったのかと問い、最も参考になるケースとしてアテネのソロンの法を考察しています。
法の発生や僭主登場の背景については、都市国家ごとに抱えていた問題、背景となる状況も異なっていたでしょうが、それぞれの都市国家は、それぞれの問題を解決するために、一方ではルール(法)作りに励み、他方ではカリスマ的指導者(僭主)に権限を委ねるなど試行錯誤を繰り返していたようです。
第5章 敵対する
本書のテーマは戦争です。
最初期のギリシア都市国家間の戦争としては、エウボイア地方で行われたレラントス戦争が知られています。
また、ヘロドトスはスパルターテゲア戦争を記しています。
重要な点は、前5世紀のギリシア人によれば、前古典期の戦争は隣国間のものであり、たいてい敗戦国を征服するまでには至らないことです。
つまり、戦争をフェアに行うという慣習は根強く、他都市の征服にはあまり関心がなく、むしろお互いの力関係をどうするかという点に関心があったようです。
(ただし、スパルタとメッセニの場合は、一方が他方に服属するという要素が含まれていますから例外的事例となります。)
また、前古典期の戦争に関するフェアな伝承は、事実を素朴に伝えているだけというよりも「象徴的な表現」と見た方が意味が通るようです。
ギリシア都市間の戦争の目的は、全面降伏を目指したものではなく、境界線の変更や政治体制の変更であり、あるいは競合する隣国に対して自国の優位を見せつけることにありました。
従って、市民団を構成している農民たちが進軍し、隣国の経済的基盤となっている農地を荒らし、自らの耕地を守るために農民=市民が敵を迎え撃つという戦い方は、理にかなっていたわけです。
しかし、前5世紀、前4世紀に主流となった戦争はそれまでのものとはまったく異なりました。
いわゆるペルシア戦争は、ペルシアが目指した広域支配に対して、いくつもの都市国家が連携して戦ったわけですから、隣国紛争とは目的も規模も違っていました。
また、戦後のアテネを盟主とした「デロス同盟」の結成、さらには対ペルシア戦争が海戦に姿を変えたことで、スパルタとアテネは、同盟関係から永遠のライバルになりました。
アテネを盟主とした「デロス同盟」とスパルタを盟主とした「ペロポネソス同盟」の対立は、民主的な統治を推進していたアテネと、少数者の支配体制のスパルタとの対立と結びつけられるようになりました。
こうしてギリシア世界はイデオロギー上、二つに分断され、各都市の内部でも、個人的政治闘争は影を潜め、原理原則に基づいて、民衆統治とエリート支配のいずれかを志向するかによって、親アテナイ派と親スパルタ派に別れて対立することになりました。
第6章 自由と抑圧の都市
本章では、古典期のアテナイ市民(=成人男性市民)たちが、どれほど政治に参加できたのか、自由と平等を謳歌していたのか、そしてそれを実現するために奴隷や女性、外国人などがいかに押さえ込まれていたのか、いなかったのか、その相関関係が浮き彫りにされています。
前5世紀、ギリシアの政治的スローガンといえば「自由」でした。
しかし、自由は、抑圧と表裏一体です。
抑圧することによって自由は支えられ、自由を保障すると思われる構造そのものに、誰かを抑圧するという行為が組み込まれていました。
アテナイ市民にとって、政治がみんなのものだという信念を支えるには、権利に基づいた現代的な平等観よりも遙かに強力な市民平等の意識が必要でした。
そして、市民参加型の民主政は、自己抑圧と他者への抑圧を生み出しました。
他者への抑圧、すなわち、自由は奴隷制と手を携えて成長するというモーゼス・フィンリーの評言は有名です。
彼が想定していたのは余暇と労働の問題で、政治参加するには十分な余暇が必要であり、そのためには奴隷労働が必要であったと考えたのですが、著者は、自由と奴隷制が一体であるという考えは、むしろもっと広い意味において正しいと主張します。
つまり、たいていの市民が従事していた農業労働を考えたとき、農繁期には自由人も参加していたであろうし、逆に農閑期は十分にあり、政治参加実現のための時間的余裕を奴隷労働が生み出していたと考える必然性はないと。
いずれにせよ、市民が平等であるためには、「汚れ仕事」をする他者が必要で、アテナイではそれは奴隷でした。
奴隷の総数に関しては、推定が困難ですが、富裕者の家には相当数の奴隷がいたようです。
そして、多くの奴隷は手工業生産に従事していました。
中には、開放されて市民になるものもいましたが、美術作品や文学作品に描かれている、奴隷たちの歪んだ身体は、拷問、殴打、烙印、むち打ち、重労働が、奴隷たちの身体にその傷跡を残しています。
こうした虐待と身分解放の関係は、矛盾しているのではなく、相互に因果関係で結ばれているようです。
つまり、アテナイ人は奴隷を解放もするからこそ、暴力もふるっていたのです。
アテナイ人が、その市民団の一体性を維持するためには、他者との違いを明確にしておく必要がありました。
彼らは、自分たち自身に他者との決定的な差異を刻みつけ、それによって自らの市民のアイデンティティを刻み込んでいたのです。
もし、アテネ市民が、奴隷を動物扱いすることで、自分たちとの違いを付けていたのだとすれば、在留外人(メトイコス)や女性との違いは、彼らを子供扱いすることで付けていました。
ローマと異なって、アテネの場合市民権付与は極めて制限されており、在留外人に市民権が与えられることはまれでした。
この事実は、「市民団は同質である」というフィクションから眺めて見る必要があります。
同様に、女性が参政権を認められなかったことについても、こうした観点から考えてみる必要があります。
女性を政治から排除することはギリシア世界では普遍的な現象でした。
男性と女性の生活パターンは対照的で、両者はまったく別の存在として見られていました。
したがって、女性を政治から排除しておくことも、参加者全員が同じ経験をしてきたという架空のイメージを抱くのに、極めて大事なことでした。
ただし、アリストファネスの『女の平和』、『女の祭り』などから推測するに、女性が政治的役割を果たすということは、想像の範囲内にあったようです。
また、リュシアスの弁論集には、故人の妻が夫の財産を列挙していく様子も描かれており、女性が家政に大きく関わっていたことは明白で、彼女たちは、ポリスの運営にも大いに関わりがありました。
ポリスの中での女性の中心的役割は、宗教活動です。
実際、ギリシアの都市では、男性を排除する祝祭の方が、女性を排除する祝祭より数多く開かれています。
さらに、宗教活動は、上は全ギリシア的なものから下はデモス(区)に至るまで広範に拡がっており、アテナイ人は男女ともに明らかに週に一度以上の割合で供儀に関わることができたようです。
政治的な集まり(年に40回しか開かれなかった民会)よりもむしろ、宗教的な集まりこそが、ギリシア都市における最も基本的な人々の交流の場だったのです。
最後に、アテナイ民主政は奴隷や女性には抑圧という方法で依存していましたが、前5世紀には、他のギリシア都市に対してはまた別の方法(デロス同盟という形)で抑圧を加え、これに依存していました。
私たちにとって最も衝撃的な教えは、有名なペリクレスの演説(トゥキュディデス『歴史』2巻41章)の中で高らかに唱われている自由の思想が、実際はシスティマティックな抑圧によって実現されていたということです。
第7章 ギリシア都市、斉一性と多様性
本章は、古代ギリシア世界の政治や法、宗教、文化について、斉一性と多様性という観点から概観されています。
ギリシア世界には様々な政治体制が存在していました。
アテナイとスパルタについては、前者は民主政を、後者は二重王政を布いていました。
両者は、対照的に描かれがちですが、実際のところはとてもよく似たところがありました。
スパルタでも、全市民が均質であるというフィクションが用いられ、正規市民は自分たちを「似たもの同士(ホモイオイ)」と称していました。
「市民の均質性」を生み出したのは、スパルタの場合、服属させたギリシ人住民「隷属民」(ヘイロテス)の存在です。
スパルタの隷属民制度は、アテネの奴隷制度とは全くの別物で、隷属民であることとアテネで動産奴隷であるということは大きく異なっていました。
それは、政治と経済(特に農業経済)が複雑に絡み合っていることから来ています。
しかし、スパルタ市民が自己定義する際に、隷属民を「他者」として規定しているのは、アテナイ市民が奴隷を「他者」として扱っているのと極めて似通っています。
また、動産奴隷と隷属民の共通点は、両者とも解放される可能性はあったのですが、自由を手に入れはしても、いかなる政治的権利も手にすることはできませんでした。
アテナイとスパルタを除くと、他の都市の国制について知るには碑文に頼らざるを得ません。
いくつかの政治的問題(例えば、市民資格、評議会の有無、評議会の構成員、公職者の選出方法など)に対して、各都市はそれぞれ異なる決定を下していました。
しかし、18歳以下、女性、在留外人、そして奴隷に市民権を与える都市は一つもありませんでした。
公職選出に関しても、その採用方法は様々でも、公職が世代間で継承されることはなく、長子に政治的な特権が認められることはありませんでした。
イデオロギーの論争が繰り広げられ、内戦時には流血の惨事となっても、彼らは限定的な枠組みの内で対立していたに過ぎないのです。
このことは、政治と法律は密接に結びついていたわけですから、体制に関わる基本的な枠組みが一致していれば、法的な問題に関する基本的な枠組みも一致していることになります。
もちろん、個別の法規定に着目すると様々な法規定がありますが、その背後にある決まったパターンを見て取ることができます。
すなわち、都市は違ってもそれぞれの法は決まって同じ「型」を持っているのです。
つまり、どんな問題に関して法を制定すべきか、どのような観点から法の枠組みをつくるべきか、こうした点については、どの都市も似通っていたと言えるでしょう。
とりわけ、国際法に関連する分野では、異なる都市がおおよそ類似した法規定を持っていることに大きな意味がありました。
宗教に関しては、ギリシアの各都市に見られる宗教儀礼の性格は、およそ統一的と言えるものではありません。
神殿の造形は各地域ごとに多様で、最重要聖域と中心市域との地地理的関係も様々です。
青年男性像(クーロス)、少女像(コレー—)などの奉納品の違いはさらに一層顕著です。
神殿建築のスタイルと奉納物というモノから、祭祀活動の多様性を視覚的に確認することができ、実際祭祀活動そのものも疑いなく多様でした。
こうした多様性が解消されることは決してありませんでしたが、時代を経るととともにギリシア都市の相互の類似性が次第に高まってきます。
このことは、アルファベットの変化からうかがい知ることができます。
書体の規格化、書法の標準化です。
それは、陶器にも、建築にも、悲劇にも当てはまります。
前5世紀から前4世紀にかけて、アテナイは政治的にもギリシア世界の中核国となり、一大消費センターとして、ギリシア各地の人々を引きつけました。
アッティカ式の陶器や、悲喜劇などといった物質文化、精神文化が生み出され、育まれ、そしてギリシア世界の各地に広まっていきました。
各地のギリシア人、ならびに非ギリシア人をアテナイに引きつける力自体が、国内の文化活動に対する刺激となり、ペロポネソス戦争敗北後もアテナイが長くギリシア世界の文化的中心であり続ける要因となったのです。
第8章 アレクサンドロス —ギリシア史終幕?
本章ではペロポネソス戦争以降のギリシア史が扱われています。
この時代は、しばしば古代ギリシア衰退の時代とすらされてきました。
しかし、こうした評価は現在、あまり正当なものだとは考えられていません。
それでは、紀元前4世紀、そしてヘレニズム時代にかけて、ギリシア世界にはどのような変化が生じていたのでしょうか。
どのような点で継続性が指摘できるでしょうか。
また、それらはどれほどの歴史的意味があったのでしょうか。
著者は、まずペロポネソス戦争後のアテナイの歴史から話を始めます。
スパルタに支援された「三十人僭主」の崩壊から、スパルタ「帝国主義」の問題点を、他国の制度を改変するよりも、「友人」を権力の座につけて他国を操ろうとした点にあると指摘します。
そして、アテナイの「第二次アテナイ(海上)同盟」に言及し、さらに、スパルタと将軍エパメイノンダス率いるテバイの対立、スパルタの敗北、そしてマケドニアの台頭、フィリッポスの死、アレクサンドロスの登場とギリシア世界の歴史を概観します。
前5世紀の歴史は概して、アテナイ人、スパルタ人、コリント人がどうしたと叙述し、あえて個人を中心に据えて前5世紀の歴史を構築する近代の歴史家はいません。
しかし、前4世紀には、前5世紀と異なり、傑物が活躍するための歴史的環境が作り出されていました。
また、アレクサンドロス以降のギリシアのポリスが、前5世紀のような独立自治を、二度と謳歌することはありませんでしたが、市民生活の様式には継続性があったようです。
さらに、ヘレニズム期とそれ以前のギリシア都市の違いは、一つには都市の決議を文章化する傾向(碑文)にありました。
ギリシア史上の重大事件が、ギリシア諸都市のほとんどの住民に深刻な影響を与えた、などということは決してありませんでした。
そしてまた、ヘレニズム時代と古典期の市民生活の間には、さほど大した違いはありませんした。
前古典期に小規模な自治都市国家において繰り広げられて来た市民生活の様式は、その後も長きにわたって、ギリシアにおける市民生活を支える枠組みであり続けました。
また、都市国家の自治政府がどのようなものであるべきか、こうした理念はギリシア本土で確立しましたが、やがて東はアレクサンドロスの征服した領域まで、西はローマ人の征服した領域まで拡がっていきました。
すなわち、自治政府のありかたは、ヘレニズム時代にも各地で継承され、そして、後代にまで継承され、影響を与え、我々が「自治政府」を思い描く際に、そのイメージを何らかの形で規定しているのです。(訳者の注引用)
澤田典子『アテネ 最後の輝き』
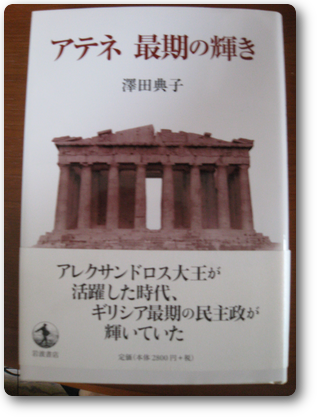
澤田典子著『アテネ 最後の輝き』岩波書店 2008年3月刊 269頁 2800円
著者は、「はじめに」で、カイロネイアの戦いから話を始めます。
そして、カイロネイアの平野で、自問します。—この地で、フリッポスはギリシア世界の覇者となり、ギリシアの「古典期」は終わりを告げた。ギリシアの「自由」は、ここで滅びてしまったのだろうかと。
前338年のカイロネイアでの敗北によってギリシアの「自由」に終止符が打たれた、というのは、私たちが馴染んできた通説です。著者は、疑問を呈します。
そもそも、前338年の敗戦は、「古典期」という栄光の時代に終止符を打つ重要な画期だったのか。アテネにおいて、前338年をもって何かが決定的に変わったのだろうかと。
本書の目的は、英雄アレクサンドロスの陰で、注目を浴びることの少ない、彼の時代のアテネの実相に迫ることにあります。
本書の構成は、以下の通りです。
はじめに。
序章—「黄昏のアテネ」に迫る
第一章 決戦へ
第二章 敗戦—マケドニアの覇権
第三章 対決「「冠の裁判」
第四章 平穏—嵐の前の静けさ
第五章 擾乱—ハルパロス事件
第六章 終幕—デモステネスとアテネ民主政の最後
終章
史料について
主要参考文献
関連年表
あとがき
序章—「黄昏のアテネ」に迫る
著者は、本書で、アテネの「黄昏」といわれる、前388年からラミア戦争に敗れる前322年に光を当てると、さらに、弁論家デモステネスを主人公として、彼の人生の最終章を通じて、アテネの「黄昏」とされる姿に迫るという見通しを述べています。
民主政のしくみ、民会・評議会・民衆法廷の既観に続いて、本書で問題となる二つの裁判(「冠の裁判」と「ハルパロス裁判」)について、簡単に触れられています。
そして、次にアテネの場合、「政治家」とは、どのようなものか。という点について、M.H.ハンセンの「政治家」を「レトルとストラテゴス」と定義する研究を紹介し、前4世紀には、指導者の機能分化・専門分化が進んでいたこと、「政治家=レトル」であり、彼らは総じて、富裕者階級であったとみなしています。
さらに、前338年〜322年の政治家達として、従来の「党派」というモデルを斥け「政治グループ」というモデルを提唱した、R.シーリーの見解が紹介されています。
第一章 決戦へ
本章では、カイロネイア以降のアテネに迫るための前提として、決戦の日に至るまでの、デモステネスの生きざまとアテネの歩みが既観されています。
まず、ペロポネソス戦争敗北後の、アテネの第二次海上同盟の盛衰、エウブロスによる財政再建、マケドニアの台頭が描かれます。
次に、デモステネスの前半生が述べられます。最初に、生い立ちから、政治家としてデビューする前355年の『アンドロティオン弾劾』(第22弁論)までの歩みが、簡単にスケッチされています。
そして、彼が、対外不干渉主義を取るエウブロスに対抗する形で、反マケドニア路線を選択したこと、オリュントス戦争、フィロクラテスの和約を通して、反マケドニアの闘士へと変貌していった過程が記述されています。
最後に、「宿敵」アイスキネスとの対立を軸として、カイロネイアの戦いへと至る過程が述べられます。アイスキネスの紹介に始まり、両者の最初の対決(両者の同名の弁論『使節職務不履行について』デモステネス第19弁論、アイスキネス第2弁論)、そして、フィリッポスの勢力伸長の過程で、アテネの世論は、デモステネスら反マケドニア政治家たちへと傾斜します。「時の人」となったデモステネスは、テーベとの同盟締結に成功し、こうして、カイロネイアの戦いを迎えます。
第二章 敗戦—マケドニアの覇権
本章では、カイロネイアでの敗北以後から、アレクサンドロス大王のペルシア征服までの歴史が、マケドニアとギリシアの関係を軸に記述されています。
フィリポスとアテネの間の「デマデスの和約」は、アテネに取って寛大なものであり、コリントス同盟の成立により、マケドニアの覇権のもとで、ギリシア世界の平和とギリシア諸都市の自治自由が保障されました。しかし、テーベ・コリントスなどに、マケドニア駐留軍が置かれ、これらの駐留軍はマケドニアによる支配の象徴的存在と見なされます。
敗戦直後の、アテネでのデモステネスの立場は、葬送演説を行う大役に任じられており、デモステネスの活躍が注目されます。
そして、フリッポスの暗殺に続いて、アレクサンドロスの登場です。
フィリッポスの暗殺に乗じて、テーベの反乱が起きます。アテネは不関与を決めますが、デモステネスは、金銭の提供など裏工作を行ったようです。そして、テーベの壊滅。この事件は、アテネ市民にとって、カイロネイアでの敗北よりも衝撃的な出来事であり、以後、マケドニアへの抵抗気運は消え、デモステネスでさえそうした動きを起こそうとはしなかったようです。
著者は、次にアテネとのかかわりに注目しながら、アレクサンドロスの遠征を既観します。
注目に値するのは、グラニコス河畔の戦いでの、ペルシア陣営で戦ったギリシア人の傭兵の存在でしょうか。捕虜の中にはアテネ人も含まれており、アテネは捕虜の釈放を求めて、アレクサンドロスのもとに二度にわたって、使節を派遣しています。
アレクサンドロスの東方遠征の途上、スパルタが反旗を翻します。「アギス戦争」です。アテネは同調せず、蜂起はアギスの死を持って終ります。
著者によれば、この時期のアテネは、「マケドニアの平和(パクス・マケドニカ)」のもとで、エーゲ海における通称の安全という恩恵を享受し、リュクルゴスの財政指導によってこれまでにない繁栄を手にしていました。そして、この経済的繁栄といった要因が、アテネとマケドニアの平穏かつ良好な関係を生み出していたと結論づけています。
第三章 対決—「冠の裁判」
前330年のデモステネスとアイスキネスの対立の最終幕となる「冠の裁判」について、考察がなされています。
著者は、まず、「冠の裁判」が、新マケドニア派と反マケドニア派の対立という通説に、疑問を呈しています。両者が、何を争点にして争ったのかに着目して、この「弁論家の戦い」を検討しています。
「冠の裁判」は、前336年のクテシフォンによるデモステネス顕彰の提案に対し、アイスキネスが、「違法提案に対する公訴(グラフェ・パラノモン)」を行ったことから始まります。ところが、裁判は中断します。フィリッポス2世の暗殺、アレクサンドロスの即位という激変が原因と考えられています。では、なぜ、6年後の前330年に突然、裁判は始まったのか。
著者は、裁判開始のイニシアティブを取ったのは、誰かと問います。
クテシフォンの提案の「違法性」についての、アイスキネスの議論に正当性があるという通説に対する、E・Mハリスの研究を参考にしながら、アイスキネス自身が、自分の法的な議論が正当性を持たないことを自覚していた、と指摘しています。
そして、「公訴を取り下げた者は、100ドラクマの罰金と市民権喪失に処される」という「外的圧力」が、アイスキネスが裁判を開始した理由であると推測しています。つまり、イニシアティブは、デモステネスの手にあり、アイスキネスを脅して、裁判の開始を強いたと見なしています。
さて、次に、著者は「弁論家の戦い」として、二人の弁論に取りかかります。
アイスキネスの『クテシフォン弾劾』(第3弁論)とデモステネスの『冠について』(第18弁論)、の要点が整理されて述べられています。
そして、デモステネスの完勝とアイスキネスの亡命は、反マケドニア派が親マケドニア派に対して勝利をおさめたということではない。デモステネスという現役の政治家と、アイスキネスというすでに引退した政治家が、現在の政治的主義主張とは異なる次元で争った裁判、それが、「冠の裁判」であったと結論づけています。
第四章 平穏—嵐の前の静けさ
本章では、最初にデモステネスの隣人達と称して、リュクルゴス、ヒュペレイデス、デマデス、フォキオンの四人のプロソフォグラフイーがなされています。
まず、リュクルゴスの業績を検討し、その公共事業、ならびに、エフェベイア制度の整備を挙げ、彼の非愛国的行動者に対する告発は、古き良きペリクレス時代のアテネの復興を目指す帝国主義に根ざしていたと指摘しています。
次に、ヒュペレイデスの反マケドニアの政治家としての活躍、喜劇作者等による揶揄や逸話が紹介され、さらに、デマデスに関しては、「売国の徒」と「マケドニアの追従者」というレッテルが、貼られてきたが、著者は、「愛国者」の一人と見なしています。最後に、政治家として、そしてストラテゴスとして活躍したフォキオンに関しては、著者は、ベッロホのいう「穏健的親マケドニア派のリーダー」でも、ターンの言う「寡頭派のリーダー」でもなく、アテネのために最前をつくした慎重な政治家として評価しています
次に、前322年に終止符が打たれるまでの、十数年間のアテネ民主政の姿が描かれています。「反僭主法」について、それが、アレオパゴス評議会を守るための規定だという説を紹介し、市民たちの民主政への傾倒のしるしと捉えています。つまり、民主政イデオロギーの宣伝として、何らかの実効性を期待した法というより、宣誓のような色彩を帯びた法と理解しています。そして、反僭主法に描かれたデモクラティアの女神の姿、擬人化は、デモクラティア信仰の活発化と見なしています。
さらに、この時期に頻発した、「民主政転覆罪」という、弾劾告発(エイサンゲリア)に触れています。著差は、この裁判も、民主政の「変質」であるかもしれないが、「衰退」とは言い切れない、民主政に向けられた市民たちの情熱の高まりと解しています。
最後に、動乱の前触れとして、リュクルゴスの最後、アレクサンドロスの「亡命者復帰王令」、そして次の章のテーマであるハルパロス事件の張本人、ハルパロスについて、その人物像が描かれて、この章は閉じられています。
第五章 擾乱—ハルパロス事件
著者は、最初にハルパロス事件とは、何かから記述を始めます。まず、それがアテネ史上随一の大収賄疑惑事件であったこと。デモステネスを亡命に至らしめた一大スキャンダルであったことを。そして、従来のこの事件の捉えられ方を紹介しています。対マケドニア政策を軸とする争い、急進派と穏健派の対立とする解釈を。
そして、ハルパロス事件の経過が述べられ、表でこの事件の年譜がまとめられています。
次に、事件当時のアテネの情勢が、述べられます。亡命者復帰王令、そして、それに対するアテネの機運は、つまりアレクサンドロスに対する抵抗機運は、醸成される素地はなかったと理解しています。アレクサンドロスの神格化問題については、アレクサンドロス側からの命令はなく、ギリシア人達が自発的に神格に応じたと推測し、アテネの対応も、デモステネスが神格化容認に傾き、デマデスの提案により神格化を承認したと述べています。
そして、本章の中心テーマであるハルパロス裁判の検討に入ります。
まず、最初に、裁判の経過と結果が述べられます。結果は、デモステネスの有罪、50タラントンの罰金。この罰金刑については、著者は、本来ならば、死刑であるところが、50タラントンという罰金刑は軽かったと解し、この裁判の不可解さの印象、その焦点は収賄事実よりもどこか他にあったのではないかと推測しています。
そうして、次に裁判の背後の人間模様に目を向けます。
「被告の顔ぶれ」、「告発人の顔ぶれ」の簡単なプロソフォグラフィーがなされ、著者は、さまざまな「個人的対立」に着目しています。そして、あくまでも、推測の域をでないがと、ことわりながら、被告人と告発人の間のさまざまな「個人的対立」が裁判において、大きな比重を占めたと捉えています。
すなわち、ハルパロス裁判の性格を、「個人的対立」を大きな要因と捉え、従来の対マケドニア政策を軸とした政治的対立という単純な構図で、この時期のアテネの政治を把握するのは妥当ではないと論じています。
第六章 終幕—デモステネスとアテネ民主政の最期
民主政アテネの最後の戦い、題されて、デモステネスの亡命生活から始まり、ラミア戦争にいたる過程、そして、ラミア戦争の経過と、敗北によるアテネ民主政の終焉が描かれています。
次に、愛国者たちのそれぞれの最後として、ヒュペレイデスの最期、デモステネスの最期、デマデスの最期、フォキオンの最期が、簡潔に記述されています。
終章
本章では、最初に、デモステネスの遺したものと題され、デモステネスの今に至る人物評価の変遷が記述されています。
前280/79年、アテネの民会で、デモステネスの顕彰決議がなされ、彼の名誉は回復しました。著者は続いて、今までの歴史の中で、彼の弁論家としての評価、そして、政治家としての評価に目を向けます。近代以降、デモステネスは同時代の政治的文脈の中で、その評価は大きな変遷を遂げています。とりわけ、19世紀から20世紀前半にかけて、政治家デモステネスに対する評価は、「愛国的英雄」というプラス評価と「狂信的なエゴイスト」というマイナス評価の間をめまぐるしく揺れ動いていると指摘します。
著者は、政治家としての「評価」について、後世の後知恵や、現代の私たちのモラル・スタンダードで判断して彼の政策の功罪を問い、政治家としての評価を下すのに批判的です。デモステネスの『神話』や結果論から離れて、彼の言動や政策をその時々の状況や文脈の中に位置づけ、その政治的社会的脈絡の中で丹念に検討を重ねることが、必要であると指摘しています。そして、その意味で、前338年以降の時期は、血の通ったデモステネス像に迫るための格好の素材と言えるとしています。
次に、「黄昏」の民主政について、論じられています。
著者は、カイロネイア以後のアテネは、平和と繁栄を享受し、前323年のアレクサンドロスの急逝まで、アテネとマケドニアの関係は概ね良好であり、彼の死を持って、抵抗のスタートが切られたと見なしています。
そして、アテネの政治的状況も、対外政策の対立軸は消滅し、政治における個人的要因の比重が増したと推測しています。
最後に、この時期のアテネ民主政は、「衰退」であったのかという問題に言及しています。著者は、アテネ民主政は、前322年に終止符が打たれるまで、しぶとく生命力を持っていたと見なしています、本書に登場したデモステネスをはじめとする政治家たちは、そうした民主政の中で、光を放っていたと。
著者は、抽象的な言い方であるが、とことわりながら、民主政の本質が、市民たちが自ら選びとった生体にエネルギーを注ぐこと、政体を誇りにし、維持に力をつくすことであるなら、民主政の命は、前338年に絶たれたわけではなく、独立国家としての地位は失ったもの前322年に終止符が打たれるまで、強靭な生命力を持ってたくましく生き続けたと言えると結論づけています。
著者は述べます。デモステネスの人生の最終章である「黄昏のアテネ」は、民主政が老衰した「衰退」ではなく、民主政が最後の輝きを放った時代、最後の花を咲かせた時代であったと。
周藤芳幸『古代ギリシア 地中海への展開』
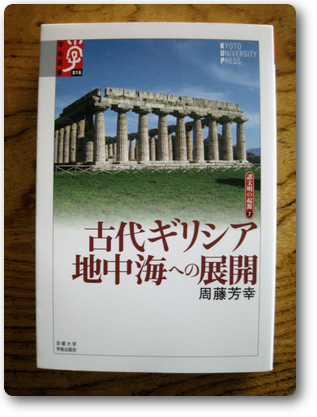
周藤芳幸著『古代ギリシア 地中海への展開』京都大学学術出版会 2006年10月刊 436頁 1800円
本書は、学術選書シリーズ<諸文明の起源>全15冊の内の、7冊目として書き下ろされたものです。ただし、一部の内容は、既発表論文に依拠しているようです。(「あとがき」参照)
概説書ですが、著者も「はじめに」と「あとがき」で述べていますように、古代ギリシア文明の諸相を網羅的に論じたものではなく、考古学的な証拠から検討することの可能な問題を取り上げています。
近年の考古学的知見を交えた、著者独自のアプローチが試みられ、随所に自説が展開されています。そういう意味では、意欲的な著書です。
著者は、「はじめに」で、古典期中心の伝統的なギリシア史に代わる、「長いギリシア史」(ギリシア文明を、ミケーネ時代からヘレニズム時代にいたる長期的な構造転換の動態として把握する歴史観)、と「広いギリシア史」(アテネ中心ではなく、地中海というコンテクストを重視した、古代ギリシア文明の形成過程の復元)に、叙述の重心をおくと述べています。
著者によれば、本書の内容は、五つの部分から構成されています。
以下、著者の構成に従って、簡単に紹介します。
第1の部分:(第1章)
第1章 古代ギリシア文明へのアプローチ
まず、著者は、最初に「空間の構造」と「歴史的素描」を述べます。
.古代東地中海世界は、「地中海の北側」「北アフリカの沿岸諸地域」「地中海の東端部」の三つの単位に分割され、その三つの地理単位を基盤としながら、ギリシア人の文化圏と在地の人々の文化圏がモザイク上に展開する複雑な空間構造を呈していたと。そして、次に、青銅器時代からヘレニズム時代に至る簡単な歴史的素描をおこないます。
次に、「古代ギリシア文明」の構築として、ルネサンスのヨーロッパにおいて再発見された「古代ギリシア文明の二重性」が論じられ、ヴィンケルマンの提示した新古典主義のパラダイムの影響、近代国民国家ギリシアの国民たるエリネスの対外的なアイディンティティの拠り所としての役割についての記述が続いています。
最後に、古代ギリシア文明へのアプローチは、「孤立する古代ギリシア文明」とギリシア・ローマ文明の世界とエジプト・西アジア文明の世界とをまったく異なる実体として捉える「地中海分断モデル」(著者によれば、ルネサンス以来の人文社会科学の発展の過程で、とくに、18世紀の後半から顕著になってきた思考の枠組み)、を克服することから始められなくてはならないと結んでいます。
第2の部分:(第2章)
第2章 ギリシア文明の起源—ミケーネ文明
宮殿を中心とするミケーネ文明とポリスを中心とする古代ギリシア文明との関係の解明のため、ミケーネ文明のさまざまな文化的特徴が論じられています。
まず、著者は、最初に、ミケーネ社会研究の初期の二つのモデル、ヴェントリスとチャドウィックによる「中世封建社会モデル」とフィンリーによる「西アジア社会モデル」の歴史的背景を明らかにし、批判しそして斥けます。
次に、ミケーネ文明最初期の支配者の性格として、円形墓域と竪穴墓と副葬品を検討し、前者が在地の文化伝統の上に立っているのに対し、後者が当時の国際的交換網の中に身をおいていたことを示唆していると指摘しています。
また、ミケーネ社会初期の王権の性格を考える上で重要な戦車は、実用的な武器というよりは、支配者の地位と密接に結びついた象徴としての意義の方が大きかったと推測しています。
次に、ミケーネ文明の王権と社会構造を論じています。
著者は、竪穴墓、トロス墓を検討し、両者に共通するミケーネ時代の葬制の顕著な特徴は、個々の墓がほとんど常に複数の被葬者を前提に構築されていることを指摘しています。そして、この葬制からミケーネ文明の社会の最上層に位置していたのは、単数形の「王」ではなく、「集団(地域エリート層)」であったと推測しています。
さらに、ミケーネ社会が「再分配システム」を経済的な基盤としていたこと、そして、大規模な土木事業が論じられていますが、土木事業は、必ずしも専制的な王権のイニシアティブによるものではなかった可能性を指摘しています。
最後に、東地中海世界とミケーネ文明を論じています。
著者は、まず考古学的証拠から、ミケーネ文明世界の王権とエジプトとの王権の相互の外交関係を推測し、さらに、水上考古学の知見から西アジアとクレタ島の商業的な交渉の可能性も指摘しています。
そして、東地中海のコンテクストに位置づけ直すと、ミケーネ世界のなかには、すでにポリス社会へと連続していく社会構造の特徴が、少なからず芽生えていること、ミケーネ文明の形成からポリスの成立までが、一連の歴史的プロセスとして把握されうると推測しています。
第3の部分:(第3章から第5章)
第3章から第5章で、ミケーネ社会からポリス社会への移行期を問題としています。
第3章では、初期鉄器時代(いわゆる暗黒時代)の物質文化として、アッティカ、ならびにギリシア各地の幾何学文様土器について、その様式の多様性が論じられています。葬制とその社会構造の密接な関係が指摘され、さらに、集落研究の現在として、クレタのカヴーシ、メッセニアのニホリア、エウボイアのレフカンディア、エレトリアの対岸オロポスの発掘が紹介されています。
第4章は、著者によれば、「広いギリシア史」の根拠となるギリシア人の世界の空間的拡大をテーマにしており、本書の中でも特に重要な部分と述べられています。
ギリシア人の植民が扱われており、ピテクーサイの遺跡や、シチリアの植民市、タラス植民、キュレネ植民、黒海沿岸の植民、そしてエジプトのナウクラティスが、近年の考古学的知見より紹介されています。興味深いのは、エジプト文化のギリシアへの伝播に貢献したのは、ギリシア系の傭兵であったという指摘です。
最後に、大植民時代の遺産として、植民市の都市化について論じています。都市化が、前7世紀にさかのぼること、そして、均等に区画された街区が、市民団の平等の原理であったことが述べられています。
第5章は、まず最初に、前8世紀のギリシアで創造されたアルファベットの成立過程について論じられています。
B.パウエルの研究、ギリシア語のアルファベットは、特定のギリシア人「翻案者」が、フェニキア人の「情報提供者」から学んで作ったこと。そして、次にR.ウッダートの「正書法」の研究、アルファベットのリテラシーがキプロス音節文字(遡れば線文字B)の識字能力を前提として成立したという論が紹介されています。著者は、線文字Bとアルファベットとのあいだに連続した記述の伝統があるという主張に、ウッダートは、アルファベットの基本単位である音素に注目することで、精緻に跡づけたと述べています。
次に、著者は、表象芸術の世界を論じます。
彫像の制作や神殿の建築を通して、そのオーダー(標準的規格)の確立は、ギリシア人たちに精神文化での一体性を強く訴える視覚的効果をもっていたことを指摘しています。さらに、個別的、メッセージを発するようになったのが、神殿の破風やメトープに配された装飾で、その政治的イデオロギーの頂点に位置するのが、アテネのパルテノン神殿であるということ。そして、パルテノンの東西の破風、四方のメトープには、女性や外国人などの「他者」を力で排斥するモチーフが共通しており、この時代のアテネ市民団のイデオロギーが誇示されていると結論づけています。
第4の部分:(第6章から第9章)
史料的にもっとも恵まれている、アテネを例にとり、ポリス社会の構造的な特徴に四つの側面から光をあてています。
第6章では、デーモスとフラトリアの問題を軸に、古典期のアテネ市民が所属しいた中間的な諸集団の性格と機能が論じられています。
まず、古典期のデーモスについて、考古学的調査の成果から、ハライ・アイクソニデスの景観が説明され、それが、ポリスの縮図あったことが明らかにされています。さらに、それとは対蹠的な景観をもっていたデーモスとして、辺境のデーモス・アテーネー(孤立農場の集落)が挙げられています。
デーモスの規模と数が論じられ、著者は、古典期の139という数が、前五世紀の社会変動に伴う、デーモスの再編成の結果であると推測しています。
次に、フラトリアが取り上げられています。フラトリアは何か、という説明に続いて、ゲネスとの関係を論じています。著者は、「デーモティオーニダイの決議」を取り上げ、それが、ゲノスの衰退によるフラトリアの民主化というより、両者の密接な連携、フラトリア内部での入籍手続きの簡素化を目指したものと解釈しています。
最後に、古典期のアテネの共同体の構造(デーモスとフラトリア)に関して、従来説明されてきた、国制レヴェルと私法レヴェルとの二系統の編成原理の並列図式は、実態に即したものではなく、むしろ、この二系統の編成原理は、市民権の認定を軸として相互に密接な結びつきを保持していたこと、さらに、フラトリアは実質的な機能を備えた国制上の単位だったと結論づけています。
第7章では、アッテイカ周縁部に残された考古学的な証拠を吟味することより、国境地域の意義からポリスの自律性を逆照射しています。
著者は、最初に、「ポリスとは何か」という議論から話をはじめます。そして、理念ではなく、現実はどうであったかと問い、国境地域の問題を取り上げます。
まず、考古学的調査、さらに民俗学的調査の意義について述べます。具体的には、アルゴリス半島のフルニ谷のエコシステムが紹介されています。
そして、アテネの領域周縁部としては、スクウルタ平野、オイノエ平野、クンドゥーラ谷、カンディリの四カ所が、考古学的踏査をふまえて既観されています。そこでは、内陸交通路の存在を考慮する必要が説かれています。
著者は、国境地帯に緩衝地帯とも呼ぶべき地域が広がっていたこと、そして、その帰属の曖昧な緩衝地帯が、相互に自律的なポリスが併存していくためには必要な空間であったと推測しています。その空間に固有の生態学的価値があったため、「共有地」としてみなされていた地域は、孤立農場を足がかりにした開発の対象とされ、その結果、係争が生じると線による画定が行われた。自律的なポリスが歴史から姿を消す前2世紀に、こうした国境線の画定が行われたことは、国境地域のももっていた独自の意義を逆照射していると結論づけています。
第8章では、アテネの国家祭儀の一つであるディオニュシア祭の分析を通じて、祭儀がポリスの空間的な統合に果たした役割の一端を明らかにしています。
まず、最初に、古典期のアテネにおけるディオニュソス祭儀の全容、オスコフォリア祭、在地のディオニュソス祭とレナイア祭、アンテステリア祭、中心市のディオニュソス祭が紹介されています。
次に、「在地の」ディオニュソス祭と「中心市の」ディオニュソス祭の、二つの起源について論じています。著者は、「中心市の」ディオニュソス祭の創始を、全6世紀の末、クレイステネスの改革後と推定し、「在地の」ディオニュソス祭が、比較的歴史の浅い祭儀であり、中心市のそれを模倣する形で成立したと推測しています
著者は、両者の関係について、ペイライエウスのディオニュソス祭を取り上げ、ポリスによる「在地のディオニュソス祭」への干渉事例の知見から、在地デーモスの中心市からの自律という傾向の可能性を指摘しています。
最後に、『アカルナイの人々』を引用し、在地のディオニュソス祭が、在地デーモスの自律性の拠り所となっていたことを明らかにしています。そして、『アカルナイの人々』が、中心市と在地デーモスの緊張関係を想定して、はじめてその本質を読み解くことが可能なこと、さらに中心市とアッティカ在地デーモスによって構築された古典期アテネというポリス空間の中で、ディオニュソス祭が果たした役割が、そこに照射されていると述べています。
第9章では、ジェンダーとセクシュアリティーが論じられています。
まず、著者は、ジェンダーとセクシュアリティーが分析概念であること、そして、ジェンダーとは、生物学的な性であるセックスに対して、後天的もしくは社会的に構築された性の特徴、すなわち文化的性差のことを指して用いられること。これに対して、セクシュアリティとは、セックスやジェンダーから派生する性的な嗜好、性的な欲望、性行為などの現象の総体を意味していると解説しています。
次に、古典期のアテネの女性について、ジェンダーの明確な区分と公的領域からの、女性の排除は、古典期アテネの顕著な文化的特色であるが、物質文化の研究は、こうした女性の姿にどのような光を投げかけているかと問うています。
著者は、葬制の変遷の検討から、アテネでは遅くとも前9世紀までに、ジェンダーが社会の編成原理の上で重要な位置を占めるようになっていたこと、つまり、前8世紀には、特権化された成年男子市民の平等主義的な関係に基づく市民関係が達成され、女性は組織的にそこに参加することを排除されていたと指摘しています。
さらに、当時の家屋の空間構造がジェンダーによって規定されていたこと。いわゆる、女性部屋と男性部屋の構造を、ジェンダーの視点から、考古学的検討を行っています。そして、家屋の内部こそが、女性の活動の場であったこと、古代ギリシアでは、ジェンダーによる空間の区別は、家の内と外との間で成立していたと結論づけています。
そして、男部屋(アンドロン)での「シュンポシオン(饗宴)」が、社会的重要な慣行であったことが論じられています。さらに、ギリシアでの「同性愛」特に「少年愛」について、多くのページが割かれています。少年愛が広く認められていた慣習だったにもかかわらず、ポリスの統治という視点からは、しばしば、これが規制の対象となったことについて触れ、著者は、金銭の授受を介在させことによる職業化をその理由に挙げています。そして、少年愛に反社会的側面があること、古典期のアテネの少年愛は、社会的に矛盾に満ちた慣行であったと述べています。
最後に、古代ギリシアでは、セクュシュアリティの面においてさえ、男女という性差よりも市民か非市民かという構成員資格の差による境界線の方が明確であったらしいと結んでいます。
第5の部分(第10章)
第10章ヘレニズム文明への変貌では、エジプト出土の交易用アンフォラの研究成果に依拠しながら、ヘレニズム時代のエジプト在地文化が、「地中海コイネー文化」へと変容したプロセスを分析することで、ギリシア文明が地中海文明へと脱皮していく過程を描いています。
まず、最初に、ヘレニズム時代と古代ギリシアの経済史研究と題して、M.I.フィンリーの『古典古代の経済』に内在する、二つの問題点を指摘しています。第一に、エジプトのパピルス文書やデロス島の神殿会計碑文のような関連史料が豊富に残されているヘレニズム時代の状況が扱われていないこと。第二に、数量データの欠如を補うために不可欠の考古学的証拠がほとんど利用されていないという点を批判しています。
著者は、こうした研究動向を踏まえて、中エジプトのアコリス遺跡からの出土遺物を手がかりとして、ヘレニズム時代におけるエジプトの在地集落と東地中海を結んでいた経済的関係について、また、それが在地社会に及ぼした影響についえて考察することにより、ギリシア文明のヘレニズム化を考えていくと、本章の見通しを述べています。
まず、アコリス遺跡の考古学的調査が紹介されています。そして、史料としてロドス産の交易用アンフォラが取り挙げられ、その取っ手に押された二種類のスタンプ、「工房銘」と「紀年銘」が説明されています。その「紀年銘」の編年を利用して、この時期の地中海各地の遺跡や遺構の年代を突き止めることが可能になったことが指摘されています。
さらに、ロドス産アンフォラの分布年代については、前210年頃から約100年間にわたって搬入され、そのピークは前150,年頃と推定しています。
他の遺跡の状況、例えばナウクラティス出土の土器の検討から、生活文化の画一化、当時の東地中海における食文化の共通性などから、この時代のエジプトの文化が、ギリシア文化と地中海各地の在地文化との相互作用から生まれたヘレニズム時代の地中海に共通する文化(著者のいう地中海コイネー文化)へと変容していったことを指摘しています。
そして、このような文化変容のプロセスとして、著者は、地中海の穀物交易を挙げています。エジプトにおけるロドス産アンフォラの飛躍的増加は、エジプト産の穀物がロドスの商船によって東地中海の各地に供給されているシステムが確立される過程と、軌を一にしていたと論じています。
また、もう一つのレベルの変化として、首都アレクサンドリアと領域部の関係が考慮されなくてはならないと指摘しています。すなわち、アコリスの石材加工と搬出によるアレクサンドリアとの結びつき、物資や情報の流れは、双方的なものとして理解すべきで、アレクサンドリアへ穀物や石材を運んだ船は、戻る際には領域部では入手できない物資を積んで戻ったはずで、アコリス出土のロドス産アンフォラもそのような船で運ばれたと想定しています。
さらに、前三世紀を通じて、中エジプトとアレクサンドリアとの間の政治的経済的関係が結ばれるようになったこと、地中海コイネー文化は、地中海というマクロなレヴェルでの政治的経済的動向と、先に挙げた局地的な動向との相乗効果によって、各地に浸透していったものと考えられると述べています。
最後に、ギリシア文明から地中海文明として、地中海ではギリシア文明が変容拡大し、エジプト領域部の農村社会の住民もロドスとエジプトとの間の国際交易関係、さらにアレクサンドリアと領域部で結ばれた新たな都市・農村関係という二重の関係の変化への対応を余儀なくされたこと、その過程で、彼らは地中海コイネー文化として装いを新たにしたギリシア文明と同化していったと結んでいます。
本書は、「あとがき」につづいて、「古代ギリシア文明への理解をさらに深めるための文献案内」が紹介されています。「事典」「史料」「通史」「文学と思想」「美術と建築」それに続いて、第1章から第10章までの内容について、より理解を深めるための手助けとなる、邦語文献、欧語文献が提示されています。
馬場恵二『癒しの民間信仰—ギリシアの古代と現代』

馬場恵二著『癒しの民間信仰—ギリシアの古代と現代』東洋書林 2006年8月刊 596頁 6000円
はじめに
著者は、古代ギリシア史の専門家ですが、「はじめに」を一読するだけで、ギリシア史に対する姿勢を知ることができます。
自称「元古代ギリシア史家」というとおり、その視線は現代のギリシアに注がれています。
本書は、30余年にわたる問題意識、古代から現代に至るギリシア人の『癒しの民間信仰』に見られる精神構造を明らかにしようとしています。
大著であり、長年にわたる現地踏査をふまえた、全編を通してあふれるギリシアへの思いは、感銘を与えられます。
そして、本書は、「癒しの民間信仰」(それは、連続性であり)、一方では「ギリシア民族呼称」(それは断絶・絶縁性)双方の検証を重ねることによって、「古代中心」にかたよらない、新しい「ギリシア」像を提示することを重要な狙いとしています。
それは、暗に、現在の古代ギリシア史研究の姿勢が、古代に偏っていることを批判しているようです。
第1章 「癒し」の奉納品
ギリシアにおける「癒しの奉納品」の「古代と現代」を既観することから始めています。
そもそも、「奉納品」は「癒しの祈願」の「癒し手」である「超越的存在」と「癒し」を求める「祈願者」との間の一種の「やり取り」・「かけ引き」という性格を帯びており、「奉納品」はそのような「緊張関係」の所産であること。そして、「奉納品」は「癒しの民間信仰」の限られた一面しか示されていない、という限界性を認識する必要が説かれています。
日本社寺の絵馬、アルトエティング巡礼教会堂の「奉納絵馬」に読み取れた「聖母崇拝」の既観に続いて、ギリシアに入ります。先史クレタ島の「山頂聖所」における「元祖タマ(=癒しの奉納品)」から始まって、畜産生産の向上を祈願しての「甲虫塑像」の考察が続きます。
話は、少しそれて、作家カザンザキスの墓に詣でています。
墓石に刻まれた“私は期待など一切しない。/私は何ひとつ怖れもしない。/私は自由人なのだ(イメ・レフテロス)の名句は感動的です。
話は戻って、「ゼウス埋葬の地」とされたユクタス山頂聖所の訪問で、クレタ島から別れを告げています。
ギリシア世界の「古代タマ」との出会い、アルキノス奉納の浮彫り「絵馬」、ミストラでの現代ギリシアの「タマ」との出会い。
こうした出会いにより、著者は「癒しの民間信仰」の「古代と現代」の「連続性」に強く心を打たれています。
最後に、キプロス島の「タマ」に相当する「平癒祈願/感謝奉納品」である「蝋人形」に触れながら、キプロス島の古代史紹介を兼ねて、旅の紹介がなされています。
第2章 「癒しの聖母」と福音書記者ルカの伝承
「癒しの民間信仰」の根底にある「聖母崇拝」のあり方そのものに目を注ぐ必要から、「古代」に遡る前に、ビザンツ時代の帝都コンスタンディヌゥポリスにおける「聖母による癒し」の背景と理念の根幹に迫っています。
「聖母伝」とマリアの尊称としての「テオトコス(神を産んだ女)」の考察に始まり、「聖母」に先立つ「癒しの聖人」ミハイルとアナスタシアの重要な役割に注目しています。
特に、聖女アナスタシア・ファルマコリュトリア(解毒者)について、牢獄慰問などの伝記、添え名(~トリア)の解説、その特異性を論じ、同聖女が、特別な篤い尊崇を集めていたことを指摘しています。
そして、いよいよ「癒しの聖母」の出現です。
431年のエフェソス宗教会議を挟む前後から、「癒しの先行者」である聖女アナスタシアの「実績」に「便乗」する形で、ビザンツ世界に「癒しの聖母」が徐々に姿を現します。
そして、「癒しの聖母」は「帝都守護」という「国家の癒し」にまでその力量を発揮します。
「福音書記者ルカ」筆と伝わる「聖母イコン」の歴史的役割、さらに、ビザンツ帝都で「聖母オジギトリア(道案内の聖母・付き添いの聖母)」が「癒しの聖母」として最大級に尊崇されていたことを明らかにしています。
次に、「キリスト再臨図」の「懇願(ディシス)の聖母」について論じています。
筆者は、ビザンツ様式の「キリスト再臨図」のイコンや教会堂の壁画、奉納図の銘文の解説、さらには、西方教会の「最後の審判」(ディシスの不在)との比較検討を通して、ビザンツ世界の「ディシス」(懇願)の重要性を指摘し、聖母が罪ある人間と「神の子キリスト」との間に立つ「とりなしの聖母」であることに注目しています。
さらに、ルカ福音書に現れるキリストとともに磔になった「悪党」が「キリスト再臨図」に取り込まれている点、アブラハムの「懐」に抱かれる貧者ラザロのたとえ話などの解説をとおして、ルカ福音書に漂う「寛容」と「包容力」、「優しさ」の雰囲気が、東方教会ビザンツ世界のギリシア人を大いに魅了したであろうと推測しています。
そして、ルカの伝承の説明、テーベの聖ルゥカス教会堂とスゥメラ聖母修道院への訪問が記されていますが、ここで語られる、ポントス・ギリシア人の歴史はとても興味深いものがあります。
最後に、ルカの後代のギリシア世界における「人気」の根底には、「ギリシア」の土壌に古代以来連綿と根を張り続けてきた「癒しの民間信仰」があった、という著者の見方が紹介されています。
第3章「癒しの半神」たちーアスクレピオス以前
先史クレタ島の「山頂聖所」に始まったエーゲ海周辺地域における「癒しの民間信仰」の歴史は、ミノア宮殿文化の崩壊とともに長い「空白期間」に突入します。
「暗黒時代」と呼ばれる霧が晴れるのは、前6世紀/5世紀初め、早くても前8/7世紀のこと。考古学的な手がかりが乏しく、「癒し」関連の奉納品と断定できる遺物は、何一つ発見されていません。
著者は、「癒しの民間信仰」が途中で途絶えてしまったという事態を信じてはいませんが、検証不能の「空白期間」の存在したことは認めています。「癒し」の「空白期間」は依然「空白」のままだとして。
著者は、次に古代アテネの「山頂祭祀」に話を進めます。
ここでは、パウサニアス『ギリシア案内記』を史料に、アテネ周辺の山頂祭祀が紹介されています。
そして、アテネの山々において、「癒し」を目的とする「聖所」が創設される時期に重なって、平野部では、「半神祭祀(ヒーロー・カイト)」と呼ばれる新しい祭祀の勃興が指摘されています。
暗黒時代に台頭した富裕者階層が、ミケーネ時代の古墳の再利用を通して、「死者供養」の習俗に便乗しながら、その祭式儀礼を恒久化させることによって「半神祭祀」を創出したこと。
そして、日常生活につきまとう不安と恐怖にさいなまれる地域住民の「神頼み」こそ、「半神祭祀」の存続の基盤であったことを論じています。
次に、ヘシオドスの「ディケー(正義)」に言及し、そこで記されたダイモン(精霊)を「半神」と読み解き、地域住民が頼りとしたのは、「農作物の稔り」と「悪疫駆除と癒し」の祈願成就であったと推測しています。
さらに、半神祭祀の例として、スパルタのメネライオン(メネラオス半神廟)と半神ヘレネの「癒しの事績」が取り上げられています
前8/7世紀の、オリュンポス神を祀る聖所の出現は、オリュンピアのゼウス祭祀を筆頭に、各地で大量の奉納品の出土によって確認されています。
しかし、著者によれば、「オリンポス十二神」系の神々と「癒し」との結びつきは稀薄で、「癒し手」としての役割は、「半神祭祀」の半神たちに求められ、半神たちの「役割」の明確化と同時に、崇拝者の祈願に真正面から対応できる「新しい半神」の「創出」が求められることになったと指摘しています。
「アスクレピオス祭祀」伝来以前のアテネ市内の「癒しの民間信仰」として、「癒しの半神」ヘーロス・イアトロスを取り上げ、碑文史料などから「国家的祭祀」ではなく、講組織(オルゲオネス)の結社が営む「私的祭祀」であったと推測しています。
次に、アテネ市内の「癒しの聖所」を既観して、最後に、「全力格闘技選手(パングラテス)」テアゲネスを例に、古代ギリシアにおける「癒しの民間信仰」とスポーツの関わりを論じています。
第4章 聖地エピダウロスのアスクレピオス祭祀
哲学者ソクラテスのエピソードから、話は始まります。
「アスクレピオスに雄鶏一羽の借りがある。」という有名な最後の言葉です。
真相は霧の中ですが、前399年には、「医神アスクレピオス」は、アテネのソクラテスにとっては、なじみのある医神であった事実が指摘されています。
次に、アスクレピオスに言及する文献史料の検討に入ります。
前8世紀のホメロス『イリアス』と前5世紀前半のピンダロス『ピュティア祝勝歌3』です。ホメロスの『イリアス』(第2巻軍船のカタログと第4巻)では、アスクレピオスは、「医神」はなく、生身の「人間」の「医師アスクレピオス」にとどまっています。しかし、ピンダロスでは、アスクレピオスの「生と死」を語る中で、神アポロンと人間の混血であったアスクレピオスに「半神(ヘーロース)」の名が与えられています。
このようなアスクレピオスの神域エピダウロスについて、「劇場」をふり出しに「癒しの聖所」が、パウサニアスに従って紹介されています。
そして、「癒しの先行者」として、前章で検討した「半神祭祀」の半神マレアタスが、アポロンと融合して、新しい神格「アポロン・マレアタス」が生まれたこと。
それは、エピダウロス国家が、「国益」の観点から、地方的な祭祀に国家が介入の手を伸ばして、「地元半神マレアタス」と「アポロン」との習合に向かわせたと憶測しています。
そして、前5世紀前半の段階では、アスクレピオスは、アポロン・マレアタスの「補佐役」という副次的な地位にとどまっていたと推測しています。
次に、前4世紀の碑文から判明した、ギリシア各地への「テアーロス」と呼ばれたエピダウロスの宣教活動(神事使節団)に触れています。
そして、いよいよ、「癒し」の実態に迫る「癒しの事績」の碑文史料の検討に入ります。
ここでは、「癒しの事績」の碑文史料(現存碑文は七十例を数える)、事例を十例余り紹介しています。平癒嘆願者が「お籠り堂(アバトン)」に一夜籠って、「夢見」の中で医神の治療を受けて平癒を得る、という話が中心ですが、それぞれ個性的な興味深い話が紹介されています。
また、「お籠り」によらない癒しの例も挙げられており、事例47の「魚の行商人」の話では、「罪の告白」(懺悔)と神の「赦し」が織り込まれていて、「キリスト教」にも通じる宗教的雰囲気さえ感じさせます。
著者は、こうした「お籠り」によらない「癒し」の事例は、「癒しのメカニズム」の観点から、非常に興味深く、キリスト教時代の「聖母・聖人による癒し」の思想と重なる部分もあって重要であると指摘しています。
最後に、「癒しの事績」の国外のアスクレピオスの祭祀への言及、祭祀の国外伝播に触れています。
第5章 アテネ市民テレマコスのアスクレピオス勧請と悪疫流行
前5世紀のアスクレピオス祭祀に関する情報は、アテネからもたらされます。
悲劇詩人ソフォクレスの例です。
ビザンツ時代の史料から、彼が「デクシオン(奉迎者)」と呼ばれ、アスクレピオス勧請に関係したことが記されています。
しかし、アテネ市内へのアスクレピオス勧請について、より直接的な史料は、前4世紀はじめの碑文史料です。
著者は、このアスクレピオス勧請碑文の全文を引用し、検討を加えています。
それによると、アスクレピオスのアテネ市内への勧請の年代は、「ニキアスの平和」の後の前421/0年、エレウシス秘儀大祭に合わせて、神事が執り行われています。
注目されるのは、この勧請がエレウシス秘儀神官のバックアップを受けての、テレマコスという一アテネ市民の「私的」な行為であった点です。
さらに、アスクレピオスは、アテネ市内に勧請される以前に、ペイライエウスのゼア地区に既に勧請されていたこと、そして、アテネ市内への勧請の翌年度(前420/19年)には、アスクレピオスの聖所全体の落成がなされていることが明らかにされています。
次に、復元された「アスクレピオス勧請記念碑」に描かれた「勧請縁起」のレリーフについての解説がなされています。
復元見取り図(アスクレピオス、娘ヒュギエイア、テレマコス)の解読に続いて、「裏面レリーフ」に描かれた「こうのとり(ペラルゴス)」の意味について、それがアクロポリス南麓の「ペラルギコン」そのものであると指摘しています。
ペロポネソス戦争時の、ペリクレスの籠城作戦は、アテネ市内に「ペスト」の蔓延をもたらしました。
著者は、悪疫流行とアスクレピオス信仰の接点について論じています。
アテネの災害・惨状は、ギリシア諸国の人々に衝撃を与え、彼らの心を「医神アスクレピオス」に向かわせて、それが前4世紀の聖地エピダウロスの発展につながったと推定しています。
しかし、アテネの悪疫駆除については、アスクレピオスではなく、その父神アポロンに祈願したこと、国家の名で「平癒感謝」の奉納がおこなわれたことを指摘しています。
次に、喜劇『福の神』に見る「癒し」が取り上げられています。
そこでの癒しの場面には、具体的に神聖な蛇の治癒が描かれています。
そして、注目に値するのは、そのアスクレピオス神殿は、アテネ市内の神殿ではなく、ペイライエウスの神殿でした。
最後に、著者はペイライエウス聖所の遺構から発見された平癒感謝のレリーフの「絵馬」の解説を行い、民会決議の碑文から、このペイライエウスのアスクレピオスの聖所が、設立当初からアテネ国家の管理下に置かれていた「国営」の聖所であったことを明らかにしています。
第6章 アテネ市内アスクレピオス神殿の「国営化」と「奉納品明細」の碑文
はじめに、「奉納銘」の表現形式について、考察がなされています。
ペルガモン出土の奉納品とアテネの「市内アスクレピオス神殿」に捧げられた奉納品の比較検討から、ローマ帝政期の2/3世紀には、「祈り(エウケー)を奉納した」という表現形式が取られ、著者はエウケーを「奉納品(タマ)」そのものを指していると解釈しています。
そして、前4世紀には、「エウクサメネス(祈願して)」という表現形式が取られていたことを指摘しています。
次に、セイラ・アイリシャ女史の『アテネ市内のアスクレピオス神殿参詣人と奉納品および明細表』の業績に依拠して、市内アスクレピオス神殿の「奉納品明細」表の検討に取りかかります。
「奉納品明細表」の「頭書き」から、この明細表が民会決議の「議事録」の一部をなしていたこと、すなわち、奉納品に対する「国家管理」の実態を明らかにしています。
著者は、「奉納品明細書」碑文の出現そのものが、同神殿がアテネ国家の管理下に置かれ、従来は私的性格にとどまっていた祭祀が、「国家的祭祀」の枠組みに取り込まれたこと、換言すれば、体よく国家に「吸収」されて「国営化」されてしまったことを裏書きしていると指摘しています。
さらに、奉納品自体の「素材」に注目すると、表1〜表5にいたるまで、金銀製品・宝石類がずらりと記録されており、前3世紀末以前の段階では、アテネ市民の少なくとも上流階層の間では、かなりの「経済的余裕」があったと推測しています。
著者は、アリシャ女史の補填に依拠しつつ、碑文「表2」の全体を試訳しています。それによると、碑文は、奉納品全体ではなく、「黄金製奉納品」に焦点を絞って、年度順に、「黄金製」・「銀製」・「青銅製」に仕分けされた上で列挙されています。
最後に、古代タマの分析がなされています。
碑文に現れる、「古代タマ」は多種多様で、人体の部位が数多く上がっています。
特に、注目されるのは、「目」のタマが断然群を抜いていることです。
実数総計(566個)のうち、290個(51.2%)を占めています。
ただし、著者は、この点に関し、「目の癒し」という「平癒祈願」の要件に加えて、「魔術・呪詛」との関わりを想定しています。
古代について、「目の癒し」が専門という「癒しの神・半神」は見つからない。
アポロン神にせよ、アスクレピオスその他の半神たちにしても、身体の部位を象った奉納品「古代タマ」の出土状況から推測して、古代の「癒し手」はレパートリーの広い「万能医」であったと結論づけています。
第7章 アスクレピオス祭祀の広がりーギリシア本土、クレタ島、コス島、ペルガモン
本章では、アスクレピオスの祭祀のアテネ以外の主な事例を紹介しています。
著者は、ここで取り上げられるアスクレピオスの聖所を、精力的に現地踏査して、パウサニアスの記述を中心に、解説しています。
まず、著者はアスクレピオス祭祀を、テッサリア地方の「トリッカ系」と「エピダウロス系」の、少なくとも二系列に仕分けするのが正しいと指摘しています。そして、コリントから話を始めています。
コリント・アスクレピオス聖所では、先行する「アポロン神殿」を包摂する形で「アスクレピオス神殿」が造営されたことを確認し、前4世紀末までには、旧来のアポロンの「癒し」がアスクレピオスの「癒し」に取って代わったことを実証しています。
そして、アスクレピオス神殿の「お籠り堂(アバトン)」や「レルナの泉場」の解説がなされています。
次に、同じくパウサニアスの記述に従って、ペロポネソス半島のシキュオン領に属する聖地ティタネと中部ギリシア・フォキス地方のティトレアの紹介が続きます。
ティタネでは、地元の半神アレクサノルとエウアメリオンが、新しい半神アスクレピオスに取って代わられていること、その時期は前5世紀末から前4世紀にかけての時期を想定しています。
ティトレアでは、アスクレピオスの聖所は未発見で、その場所も特定されていません。
さらに、ペロポネソス半島のアスクレピオス祭祀の既観がなされています。
著者は、アルカディア地方のアスクレピオスの聖所に注目し、パウサニアスの「幼児アスクレピオス祭祀」の記述から、先に挙げた「トリッカ系」や「エピダウロス系」とは異なった別系統の「アルカディア系」の「アスクレピオス祭祀」を想定しています。
次に、クレタ島レベナの聖所が紹介されています。
この癒しの聖所も、先行の「妖精と河神アケロオス」の祭祀を、前4世紀に「医神アスクレピオス」が「乗っ取った」ことが推測されています。
そして、この古代聖所が廃墟となった後の5世紀末/6世紀初め頃、境内の北東隅に、バシリカ様式の大型の教会堂が建立されています。
著者は、この事実を、古代的な「癒しの信仰」の継承を示唆する状況証拠として、注目しています。
コス島のアスクレピオス聖所について、著者は、アスクレピアダイ(アスクレピオス一門)と称する、「癒し手=医師」の存在から話を始めています。
そして、「医学の父」ヒッポクラテスもその一員であったこと、彼の時代のアスクレピオス神殿は、「イストモスに在すアスクレピオス」であり、私的祭祀であり、トリッカ系であったと推定しています。
そして、イストモスのアスクレピオス祭祀は、前4世紀の半ばごろ、新設都市コス近郊の聖地に「分祀・株分け」され、前3世紀には壮大なアスクレピオス聖所が現出すると指摘しています。
著者は、そのコス島の首都近郊に勧請されたアスクレピオスの祭祀が、アポロン・キュバリシオスとの合祀という形を取っているにせよ、その祭祀が従来の私的性格を脱却して、国家的祭祀に変容しているという事実を重要視しています。
そして、この聖地は、前述したように前3世紀以降、大発展をとげるのですが、それは、「医神アスクレピオスの聖所」としての整備・拡充であって、アポロン・キュバリシオス祭祀の縮小傾向は歴然たるものであり、コリントや聖地エピダウロスで検証された「オリンポス神」アポロンから「医神アスクレピオス」への「主役交代」が、コスの聖所でもくり返されていると指摘しています。
最終的に、ユスティニアヌス帝時代の、551年に生じた地震災害が、コス市の壊滅に伴うアスクレピオスの祭祀の終焉を決定づけたと推定しています。
次に、ペルガモンのアスクレピオス祭祀について述べられています。
ペルガモンのアスクレピオス勧請が、国家によるものではなく、一個人アルキアスの私的な勧請であったこと、「エピダウロス系」であったことが明らかになっています。
そして、ペルガモンでも、古参の半神テレフォスを祀る「半神祭祀」が守られていたところへ、新参のアスクレピオスが登場して、その地位と役割を「乗っ取った」ことが推測されています。
さらに、前3世紀後半のアッタロス1世の治世には、アスクレピオス祭祀の国家的祭祀への「昇格」(国営化)が実現していたこと、そして、聖所の神官職の勧請者アルキアス一門の世襲が公認されたこと、が論じられています。
ペルガモンのアスクレピオス神学について考察されています。
新祭神「ゼウス・アスクレピオス」、「ゼウス・ソーテール(救済者)・アスクレピオス」の事例の分析を通して、上昇ムードにある「アスクレピオス」と下降ムードの「ゼウス」の両者の結びつきを想定しています。
そして、ペルガモンのアスクレピオスの祭祀も、コス島と同様、3世紀の半ばに地震災害の影響を受けて「消滅」してしまったと結論づけています。
癒しの神「ゼウス」の古代タマの奉納銘については、「ゼウス・アスクレピオス」の称号に含まれていたゼウスの名で、「医神アスクレピオス」の評判・名声のおかげで「名誉回復」の機会を得たと推測しています。
最後に、「お籠り」の手続きを規定したペルガモン聖法の断片が訳出されており、そこでの白い雄鶏の祓い清めは、前述のソクラテスの最後の言葉を想起させます。そして、「癒しの事績」が3例挙げられています。
第8章 古代文化遺産とキリスト教
「癒しの民間信仰」の基盤は、「現在を生き抜く」意志、「生への執念」に他ならないが、「癒し」の最終目的は「天国」の安らぎでしょう。
著者は、「天国」という言葉から、考察を始めています。
それが、キリスト教の「用語」と見なされていること、そして、初期キリスト教時代の2/3世紀頃には、「パラディソス」=「天国」との見方が固まったと推測しています。
そして、「天国」の観念は、古代ギリシア人と無縁であったかと問うています。
著者は、アテネ戦没者国葬墓の墓碑銘を皮切りに、古代ギリシア人の墓碑銘一般を通してうかがえる彼らの「天国」観を追っています。
そこでは、アテネにおける戦没者の「英霊化」がなされており、霊魂は「天上の霊気(アイテール)」に受けいれられていますが、前4世紀半ばには、霊魂の「天上界」行きが一般人まで開放されています。
キリスト教自前のものと思われがちな「天国」観について、実は前5世紀以降の古代ギリシアの「来生観」・「宇宙観」が大きく貢献していることを墓碑銘の分析を通して指摘しています。
次に、アスクレピオス祭祀とキリスト教との「近似」と「対立」の中に、「癒しの民間信仰」の、ギリシア人世界における「古代」から「中世ビザンツ」・「現代」への「連続性」への問題に迫っています。
すなわち、「古代タマ」奉納の習俗が、「キリスト教化」の大波を乗り越えてビザンツ時代、そして現代に受け継がれた背景にはどのような宗教的・文化的事情が存在したかを問うています。
著者は、新プラトン主義哲学の拠点「アテネの学園アカデメイア」の身近な存在が、アテネ市内のアスクレピオス神殿にとって有利に働き、長期存続につながったこと、「タマ奉納」の習俗に見て取れる「古代と現代」の連続性の根本には、「学園都市」という土地柄と「新プラトン主義哲学」の教説という二つの要素が重なり合って、「アスクレピオス祭祀」の維持存続に決定的に重要な役割を演じていたと論じています。
そして、「タマ奉納」という古代的習俗が、「キリスト教時代」の中世ビザンツ世界、そして現代ギリシアに「連続」したという事実に関する限りは、アテネ市内アスクレピオス神殿が、「キリスト教」との相克の中で果たした役割が断然大きく、後続世代への古代的習俗の「引き継ぎ」とその「普及」に貢献したのではないかと考えています。
古代ギリシア語と教会用語について、ギリシア「古代文化」と「キリスト教文化」との間の、受容と継承を含む「重なりぐあい」を検証しています。
古代ギリシア語の「エクレシア(民会)」と教会「エクリシア」、古代ギリシア語のレイトゥルギア(公共奉仕)」と教会用語「リトゥルギア(礼拝)」について、前者は「召集」をかける主体の「政治当局」から「神」への基軸の転換が基盤となっていること、後者は、奉仕の対象が「大衆(ラオス)」から「神(テオス)」にすり変っていること、すなわち、視点の基軸の転換によって、古代ギリシア語がもとの綴りのまま「キリスト教化」を実現し、後代へ生き延びたと論じています。
古代ギリシア語のキリスト教化については、さらに、ビザンツ教会堂壁画絵師の職業名「ヒストリオグラフォス」について触れられており、次いで、「キリスト再臨図」における風神ボレアスの変容が述べられています。
古代神ゼウスと予言者エリヤ(プロフィティス・イリアス)の関係について、論じられています。
キリスト教時代の到来とともに「古代神」ゼウスは死んで姿を消し、「旧約聖書」の一人であった予言者エリヤは「聖予言者(アヨス・プロフィティス)イリアス」という名の聖人としてギリシアの土壌に再生しました。
しかし、著者は、「慈雨をもたらす」という機能・役割において、顕著な「共通性」を認め、「先行者」・「後継者」の関係を見て取っています。
カザンザキスの『キリストはふたたび十字架に』を引用しながら、聖人プロフィティス・イリアスが、「癒しの聖人」であったことが述べられています。
そして、「雲を集め、雨を降らせる」という点で古代神ゼウスと予言者イリアスはイメージにぴったり重なり合うことから、山岳名の「オリュンポス」がキリスト教時代の「プロフィティス・イリアス」に席を譲ったと推測しています。
さらに、著者は、古代とともに死んだはずの古代神ゼウスについては、前述したように「アスクレピオス祭祀」に便乗する形で、「癒しの神」として機能しており、キリスト教の聖人プロフィティス・イリアスの中にとけ込む形で存続していると考えています。
次に、「癒しの聖人」たちが挙げられています。
特に聖女(アヤ)パラスケヴィーとキプロス島の聖ランバディスティス修道院が紹介されています。
「魚(イクテユス)」の表象とふたりの「ソーテール」—キリストとアスクレピオスの関係の検証が続きます。まず、イクテユスの呼び名の説明、そしてその表象は2世紀後半にさかのぼることが述べられ、キリストの添え名「ソーテール」について検証されています。
そして、イエス・キリストに添えられた「救済者(ソーテール)」の称号は、ペルガモンの医神アスクレピオスがその前例となって、影響を及ぼしたことを想定しています。
次に、キプロス島のクーリオン遺跡の「エウストリオスの家」が紹介されています。
この建物は、中庭周縁に方やフォイボス・アポロン、方やキリストという「異質の神」に言及する二種類の碑文が同時並存しています。
著者は、「古代神」アポロンから「現代神」キリストへの「鞍替え」のイメージを想定し、「キリストの表象」は「魔除け」の「おまじない」にほかならないと考えています。
「現世利益」の「効率」ゆえに、「キリストの表象」が屋内装飾に「活用」されている現実は、一般民衆の「キリスト教信仰生活」の日常生活レベルにおける「信心」の実相を映し出していると見て取っています。
最後に、著者がオルコメノスの町のスクリプゥ聖母永眠教会堂で体験した「現代史的」なイコン(ドイツ軍撃退の聖母)との出会いが紹介されて、本章は閉じられています。
終章 「古代VS現代」の相克—ギリシア民族呼称の「継承・断絶」と復活
本章では、副題のギリシア民族呼称について考察がなされています。
はじめに、古代民族呼称の否定と消滅が述べられています。
「ギリシア」という言葉の源は、ラテン語の「グラキア」であり、古代ギリシア語の地名は「ヘラス」、ギリシア人の呼称は「ヘレネス」でした。
現行では、ギリシア語表記は同じで、発音はエリネス。(著者は、本書では「ヘレネス/エリネス」と表記)
そして、この民族的呼称は、古代から現代まで一貫して守り通したのではなく、途中で消滅し、19世紀初めのギリシア独立戦争とともに「復活」したと述べています。
著者は、この古代的民族的呼称「ヘレネス」の否定、その過程の進展の度合いを史料に基づいて把握するという基礎作業から始めています。
アンネ・コムネナの場合(12世紀半ば)。
「ビザンツ帝国」は「ローマ人の帝国」と呼ばれ、ギリシアの本土の住民を含めて、ビザンツ帝国の支配下にあるものは一括して「ローマ人」(=ロメイ)と呼ばれています。しかし、彼女はこれと並行して、ギリシア人の古代的民族呼称である「ヘレネス/エリネス」の語も使用しています。著者は、彼女の意識においては、ギリシアの「古代」と「現在」は連続していて、「古代ギリシア人」と「現代ギリシア人」との仕切り壁など存在していないと述べています。
『モレア年代記』の場合(14世紀半ば。モレアは、中世ビザンツ時代のペロポネソス半島の呼称)。
「ヘレネス/エリネス」は「ローマ人」の呼称をローマからもぎ取ったとして、「ヘレネス/エリネス」の存在そのものを抹殺するわけではなく、キリスト教徒の「ローマイオイ/ロメイ」として扱っています。
現在は「ロメイオイ/ロメイ」と呼ばれる元「ヘレネス/エリネス民族」の存在は当然の歴史的前提として捉えられています。
詩人ゲオルギラスの場合(15世紀半ば)。
「ヘレネス/エリネス」という言葉は、一度も使われていません。
著者は、同時代の最高の知識人ゲンナディオスが「ヘレネス/エリネス」の呼び名をかたくなに忌避したように、彼もその名を意識的に避けたと推測しています。
そして、「グライコイ/グレキ」という呼称が、「ヘレネス/エリネス」の代わりに登場していることを述べ、宗教がらみのないニュートラルな言葉であったと推測しています。
「嘘新聞」の場合。(1821年独立戦争勃発当初。「嘘新聞」は、手書きのガラクシディオン新聞)
ギリシア人独立戦争勃発当初の段階では、ギリシア本土の住民は、現代ギリシア語の発音で「ロメイ」と呼び慣らされています。著者は、これが近世ギリシア人の「民族呼称」と見なしています。
こうした「ヘレネス」否定の背景として、著者は、オスマン・トルコの台頭と、ビザンツ帝国の衰退、これがギリシア人の民族呼称の歴史において、決定的なターニング・ポイントになったと論じています。
帝国崩壊の危機が迫る頃から、「ヘレネス/エリネス」離れの傾向が表面化して、ついにこの古代的民族呼称は姿を消し、「グライコイ/グレキ」の語が、現代ギリシア人の呼称に起用される。
そして、さらにビザンツ帝国滅亡後の「トルコ支配」の時代には、「帝国の夢」覚めやらぬギリシア人が、むしろ進んで「ロメイ」の呼称を自らの「民族呼称」とみなすに至った。
著者は以上のように推測しています。
次に、著者はギリシア国立銀行刊行の『近代ギリシア民間伝承における古代ギリシア人』に収録されている伝承の紹介に移ります。
まず、具体的事例の紹介に入る前に、著者は「ヘレネス伝承」全体の底にある「共通項」を指摘しています。
それは、語り手たちの語る最も重要な点は、古代ギリシア人の「ヘレネス」は過去の人類であって、語り手である自分たちギリシア人との間には何の血縁関係も存在しないという点です。
この点を確認して、民間伝承の具体的例に移ります。
ヘレネス巨人伝説。民間伝承によれば、パルテノンの階段の高い段差から、あるいは、ナクソス島の巨大なクーロス像などから、「巨人伝説」が生まれています。
古代ギリシアの理想化とミロルドス伝説が続きます。
「古代ギリシアの発見」に道を開いたのは、ドイツ人美術史家ヨーハン・J・ヴィンケルマンで、「古代ギリシア美」を絶対化して、西欧人の心を「古代ギリシアの理想化」に駆り立てました。
そして、「古代ギリシア」に憧れ、「古代の遺物」を持ち帰ろうとしてギリシアを訪れる男のことを、現地のギリシア人は「ミルドス(旦那様)」と呼びました。
エルギン卿が代表格でしょう。
興味深いことは、彼らは、西欧の地から古代の宝物を捜しにやって来る「ミロルドス連中」こそが、「古代へレネス」直系の子孫だと理解していた点です。
「古代復活」は、ギリシア独立戦争進行中のメソロンギオン市(イギリスのロマン派詩人バイロン死没の地)議会布告に見られます。
布告の第4項では、義務不履行者を「身分詐称」の「非エリネス」=「非ギリシア人」と決めつけています。
「ヘレネス/エリネス」が現代ギリシア人の確固たる「民族呼称」として復活しています。
次に、著者はコロイスの「軍歌」を検証します。
そこでは、「現代ギリシア人」の呼称が「グレキ」一本に絞られていて、「ロメイ」を完全に排除している点が、注目に値します。
さらに、著者は「1821年軍歌集」の検討に入ります。そこでは、「ロメイ」の使用例は一例もないのに対して、「グレキ」と「エリネス」の使用例はひんぱんで、さらに、コライスが「愛用」した民族呼称「グレキ」は古代的民族呼称の「エリネス」に取って代わられています。
興味深いのは、「軍歌12番」です。
ここでは、ゼウスを筆頭に古代神の名前が復活しています。キリスト教の時代になっても、ギリシアという土壌においては、「古代神の世界」は完全には消滅しきれず、時と場合によっては、堂々と「復活」して、立ち現れることを示しています。
ギリシア独立戦争の進展とともに、新聞紙上からは、「現代ギリシア人」指す呼称は「エリネス」以外のすべてが姿を消します。
1833年に誕生した「ギリシア王国」の正式の名称は、「エリネスの王国(ギリシア人の王国の意味)」であり、「エリネス」という民族呼称を正式に復活させて、「国名」としました。
自分たちは、「古代ギリシア人ヘレネス」とはなんの所縁もないとしていた「ロメイ」や「グレキ」、つい先日まで「古代へレネス巨人伝説」を語っていた同じ現代ギリシア人が、「古代ヘレネス」を自分たち直系の栄光ある祖先であるとみなし、同じ綴りの「エリネス」を自分たちの「民族呼称」としたわけです。
著者は、ギリシア独立戦争は、現代ギリシア人の「歴史と民族の発見」に決定的役割を演じたと評価しています。
最後に、著者のギリシア人の「民族呼称」の問題に取り組む、思いが語られています。以下、著者の文章を引用します。
“この問題は、私の心の中で、常に「日本」と「日本人」の問題にはね返ってくる。「大東亜戦争」突入から、「鬼畜米兵」を叫ぶさなかに味わった「敗戦」を経たかと思うと、手のひらを返したような「対米追随ムード」まっ盛りのなかで、「対テロ戦争」を錦の御旗に、いまふたたび「大和魂」の雄叫びを耳にしかねない状況が生まれつつある。”
“「日本人の節操」とは一体何なのか、「歴史」に何を学ぼうとするのか、そのあたりの「曖昧模糊」たるところが私を不安にかり立て、そのような「不安の意識」が下敷きとなって、「ギリシア民族呼称」の歴史の追跡に向かわせる。”
“「大東亜戦争」の戦時下、「牧師の息子」として、軍国主義「日本」の、いわば、「公認」の「いじめ」にさらされた、「少年の日々」は、私にとっては「失われた時」であるが、その「失われた時」の挽回にとって、「ギリシア人独立戦争」前後の「ギリシア民族呼称」の問題を浮彫りにする作業は決定的に重要な意味を持つものであった。”
おわりに
本書の図版については、大半は1972年春以降、2001年春にかけて実際にその現場を歩き、著者が撮り集めたものである、という言及があります。
現場踏査については、本文中でも触れましたが、そのギリシアにかける情熱は、本当に頭が下がります。
そして、「はじめ」にもありましたが、著者は、旅行などでの奥様の協力に感謝し、本書はまさしく「馬場ファミリー」の汗と埃の成果であると述べています。
最後になりましたが、著者は、今年(2010年)5月3日に腎がんで逝去されました。
享年77歳。
本書は遺作となります。
告別式での奥様のお話では、死ぬ前まで、本当に24時間机に向かって、最後の仕事をしていたとのことです。
その仕事を、結局、我々は見ることはできないのですが。ここに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。