原風景「有明浜からの瀬戸の夕日」

たまたま、FBで見つけました。
この絵を描かれた画家の狩野裕子さんは、私の高校の後輩で、ふるさとの「三豊百景」を描かれています。
(旧三豊郡は、現在の香川県三豊市と観音寺市にあたります)
「有明浜からの瀬戸の夕日」は、その第100番目の作品です。
この海岸は、私の高校に近く、放課後などは友人達とよく夕日を見に行ったものです。
ちなみに、HP「世界史を読む」の写真は、この有明浜からのものです。
「堅円浄滑(けんえんじょうかつ) 一星(いっせい) 流(なが)る」魚玄機(唐)
打球作(だきゅうのさく) (七言律詩)
堅円浄滑一星流。 月杖争敲未擬休。
無滞礙時従撥弄。 有遮欄処任鉤留。
不辞宛転長随手。 却恐相将不倒頭。
畢竟入門応始了。 願君争取最前籌。
堅円浄滑(けんえんじょうかつ) 一星(いっせい) 流(なが)る
月杖(げつじょう)争(あらそ)い敲(たた)き 未(いま)だ休(や)めんと擬(ほっ)せず
滞礙(たいがい)する時(とき)無(な)く 撥弄(はつろう)に従(したが)う
遮欄(しゃらん)する処(ところ)有(あ)りて 鉤留(こうりゅう)に任(まか)す
宛転(えんてん)して 長(なが)く手(て)に随(したがう)を辞(じ)せず
却(かえ)って恐(おそ)る 相(あ)い将(ひき)いて頭(とう)に到(いた)らざるを
畢竟(ひっきょう) 門に入(い)り 応(まさ)に始(はじ)めて了(おわ)るべし
願(ねが)わくは君(きみ) 争(あらそ)い取(と)るべし 最前籌(さいぜんちゅう)
硬くて丸くつやつやした球(ボール)が、星のように流れ飛ぶ。
きそって月杖(スティック)で球を打ち、休もうとしない。
球はとまっていることなく、打たれはじかれるまま動きまわるが、
柵があるので、おのずととまって外へは出ない。
ころがしながら、長く手元に置くのはかまわないけれど、
逆に打ち合いをして、球のそばに行けないのが問題だ。
けっきょく球が門(ゴール)に入ってはじめて勝負がつく。
あなた、がんばって最高得点をあげてね。
(井波律子『中国名詩集』岩波書店(2010)より)
(2018. 4. 7)
論文「宮沢賢治「永訣の朝」におけるいくつかの問題点」
宮沢賢治 「永訣の朝」(『心象スケッチ 春と修羅』より)
永訣の朝
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(*あめゆじゆとてちてけんじや)
うすあかくいつそう陰惨いんざんな雲から
みぞれはびちよびちよふつてくる
(あめゆじゆとてちてけんじや)
青い蓴菜じゆんさいのもやうのついた
これらふたつのかけた陶椀たうわんに
おまへがたべるあめゆきをとらうとして
わたくしはまがつたてつぱうだまのやうに
このくらいみぞれのなかに飛びだした
(あめゆじゆとてちてけんじや)
蒼鉛さうえんいろの暗い雲から
みぞれはびちよびちよ沈んでくる
ああとし子
死ぬといふいまごろになつて
わたくしをいつしやうあかるくするために
こんなさつぱりした雪のひとわんを
おまへはわたくしにたのんだのだ
ありがたうわたくしのけなげないもうとよ
わたくしもまつすぐにすすんでいくから
(あめゆじゆとてちてけんじや)
はげしいはげしい熱やあへぎのあひだから
おまへはわたくしにたのんだのだ
銀河や太陽 気圏などとよばれたせかいの
そらからおちた雪のさいごのひとわんを……
……ふたきれのみかげせきざいに
みぞれはさびしくたまつてゐる
わたくしはそのうへにあぶなくたち
雪と水とのまつしろな二相系にさうけいをたもち
すきとほるつめたい雫にみちた
このつややかな松のえだから
わたくしのやさしいいもうとの
さいごのたべものをもらつていかう
わたしたちがいつしよにそだつてきたあひだ
みなれたちやわんのこの藍のもやうにも
もうけふおまへはわかれてしまふ
(*Ora Orade Shitori egumo)
ほんたうにけふおまへはわかれてしまふ
あああのとざされた病室の
くらいびやうぶやかやのなかに
やさしくあをじろく燃えてゐる
わたくしのけなげないもうとよ
この雪はどこをえらばうにも
あんまりどこもまつしろなのだ
あんなおそろしいみだれたそらから
このうつくしい雪がきたのだ
(*うまれでくるたて
こんどはこたにわりやのごとばかりで
くるしまなあよにうまれてくる)
おまへがたべるこのふたわんのゆきに
わたくしはいまこころからいのる
どうかこれが天上のアイスクリームになつて
おまへとみんなとに聖い資糧をもたらすやうに
わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ
((一九二二、一一、二七))
註
*あめゆきとつてきてください
*あたしはあたしでひとりいきます
*またひとにうまれてくるときは
こんなにじぶんのことばかりで
くるしまないやうにうまれてきます
論者はこの論文で、文学作品の読み方指導としての「疑問法」という方法を踏襲して、本作品の疑問点をいくつか挙げ、先行研究を踏まえて、その問題を解決することでより深い解釈を得ようとしています。
その疑問点は、以下の3点です。
1. なぜ「わたくし」は陶椀を「ふたつ」もっていったのか。
2. なぜ妹の頼みが「わたくしをいっしょうあかるくするのか」。
3. なぜ、「Ora Orade Shitori egumo」だけがローマ字表記なのか。
ここでは、この問題に深く立ち入ることはできませんが、宮沢賢治の「永訣の朝」の多くの研究者の議論(先行研究)や、論者の解釈(結論の一部分を抜き出しますと、1については兄弟「ふたり」が「いっしょにそだってきた」からに他ならないこと(p.181)。2については、法華経信者の賢治にとって、妹トシが「信仰を一つにするたったひとりのみちづれ」(「無声慟哭」)であったこと(p.185)。3については、妹のこの言葉に接した時点での「わたくし」の衝撃が、違和感のあるローマ字表記に残されていること(p.189)。)などは、この詩をより深く理解する手がかりを与えてくれます。
この論文を読んで、「詩」は、今まで感性で読むものと考えていましたが、「詩」を教える側からの視点で分析する方法は、興味深く勉強になりました。
なお、現在初版本と宮沢家所蔵本手入れテキストが一般に流布しているようですが、論者は読み手の理解しやすさ、納得のしやすさを考慮して、教材としては初版本を選んでいます。
両者のテキストの違いは末尾にあり、初版テキストでは/どうかこれが天上のアイスクリームになって/の箇所が、宮沢家所蔵本では、/どうかこれが兜卒の天の食に変わって/と手入れされています。
菅原誠「宮沢賢治「永訣の朝」におけるいくつかの問題点:教材化のための作品研究の試み」『教授学の探求』第16号 1999年 175−191
(2018.2. 10)
クリオ(歴史の女神)の顔
クリオ(ギリシア語でクレイオ)は、ギリシア神話のゼウスとムネモシュネ(「記憶」の意)の九人の娘(ミューズ:ギリシア語でムーサ)の一人です。
ミューズ(ムーサ:複数ムーサイ)は、詩、音楽、舞踏、文学を司る女神であり、後に哲学、歴史なども司るとされました。
ギリシア語で、この言葉のもとの意味は「注意深き者」であって、歌や文芸一般の創造を注意深く守り育てることをさしていました。
クリオ(クレイオ)は、「祝福する女」の意で、ギリシア語のクレイオー(祝福する)に由来しています。
彼女は、九人の女神の中では、「歴史」の役割を担当し、(女神たちの役割が細分化されたのは、ローマ時代の後期からです。)姉妹のなかでは一番内気で、彼女の顔は時にほんの一部しか表されません。
歴史家E.H.ノーマンの『クリオの顔ー歴史随想集』から、私にとって興味深かった一文を紹介します。
「勇敢な行動、軍隊の進撃と対抗、政治家の演説などは、どういうものかクリオの心を動かさない。
彼女を感動させると思われるのは、おのおの自分の尊さに無自覚でありながら文化財の創造に貢献する人民の勤勉な努力であり、人間的愛情の伝統を注意深く守る人、また何らかの忘れられた自由を甦らせる人々である。
恐らくクリオに対して人が加えうる最大の冒瀆は、歴史を機械的で陳腐な常套句の連続に変えること、例えば、ある伝統なり制度なりに、「封建的」というようなレッテルを貼り付けてそれを無価値なものと片付けてしまうことである
(中略)
クリオは大変内気で謙遜な娘でありながら、きわめて仕えにくい主人である。
しかも彼女は気取り屋である。
彼女は、扇動的な新聞やデマゴーグがまき散らす劣悪な通貨である常套語や符牒に理解力を曇らされないきわめて平凡な市民にも、また人間の作った制度はいずれも不変なものでなく社会全般および他の制度にとって相対的なものであって、たえまない歴史の大きな運動そのものの一部として、微妙に変化し変質するものであると見ることを学んだ学徒にも、ひとしく彼女の愛らしくも物思わしげな顔を現すであろう。(72頁)」
「クリオの顔」と題された論文は、「解説」によれば、『世界』1950年1月号に発表された書き下ろしの論文です。
「歴史に謙遜に学ぶことで偏見から解放されたものには、クリオはその素顔を見せるという」(203頁)ことのようです。
(E.H.ノーマン著/大窪訳『クリオの顔 ー歴史随想集』岩波文庫(1986)から)
(2016. 9/ 5)
「ストゥディウム」と「プンクトゥム」
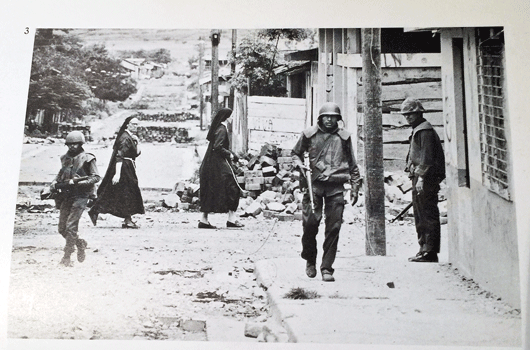
ロラン・バルトの写真論から。
彼が上記写真(ニカラグアの反乱)の中に見いだした、「ストゥディウム」と「プンクトゥム」の二つの要素について。
第一の要素「ストゥディウム」とは、ラテン語のstudium(studyの語源)という語です。
この語は、ただちに「勉学」を意味するのではなく、あるものに心を傾けること、ある人に対する好み、ある種の一般的な思い入れを意味しています。
例えば、この写真では、反乱とニカラグアとそしてこの二つに関するあらゆる記号、貧しい私服の戦闘員たち、廃墟と化した街路、死者たち、苦悩、太陽、重たそうなまぶたをしたインディオたちの眼などは、ある典型的な情報に関係しています。
彼は、そうした写真に対して一種の一般的関心、ときには感動に満ちた関心を抱くことができるが、その感動は、道徳的、政治的な教養「文化」という合理的な仲介物を仲立ちにしていると述べます。
彼が多くの写真に関心を抱き、それを政治的証言として受けとめたり、見事な歴史的画面として味わったりするのは、そうしたストゥディウム(一般的関心)によるのであり、人物像に、表情に、背景に、行為に共感するのは、教養文化を通してだからと。
それに対して第二の要素「プンクトゥム」は、ストゥディウムを破壊(または分断)しにやって来るものと説明されます。
それは、彼の方からそれを求めていくのではなく、写真の場面から、矢のように発し、向こうから彼を刺し貫きにやって来るものです。
ここで問題になっている写真には、あたかもそうした感じやすい痛点のようなものがあり、問題の標識(しるし)や傷は、まさしく点の形をしており、それゆえ、彼はストゥディウムの場をかき乱しにやってくるこの第二の要素を、「プンクトゥム」(ラテン語のpunctum:突くこと、刺すこと、点、小斑点などの意味)と呼んでいます。
すなわち、「プンクトゥム」とは、刺し傷、小さな穴、小さな斑点、小さな裂け目のことであり、ある写真のプンクトゥムとは、その写真のうちにあって、彼を突き刺す偶然なのです。
(ロラン・バルト/花輪光訳『明るい部屋ー写真についての覚え書きー』みすず書房、1985年6月刊(1997年6月新装第1刷)、37−39頁より)
追記:二重性
この写真でバルトが注意を引かれたのは、二つの要素、つまり兵士と修道女が共存していることから来ています。
少し長いですが、彼の文章を引用してみます。
「一枚の写真が私の注意を引いた。とくに変わったところがあったわけではない。それはニカラグアの反乱を撮った(写真としては)平凡な場景である。廃墟と化した街路、ヘルメットをかぶった二人の兵士がパトロールをしている。そのうしろを二人の修道女が通り過ぎてゆく。この写真が私の気に入ったとか、関心を引いたとか、好奇心をそそったとかいうのではない。ただ、この写真は(私にとっては)存在していた。その存在(その≪冒険=不意の到来≪)は、二つの要素、つまり兵士と修道女が共存していることから来る、ということを私はとっさに理解した。この二つの要素は、同じ世界に属していないという意味では、不連続であり異質である。……」(34−35頁)
彼は、ここに構造的規則が存在するのではないかと感じ、その規則性を確かめるために他の写真を検討し、彼の規則が正確に働いていることを確認します。
つまり、素晴らしい写真ではあるが、彼にとって何の標識(しるし)も含まれていない、それらの写真の均質性が文化的なものにとどまっているもの(「ストゥディウム」)、と不意の到来・彼を突き刺す偶然(「プンクトゥム」)の二つの要素の存在を。
(2016. 7. 17)
ホセ・ムヒカ氏(元ウルグアイ大統領)の言葉
2012年6月にブラシルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連会議でのスピーチが世界中の人々を感動させて、一躍時の人となったホセ・ムヒカ氏。
2016年4月、来日して話題となりました。
以下、重複していますが、彼の言葉を集めてみました。
「私は貧乏ではない。質素なだけです。」
(中東の衛星テレビ局Aljazeera製作番組『Talk to Aljazeera』より)
「貧乏とは、欲が多すぎて満足できない人の事です。」
(Chilevision製作番組『el que no conocias』より)
「私は、持っているもので贅沢に暮らすことが出来ます。」
(2012年11月15日付 BBCニュースマガジンより)
「質素は“自由のため”の戦いです。」
(2012年11月15日BBCスペイン語版より)
「物であふれることが自由なのではなく、時間であふれることこそ自由なのです。
(ベネズエラのテレビ局Venezolana de Television製作番組『La Hojilla』より)
「人間のもっとも大事なものが、“生きる時間”だとしたら、この消費主義社会は、そのもっとも大事なものを奪っているのですよ。」
(同上。『La Hojolla』より)
「物を持つことで人生を複雑にするより、私には好きなことができる自由な時間のほうが大切です。」
(『SALVADOS』より)
「孤独は多分、死の次に最も悪いことです。しかし、私はその経験と時代を生きたからこそ、今があります。」
(同上。『SALVADOS』より)
※ ホセ・ムヒカは、青年時代、極左武装組織に参加し、ゲリラ活動に従事するが逮捕され、約13年間の苛酷な獄中生活を送りました。
「お金があまりに好きな人たちは、政治の世界から出て行ってもらう必要があります。」
(2014年10月22日付 CNNスペイン語版より)
※ 最近の日本の政治家(特に今話題の桝添都知事など)に聞かせたい言葉です。
「人生ではいろいろなことで何千回と転びます。愛で転び、仕事で転び、今考えているその冒険でも転び、実現させようとしている夢でも転びます。
でも、千と一回立ち上がり、一からやり直す力が、あなたにはあります。」
(2014年12月 南米諸国連合会議でのスピーチより)
※ 以上は、佐藤美由紀『世界で最も貧しい大統領 ホセ・ムヒカの言葉』双葉社、2015年7月刊、より抜粋しました。
「どこであろうと、私は好きなように生きているだけだ。自分は貧しくなんかない。
貧しい人間というのは、いつもカネばかり追いかけ、それにとらわれている人間 のことを言うのさ。」(p.24 )
「情熱を持って、物質的な欲望を越えて生きなければならない。意欲的に行き、何かに力をそそぐということは、何でもかんでもやればいいという意味ではないぞ。確実に言えるのは、私は今、人生を最高に楽しんでいるということさ。」(p.27 )
「人生は未来だ。過去じゃない。だからといって、過去が存在しないと言っているわけではない。過去は確かに存在する。が、重要なのは未来なんだ。未来があるからこそ人間は過去を忘れることが出来る。(中略)重要なのは過去を乗り越えることなんだよ。」(p.59 )
「私は貧しいのではない。質素なのだ。私は自由でいたいし、その自由を楽しむ時間が欲しい。貧しいのは誰だって嫌さ。節度を持って暮らし、身軽でありたいと思っているだけだ。」(p275-6)
「死を受け入れられず、不幸なまま死んでいく人たちもいる。何て悲しいことなんだ!基本的に死というものは自然の法則だから、受け入れなければならない。重要なのは、自分の人生をとことん愛することだ。」(p.325 )
※以上は、アンドレス・ダンサ/エルネスト・トゥルボヴィッツ著、大橋美帆訳『ホセ・ムヒカ ー世界で一番貧しい大統領』、角川文庫、2016年3月刊より抜粋しました。
なお、余談ですが、この書物で彼が無政府主義者であることを知りました。
無政府主義者の大統領とはあまりにユニークですね。
最後に、私の目にとまった新聞記事から。
「貧乏とは少ししか持っていないことではなく、無限に多くを必要とし、もっともっとと欲しがることです。」
「乗り越えなければならないのは、私たちの文明のモデルであり、見直すべきは私たちの生き方なのです。」
「質素な生活は自分のやりたいことをする時間が増える。それが自由だ。」
「世界は多くの富を抱え、技術も進歩した。しかし、資本主義は盲目で、だれもそれを止めることは出来ない。それが資本主義の『美しき悲劇』だ。私たちは幸せに生きているのだろうか。」
(2016年 4月7日 東京新聞朝刊より)
(2016. 5. 26)
近代オリンピックの政治学
オリンピックの創立者としてのピエール・ド・クーベルタンの名前、「勝つことよりも参加することに意義がある」という標語(実際は彼の言葉ではありません)はよく知られています。
しかし、古代オリンピック競技の復活は、クーベルタン個人の思いつきではありませんでした。
クーベルタンが推進する以前に、すでにオリンピックと名付けられた競技会が各地で開かれていました。
当のギリシアでも、独立後、19世紀の半ばには「オリンピック競技」が何回か開かれていました。
古代オリンピックの復興は、クーベルタンひとりの着想ではなく、彼が育った時代のヨーロッパに拡がっていた衝動でした。
それが、19世紀末になって実際に国際的な規模で実現させることができたのがクーベルタンの情熱、組織力、実行力でした。
では、なぜ古代オリンピックの再現が、19世紀の多くのヨーロッパ人の夢たり得たのでしょうか。
一つには、19世紀には、かなりな程度までスポーツが普及し、教育にスポーツを採り入れ心身の均衡を理想的な人間性と見なす傾向が拡がっていたこと。
もうひとつは、文化的な潮流、古代ギリシアへの憧憬がありました。
古代ギリシア人の美術・思想は、すでにルネサンス人たちの憧れの対象でしたし、18世紀の啓蒙哲学者たちの著作にも同様の傾向がありました。
つまり、大まかには二つ数えられる流れースポーツへの情熱と古代ギリシアへの憧れーが一致するところに、古代オリンピック競技再興への期待が生じたのでした。
ヨーロッパ人にとって、古代ギリシアのオリンピックがどのようなものであったか、十分解明されないまま、それが、スポーツを志す人類にとって牧歌的な理想のモデルのように見え、そして、古代オリンピック競技に近代スポーツを連続させることは、それによって近代スポーツに古代オリンピックの神話的な彩りを添え、かつギリシア人の末裔であるとしてヨーロッパ人の優秀性を誇張しようとしたことは明らかです。
19世紀の初期近代スポーツ推進者たちにとって、古代ギリシアのオリンピック競技こそ、スポーツの理想的形態であると思い込むことができました。
自らの試みを神話化するには、まことに適切な先行形態でした。
競技者はアマチュアであり、平等な市民であり、獲得するのはただ栄光だけであってそれ以外の報償はない等々。
もちろん、こうした美化は故意に以下の点を言い落としていました。
優勝者は栄光以外に自らの都市から報奨を受け取っていましたし、女性は競技場に立ち入ることさえ許されず、いうまでもなく奴隷制社会は維持されていました。
最後に、オリンピックは回をかさねるごとに儀礼的な演出を工夫してきました。
どれが古代からの遺産なのか、新しい発明なのか区別しえなくなってきます。
例えば、有名な象徴としての聖火、ただの火ではなく「聖」火。
ナチのプロパガンダに利用されたことで悪評の高い第11回近代オリンピック(ベルリン・オリンピック:1936年)では、「聖火」リレーが演出されました。
「聖火」リレーがベルリン・オリンピックのさいに考え出された演出で、当時ナチにとってギリシアからベルリンまでの走路を把握することは、来るべき戦争に対して戦略的意義があったことは忘れるべきではありません。
(多木浩二『スポーツを考えるー身体・資本・ナショナリズム』ちくま新書、2012年4月(6刷)、第2章「近代オリンピックの政治学」より)
「オスマンの平和」と「トルコの圧政」の間
オスマン帝国支配下のギリシアとギリシア人について、近代のギリシア側の歴史叙述においては、もっぱら「トルコの圧政」として描かれることが多かった。
そして、近代西欧におけるこのテーマの叙述においても、同様の傾向が色濃くあらわれてきた。
しかし、時代的背景と歴史的実態を踏まえれば、オスマン帝国支配下のギリシアとギリシア人の状態は、必ずしも「トルコの圧政」の語でかたづけられるものではなかったことも明らかとなってきた。
オスマン帝国史研究のなかでしだいに明らかとなり、バルカン史、さらに近代ギリシア史においてもある程度認められてきたのは、オスマン支配下のギリシア人に対しては、弾圧や強制改宗よりはむしろ、「不平等のもと」ながら「共存」ないし、「許容」の原則がとられ、固有の宗教と法と生活習慣の保持と正教会を受け皿とする一定の自治が認められていたということであった。
このようなオスマン帝国下の異教徒の集団に対する支配システムは、ときに「オスマンの平和」とさえいわれる。
ただし、この「オスマンの平和」が、全き平和と共存のシステムであったかといえば、やはりそれは、はなはだ限定された意味のものであった。
そこでは、宗教に基づくムスリムと非ムスリムとの間の不平等が基礎をなし、そこでの共存は、あくまで優位者の側からの劣位者に対する許容であった。
<中略>
オスマン帝国支配下のギリシアとギリシア人の状態は、必ずしも一方的な「トルコの圧政」のもとにあったとはいえないが、さりとて「オスマンの平和」が全き平和と共存を実現していたともいえない。
それはあくまで当時の時代状況のなかでの相対的なものにすぎなかった。
(桜井万里子編『新版 世界各国史17 ギリシア史』山川出版社、2005年3月刊、266−67頁より)
(2016. 6. 17)
フィリッポス2世暗殺事件
マケドニア王フィリッポス2世は、前338年、カイロネイアの戦いでアテネ・テーベ連合軍を破りギリシア征服を完了しました。
しかし、彼は前336年初夏、東方遠征の準備の最中、王妃オリュンピアスの娘クレオパトラと弟アレクサンドロスの結婚の祝典の場(劇場)で、側近護衛官パウサニアスに暗殺されます。
事件の真相は、謎に満ちています。
以下、アレクサンドロス大王の研究者の説を紹介します。
まず、パウサニアス単独犯説から。
前1世紀のギリシアの歴史家ディオドロスによれば、「パウサニアスはフィリッポスの愛人で、別の愛人とのいさかいから陵辱を受け、フィリッポスに訴えたものの、受け入れられず彼に復讐を企むようになり、アイガイ(マケドニアの古都)における祭典の場で、かねてから計画していた復讐を成し遂げたのである。」(第16巻93−94章)
ただし、この暗殺を息子アレクサンドロス大王に結びつける伝承が存在します。
プルタルコスによれば、「パウサニアス(暗殺者)が、かの侮辱を受けた後、アレクサンドロスに会ってひどく嘆いた時、アレクサンドロスは「嫁の親と婿と嫁とを」という『メーディア』の一節を朗唱したと言われているからだ。」(第10章)
ここでの『メーディア』は前5世紀の悲劇作家エウリピデスの作品で、主人公メーディアの復讐劇ですが、ここでのアレクサンドロスの朗唱においては、嫁の親はアッタロス(後述のクレオパトラの叔父)、婿はフィリッポス2世、嫁はクレオパトラ(フィリッポス2世の7番目の妻。王妃オリュンピアスの娘とは別人)にあたり、アレクサンドロスは、これら三人に対する復讐をパウサウスに示唆したというのが、プルタスコスの記述の意味するところです。
ただし、プルタルコスの伝記作品を研究した専門家によると、「と言われている」というような言葉を付け足すのは、彼自身がその内容の信憑性を疑っている場合が多いようです。
王妃オリュンピアスについてはどうか。
暗殺事件と彼女との関係については、ローマ帝政時代のユスティヌスという作家が詳しく述べています。
「彼(暗殺者パウサニアス)は、アレクサンドロスの母親オリュンピアスに扇動されたのであり、アレクサンドロス自身も父が暗殺されることを知らなくはなかったとさえ信じられている。というのも、オリュンピアスは、自分が離縁されて自分の代わりにクレオパトラが(7番目の妻に)選ばれたことに対して、パウサニアスが受けた屈辱に劣らぬ憤りを覚えたからだというのである。
(中略)
このような怒りに刺激されて、二人(オリュンピアスとアレクサンドロス)は、パウサニアスが自分に対する陵辱が罰せられないでいることへの不満を訴えた時に、彼をそそのかしてこのような行為に走らせたのだと信じられている。
事実、オリュンピアスは、暗殺者が逃走するための馬さえも用意していたのだ。」(第9巻7章)
この史料も、ユスティヌス自身が、「と信じられている」と言う語句を付け加えていることから、その内容は事実と言うより、巷間に流布していた作り話に過ぎなかった可能性が強いようです。
状況証拠は存在するものの、王妃オリュンピアスも息子アレクサンドロス(大王)もフィリッポス暗殺には関与していないというのが、研究者の結論です。
(森谷公俊『アレクサンドロスとオリュンピアス』ちくま学芸文庫、2012年4月刊、第6章「暗殺」103-22頁より)
(2016. 6. 19)
「パンとサーカス」
「かっては権力や権威や軍事などのすべてに力を注いでいた市民たちも、今では萎縮して、たった二つのことばかりに気をもんでいる。パンとサーカスだけを。」(2世紀はじめのローマの風刺詩人ユウェナリスの言葉)
今日しばしば耳にする「パンとサーカス」は、上記の詩人の文句に由来します。
パンの意味するところは、民衆への穀物の配給であり(ぶどう酒や貨幣の分配なども)、サーカスは(今日では曲芸を指しますが、もともとの由来は円形競技場の楕円形コースを意味するキルクスcircus)、戦車競技や剣闘士の戦いなどの見世物を意味しました。
サーカスのような催し物は、軍事や収穫に関連する祝祭と結びついており、次第に祭日、つまり見世物の開催日が設けられるようになります。(年135日)
こうした見世物の開催は、穀物給付よりもさらに広範囲に多くの地方都市でも見られました。
ただ、いわゆる「パンとサーカス」が繁栄期の民衆の堕落を象徴するあだ花にすぎないのではなく、民衆に恩恵を施すと言う行為そのものが、為政者の栄誉を高めるものでした。
公職選挙で支持してもらうためにだけ、つまり権力の獲得のためにだけ、富裕な実力者は恩恵を施すのではなく、彼らにとって、為政者たる権威が認められていることこそ大切でした。
為政者の尊厳は、民衆が活気づき歓呼して親愛の情を示すときこそ浮き立ったのです。
(本村凌二・中村るい『古代地中海世界の歴史』ちくま学芸文庫、2012年11月刊、191−92頁より)
(2016. 7. 6)
イスラム世界の「柔らかな専制」
現在、イスラーム教というと過激派のテロ活動などのイメージが強く、不寛容な宗教で、イスラーム世界は閉鎖的で非合理的な社会と思われがちです。
それに対して、キリスト教は寛容な宗教、西欧社会は開放的で合理的な社会というイメージが定着しています。
しかし、歴史的現実は、少なくとも中世から近代初期に関しては、実態はまったく逆でした。
中世ヨーロッパは、キリスト教の支配する世界で、異教徒に対しても非常に不寛容でした。
原理的にキリス教社会において、イスラーム教徒は存在できませんでした。
十字軍運動の開始と表裏して、外でのムスリム(イスラム教徒)への敵意は、内では、ユダヤ教徒へ向けられ、キリスト教徒が蜂起してユダヤ教徒を虐殺する事件も起こっています。
それに対して、イスラーム世界では、ジズヤ(人頭税)を支払えば、宗教の自由も認められていました。
そこでは、イスラーム教徒だけでなく、キリスト教徒もユダヤ教徒も、独自の宗教を信奉することが許されていました。
16世紀に、スレイマン大帝の時代のイスタンブールで生じたユダヤ教徒に対するムスリム住民の暴動は、常備軍の出動によって瞬く間に鎮圧されました。
ヨーロッパでは、いまだ中世封建社会の遺制が残っていた時代に、オスマン帝国では君主専制の中央集権的支配組織とイェニチェリに代表される常備軍を擁していました。
このように、オスマン帝国は民族も宗教も異にする多種多様な人々を、ゆるやかに一つの政治的社会の中に包み込む、統合と共存のシステムを有していました。
現在、民族紛争と宗教紛争の活断層のような地域をおおいながら、オスマン帝国の支配が600数十年も続いた秘密の一半は、この緩やかな統合と共存のシステムにあったようです。
(鈴木薫『オスマン帝国―イスラム世界の「柔らかな専制」』講談社現代新書、1992年4月刊、254頁、740円)
領主制と封建制
中世のフランスにおいて、領主制は異民族の侵攻や戦乱のための公的秩序の乱れにより、人々が身近の直接的な人間関係に頼ることにより成立しました。
それには、歴史的な先行物がありました。
一つは、ガロ・(ガリア=現フランス)ローマ時代の大土地所有制です。
そこでは、貴族(地主)と家内奴隷・隷属的身分は、国家の法によって縛られていました。
しかし、ゲルマン人の侵入など国家の法秩序の乱れにより、有力地主と奴隷や耕作農民とは直接の<保護=奉仕>の関係に移行しました。
もう一つは、ゲルマン人の国家の「従士制」と「恩貸地制」です。
「従士制」は有力者に忠誠を誓って従士になるかわりに保護を受ける制度。
「恩貸地制」は、従士が騎馬戦士として奉仕する代わりに土地を「恩貸地」として与えられる制度です。(ただし、自由人の契約関係でした。)
しかし、ノルマン人やイスラム教徒の侵入・内乱のため、部族国家の公的秩序は乱れ、「恩貸地」はしだいに世襲的な「封」となり、これをもつ職業的戦士は土地の世襲的主人となりました。
そして、農民は、身近にいるこのような有力者に保護を求めました。
つまり、戦士は単なる「地主」ではなく「命令権」をもつ「領主」になりました。
さらに、自由人だった周辺の農民もしだいに領主の保護下に入り「領主制」が一般化しました。
こうして、「荘園」となった領主の土地は、領主「直轄地」と農民「保有地」とに分けられ、直領地が、「農奴」身分の農民の賦役によって耕作されました。
領主となった有力者自身も、自己保存のためにもっと有力な領主の保護下に入ってその従士となり、領主と領主の間、領主と農民との間に直接的な<支配=従属>関係の複雑なネットワークが形成されました。
前者の領主間の関係をさすのが狭義の「封建制」。
後者をもふくめた階層的な政治社会構造をさすのが、広義の「封建制(封建社会)」の概念です。
封建社会の領主の最盛期は10世紀から13世紀までであり、近世に入ると封建制は存在しないが、領主制は存続しました。
フランス革命期に廃止された「封建制」とは領主制のことです。
(柴田三千雄『フランス史10講』岩波新書、2006年5月刊、pp.27~29より)
ゲルマン人の法・刑罰・裁判
ゲルマン人の大移動(4~6世紀)の後、建国された各ゲルマン人の部族国家は、自分たちが属する共同体の規則を定めた法典の編纂を熱心に行いました。
このような法典を「部族法典」と呼びます。
フランク人の最古の法典である『サリカ法典』は、被害者の身分、ジェンダー(性別)などによって驚くほど詳細に定められた罰金(専門家はこれを贖罪金と呼んでいます)の一覧となっています。
つまり、犯罪に対する刑罰は罰金主義です。
殺人の場合は人命金と呼びますが、それは被害者がローマ人かフランク人か、奴隷か、妊婦かなど詳しく定めてあり、また障害などでは右手を切り落としたらいくら、指を切り落としたらいくら、というように被害箇所に応じて賠償金が決められていました。
ここには暴力は反社会的行為であるという意識がまったく見られず、反対に剣を振るい槍をかまえ弓を引く、手や腕の喪失への関心が大変でした。
戦士社会の倫理と法秩序がどのようなものであるかを、この法典は如実に示しているといえます。
裁判に関しては、ゲルマン人の社会では、「訴えなければ裁判なし」というのが大原則でした。
捜査機関というものが存在しないので、原告は自分で被疑者を捜すわけですが、犯人が特定できなければ泣き寝入りということになります。
訴えは、ふつう被告人が特定されていることが条件でした。
裁判に当たっては、原告と被告人が対決し、証人をともなって自らの言い分を主張しますが、両者の証言が食い違っていて、しかも譲らない場合は決闘などによってことの決着をつけます。
こんにちの裁判では真実の解明が鍵となって、そのために証拠を積み重ねていくのですが、ここでは宣誓による証言が不可侵の神聖性をもつものとみなされます。
だから双方が異なった証言をしたら、あとは神の審判に委ねるほかありません。
方法としては、決闘のほかに、赤く熱した鉄片を素手でつかんだり、熱湯に手を入れたりして、しばらくあとで双方の傷の治癒の具合を調べるとか、手足を縛り、水に投げ込んで浮き沈みで判定するなどがありました。
傷の浅い方が真実の証言者であるとみなされました。
水の神判では沈んだ方が、よしとされました。
神が正しき者として受け入れたからこそ、沈んだのです。
(佐藤彰一・池上俊一『西ヨーロッパ世界の形成<世界の歴史10>』中央公論社、1997年5月刊、pp.70~73より)
※ ちなみに、熱湯に手を入れて神判を仰ぐというのは、日本の古代の「盟神探湯(くかたち)」と同じで、面白いですね。
チンギス・カンの墓所
チンギスギス・カンの墓は、世界史の謎の一つとして未だ不明ですが、
白石典之『チンギス・カン』、に興味深い内容の記事が載っていました。
ご存じのように遊牧民は、季節ごとに牧草地を求めて移動しますが、チンギス・カンも季節によってオルド(宮殿)を移動しました。寒冷期は「ヘルレン」、温暖期は「サアリ・ケル」または「カラトン」という所に滞在しました。
著者は、この「ヘルレン」をアウラガ遺跡に推定しています。アウラガ遺跡とは、モンゴル中東部、ヘルレン河上流域のヘンティ県デリゲルハーン郡にある13世紀の集落跡です。そして、このアウラガ遺跡の中心に、チンギス・カンの宮殿を想定し、さらに、その遺宮が霊廟として使われるようになったと考えています。
さて、チンギス・カンの墓は造られた当初から、周囲が柵で囲われ、兵士が警備し、誰も近づくことができなかったようです。しかし、ある目撃者の証言「私は見た、テムジン(チンギスの幼名)の墓を。それは、ヘルレン河のほとりにあった。周りを山と河に囲まれていた。」から、さらに『集史』に、「チンギスの霊廟は彼の墓の近くにある」と書かれていることなどから、著者はアウラガ遺跡周辺に墓地がある可能性が高いと結論づけています。
ちなみに、この墓所はチンギスだけではなく、大モンゴル国(初代チンギスから第16代トグス・テムルまで)16人の君主の内、13人が葬られているようです。元寇のフビライ(クビライ)もその一人です。そこはモンゴル版「王家の谷」ですが、ただ、史料などからは、ピラミッドや始皇帝の墓などとは違って、質素で小規模な墓であったようです。
(白石典之『チンギス・カンー“蒼き狼”の実像』2006年1月刊、中公新書より)
トゥグリル・ベクと藤原定家の『明月記』
トゥグリル・ベクは、イスラーム世界のセルジューク朝トルコの建国者です。
1055年、トゥグリル・ベクはアッバース朝の都バグダードに入城して、カリフからスルタン(君主)の称号を得て武家政治をはじめました。
彼がバグダードに入る前の年、不思議な前兆がありました。
年代記によれば、突然空にまばゆい光があらわれ、一ヶ月もその状態が続いたと言います。
肉眼でも長さが五メートル、幅が五〇センチほどにみえたといいます。
この現象は中国、日本でも観測されました。
我が国では、藤原定家の『明月記』に記録が残っています。
客星古現例として、定家誕生以前の出来事であるが伝え聞いた内容として、以下のように記載されています。
「後冷泉院・天喜二年(1054年)四月中旬以後の丑の時、客星觜・参の度に出づ。東方に見(あら)わる。天関星に孛(はい)す。大きさ歳星の如し。(原文読み下し)」
これが、天文学の分野では有名な、おうし座のなかの恒星が超新星となった大爆発でした。
いまでも、その名残の星雲を見ることができる、カニ星雲です。
(佐藤次高・鈴木薫『都市の文明イスラーム』講談社現代新書、1993年9月刊、132頁;ウィキペディア『明月記』より)
マムルークの誕生
マムルークとは、イスラーム法のなかでは、「男奴隷」を意味するアラビア語です。
歴史的にはトルコ人、スラブ人、ギリシア人などのいわゆる「白人奴隷兵」をさして用いられました。
奴隷兵としてのマムルークの起源は、ウマイヤ朝までさかのぼり、アッバース朝カリフのムータスィム(9世紀中頃)は、イスラーム史のなかではじめてトルコ人マムルークを大量に購入して親衛隊として身辺の警護に当たらせました。
9世紀の初めに成立し、後半に独立したサーマン朝の重要な収入源は、このマムルークといわれるトルコ人の奴隷を仕入れ、イスラーム世界に輸出することでした。
サーマン朝では、自ら購入した軍事奴隷の訓練を行いました。
購入したトルコ人少年が立派な騎士として卒業するまで、七年にも及ぶ訓練が施されました。
最初の一年は騎乗することができない。
次の年からは、トルコ馬と簡素な鞍、馬勒(ばろく)をあたえられ、三年目には剣が、四年目には矢筒と弓入れが、五年目にはもっと良質な鞍、星の飾りのついた馬勒、乗馬服が、六年目には、「盃もち」の役をあたえられ、七年目には「衣装もち」の係りとなる。
次の年には天幕もあたえられ、三人の新入りの奴隷もつけられる。
以後、軍隊の中で順をふんで位が上がっていき、やがては総司令官になるものもあらわれました。
それどころか、こうした軍事奴隷から支配者になるものもありました。
トルコ人奴隷がこれほどまで重んじられたのには、いくつかの理由があります。
遊牧のトルコ人が戦闘能力に優れていたこと。
馬に乗って矢を射る技術は,彼らの独壇場でした。
それから、少年のころから職業訓練をすることによって、生まれた土地や血縁から切り離され、君主に絶対的な忠誠を誓うようになったこと。
本来の自由人とはことなり、いくら出世をしても、その地位や権力を子供が引き継ぐことがなく、使う側から見れば不安がなかったことなどです。
彼らはいわば、職業的なテクノクラートであったといえます。
子供の出世と安定した地位を望むあまり、奴隷商人にすすんでわが子を差し出す親がいたという話も残っています。
(佐藤次高著『イスラーム世界の興隆<世界の歴史8>』中央公論社、1997年9月刊、pp.150~151;佐藤次高・鈴木薫編『都市の文明イスラーム』講談社現代新書、1993年9月刊、pp.108 ~110より)
騎馬の威力
北宋が、宿敵の遼を、女真族の金と結んで打倒した直後のことです。
金側の講和使節団は、17騎で本国との連絡のため、河北を北へ急いでいました。
これを途中で、北宋側の在地軍事指揮官が、2000の歩兵をもって襲撃しました。
討ち取って、戦功としようとしたのです。
ところが、武装していた17騎は、ただちに左・中・右の三隊にみずから小分けしました。
中央に7騎、左・右に5騎ずつです。
手慣れた戦闘隊形です。
このささやかな三隊は、駆けめぐり、射たて、敵陣を攪乱し、縦横に馬を走らせました。
2000人は散々に翻弄され、なすすべもなく潰走しました。
17騎は、1騎もそこなわれませんでした。
これは、北宋側の記録にあり、実話です。
(杉山正明著『遊牧民から見た世界史 増補版』日経ビジネス文庫 2011年7月刊 43頁 <コラム>騎馬の威力から)
杉山 正明著『遊牧民から見た世界史 増補版』
杉山 正明著『遊牧民から見た世界史 増補版』日経ビジネス人文庫、2011年、477頁 952円。
著者は現在、京都大学大学院文学研究科教授。
主要研究テーマは、モンゴル時代史。
1995年『クビライの挑戦』でサントリー学芸賞、2007年『モンゴル帝国と大元ウルス』で日本学士院賞を受賞しています。
構成は、以下の通りです。
『遊牧民から見た世界史 増補版』のための追記
1 民族も国境もこえて
2 中央ユーラシアの構図
3 遊牧国家の原型を追って
4 草原と中華をつらぬく変動の波
5 世界を動かすテュルク・モンゴル族
6 モンゴルの戦争と平和
7 近現代史の枠組みを問う
あとがき
解説―「定住」と「移動」をめぐって(松本健一)
本書の目的は、“前近代のユーラシアにおいて、大きな歴史の動因となった遊牧国家のありようをながめ、それが主軸となって展開したユーラシア世界史の脈絡の中で、「国家」と「民族」をもう一度あるがままにとらえ直すこと。”(「あとがき」より)とあります。
どの章も、今までの西洋本位の見方や、中国の王朝史観からではなく、その視点は、タイトルにあるように遊牧民の側にあり、改めて歴史を見直しています。
すなわち、複眼的な視点で世界史を見る必要性が語られています。
また、最後の第7章『近現代史の枠組みを問う」では、戦後の高等学校教育での「世界史」の西洋本位の世界史像が批判されています。
著者の“コロンブスの西方航海にはじまる、「地理上の発見」という西欧の立場からの身勝手な言い方が当然視されている。”(440頁)という言説は、言い過ぎで、近年は「大航海時代」と言い換えられています。
ただ、“戦後50年をすぎ、「世界史」を学習した人が、西欧本位で語られる世界史イメージをインプットされ、実際にあった歴史よりも、はるかに西欧中心のイメージが頭に刷り込まれてしまっていて、それがある種の「文明観」「価値観」を決定しているようにさえ見える。”(441頁)という指摘。
そして、「新しい世界史像へむけて」という小見出しでの、“歴史においては、既存の世界史が語る構造やイメージ・概念をまずは、根本から疑ってかかってみたい。近代国家、現代文明という考えや、民族・国境という概念も。(460頁)という批判は、教える側としては、重く受け止める必要があると思います。
「老子」の思想とメッセージについて
(A) 「老子」は人間にある宇宙意識と社会意識の間のバランスを語る。つまり、その左手は、なにも摑めない宇宙に向かって開き、右の手は、しっかり摑める大地のものを握りしめている。その大きなバランスを「老子」の言葉から感じると、人は安らぎやくつろぎの気持ちの湧くのを覚える。
(B) この大きなバランスの視点から老子は、人間のする「行き過ぎ」に警告を発している。たとえば、近世以来の西洋(欧米)社会では、所有(possession)、自己主張(self-assertion).支配(dominateon)の三つの態度が、国にも人びとにも優勢となり、過度になった。今にいたってはそれがわが国にも波及している。古代中国の「老子」の時代にも同じ傾向が強まったのであり、彼はそれを戒めて。「争ウナ」「自カラ足ルコトダ」といった言葉をいくども発している。これらの言葉はいま、個人にたいして有用であるばかりか、二十一世紀の世界全体への警告となっている。
(C) 老子『道徳経』は、すべてが、「復帰」ーreturn processーの働きのなかにあると説く。これが根元思想である。天地の間にあるすべてのものは、社会も人間も、根に帰るーすべてが、大自然に、さらにその向こうの源(みなもと)に帰ると説いた。
(加島 祥造『タオ ー老子』ちくま文庫、2011年10月刊(第8刷)、「あとがき」274 –75頁より引用。)
※ この本は、英文学者・詩人である作者が、老子の『道徳経』全81章を口語に訳した詩集です。自由に、英訳から(あるいは原文・注釈から)、創造されており、漢文になじみのない私にも面白く読めました。
なお、同著者の『求めない』小学館、2007年11月刊(第10刷)、188頁、1300円。は、彼のタオ(道)の精神を表した詩集です。
宦官の誕生
宦官は、後宮に仕えた去勢された男性です。
この宦官は、中国の特産ではなく、時代を遡れば、エジプト、ギリシア、ローマ、トルコから東は朝鮮まで、地中海からアジア全域にわたって存在していました。
中国において、宦官の果たした役割は実に大きく、時に皇帝の影として、側近として権力を握りました。
清朝の歴史家は、各王朝ともその衰亡の原因が宦官にあったことを指摘し、特に、漢・唐・明にいたっては、直接宦官によって滅ぼされたと説いています。
また宦官の起源は、異民族の捕虜を去勢したものと思われますが、宦官は、この捕虜、宮刑(死刑に次ぐ刑罰)、自宮(宦官志望者)の三つのパターンがありました。
ここでは、自宮による宦官の誕生、つまり去勢の仕方について、1870、80年代の資料から紹介します。
紫禁城の西門にあたる西華門を出たところに手術場がありました。
ここに、「刀子匠(タオツチャン)」(執刀人)と呼ばれる無給ではあるが政府公認の専門家が数人いました。
彼らは宦官を作ることを生業としている世襲的な家族でした。
手術料は、一人前銀六両(テール)(約三万円)でした。
さて、手術の方法ですが、まず白い紐で、被手術者の下腹部と股の上部あたりを固くくくります。
また、陽物の切断をおこなうあたりを暑い胡椒湯で三度念入りに洗ったのち、鎌状に少し彎曲した小さい刃物で陽根、陰嚢もろとも切り落とします。
その後、白鑞(はくろう)の針、または栓を尿道に挿入し、傷は冷水にひたした紙でおおい、注意深く包みます。
それが終わると、二人の執刀者にかかえられて被手術者は二、三時間部屋を歩き回り,その後横臥を許されます。
手術後、三日間は飲水は許されず、かわきと傷の痛みのため,その間非常な苦痛を味わうといいます。
三日経ってその栓を抜くと、噴水のような尿が出、これで成功ということになり、祝いの場となります。
手術後はほぼ百日ほどで傷がなおり、その後、王府に送られて宦官の実務を習い、そして一年の終わりに宮城に移され、新しい職に就くことになります。
このようにして、宦官が誕生しました。
それでは、なぜ宦官は日本に存在しなかったのでしょか。
第一には、日本の古代社会において、異民族との幅広い接触、あるいはそれらを征服したという事実がなかったこと。
日本の自然環境が島国であったことが、宦官を作らなかった決定的条件と考えられるようです。
また、第二に、我が国が盛んに大陸文化を輸入したとき、その文化は唐のそれですが、そのうち刑法についてみれば、唐の五刑である笞、杖、徒、流、死は確かに取り入れられましたが、宦官の供給源であった宮刑はそこには入っていませんでした。
宮刑は隋の時代に廃されていました。
こうしたわけで、我が国では宮刑は行われず、当然、宦官も登場しなかったと考えられます。
(三田村泰介著『宦官(かんがん)―側近政治の構造』中公新書1963年1月刊、第1章、終章Ⅰより)
科挙―中国の受験地獄
科挙とは、隋の時代(598年)に始まる学科試験による官吏任用制度です。
楊堅(文帝)が君主権の強化を目指し、地方政府の世襲的な貴族の優先権を認めず、地方の役人(官吏)をすべて中央政府から任命派遣することに改めました。
この官吏有資格者を製造するために科挙制を樹立しました。
科挙は、宋代に皇帝(天子)による最終試験(殿試)が導入され完成し、元代に一時中断されましたが、清末の1905年まで続きました。
科挙は、古来数々の批評も受け、非難もこうむりましたが、しかし1300年余も連綿として実施されてきたことは、やはりそこに何らかの取るべき利点があったことを証明しています。
以下に、科挙制度の理想のなかの優れた点と現実を挙げてみます。
第一に科挙はだれでも受けられる、開放的な制度であることがその特徴です。
若干の例外はありますが、士農工商を問わず、誰でも応ずることができるから,非常に民主的な制度だといえます。
ただし、これは、万人が等しく科挙に応じる権利を行使できるとはかぎりません。
そこには経済的な問題があります。
科挙は長い連続した試験の積み重ねで、その競争も激しく、絶えず勉強をし続けるためにはそれだけの経済的バックが必要です。
貧乏人にはとうていそれだけの余裕はありませんでした。
また、個々の試験については別に受験料をとりませんでしたが、それに附帯した費用が大変でした。
例えば、地方試験(省の首府)である郷試への往復の旅費、宿賃、試験官への謝礼、係員への祝儀、宴会費や交際費もかかせません。
それが進んで、会試、殿試のために都まで出て行くことになると一層費用がかさみます。
明代の後半、16世紀にはこの費用は、約六百両(日本円にして600万円)であったといいますから、いかに受験料が無料でも、所詮一般人には高値の花で手が届きませんでした。
このように見ると、科挙が万民に門戸を開放するという看板には掛け値があったのは確かなのですが、これも時代と比較して批評する必要があります。
当時、ヨーロッパはいまだ封建制の時代です。
家柄も血筋も問わず,力のあるものは誰でも試験を受けることができるという精神だけでも、当時の世界でその比をみない進歩したものであったといえます。
次に科挙がもつ優れた利点としては、それがきわめて公平に行われる点にありました。
郷試の試験場(貢院)は、一人一人カンニングを防ぐために,受験生(挙士)は独房(号舎)に入れられ、三日二晩の試験にのぞみます。
大門からの入場に当たっては、四人の兵卒が身体検査、荷物検査を行います。
書物は言うに及ばす、文字を書き込んだ紙片は持込厳禁で、もしそれを発見した兵卒があれば銀三両を賞として与えられるというので、取り調べは厳重を極め、食料の饅頭を割って中の餡まで調べると言います。
さらに、答案審査は姓名を見ずに、座席番号だけで行われます。
郷試、会試においては、答案そのものに審査員が手を触れず、ただその写しを見て採点します。
筆跡で受験生を特定できないようにするためです。
具体的には、受験生は、答案用紙を黒字で書き、それを写字係が朱筆で写し取り、その答案を審査員が審査します。
なお、写本の誤りは、校正係が黄色の筆で記します。
写字係、校正係とも姓名を記し,責任を明らかにし、後日不正が発覚した場合は処罰されます。
このようなやり方は、現今の世界においてもその比を見ません。
世間が科挙に期待し、その合格者を尊敬するのも、この科挙の公平さを信じてのことでした。
しかし、これにも限界が有り、科挙はしばしば受験生、及び当事者自身の手によって、その公正さが歪められる事実がおこりました。
豆本を試験場に持ち込むことや、肌着にいちめん四書五経の本文を書き込んで入場する者、もっとひどいのは替え玉受験です。
多額の報酬を受け取り、商売として成り立っていたようで、優秀な答案書きは、何人分も請け負っていた例もあります。
さらに、受験生と試験官が共謀すること(関節)もありました。
しかし、こうした不正には輿論がはなはだ敏感で、世間は目を皿のようにして試験の合格発表を見守っており、不正が甚だしいときは輿論の制裁を受け、二度と立ち上がれないほど手ひどく打ちのめされたようです。
中国歴代の政府は、少なくとも天子自身はあくまで試験の公正を守り通したかったのであり、そして世間の方でもとやかく非難しながらも、科挙に多大の関心を示し、社交界第一の話題に取り上げたのは、天子の公正な態度に期待をよせていたためにほかならなかったのです。
(宮崎市定『科挙―中国の受験地獄』中央公論新社、1984年2月刊、郷試ならびに科挙に対する評価より)
羽田 正著『新しい世界史へ ―地球市民のための構想』
羽田 正著『新しい世界史へ ―地球市民のための構想岩波新書、2011年11月刊 220頁 760円
本書は、副題の通り、「世界はひとつ」という視点から、地球市民のための世界史を構想するという、意欲的な書物です。
はじめにに書かれているように、これまでの我々が知っている世界史の常識を壊し、新しい世界史を作り出すことを提案しています。
本書の構成は、以下の通りです。
「目次」
はじめに
序章 歴史の力
第一章 世界史の歴史をたどる
第二章 いまの世界史のどこが問題か?
第三章 新しい世界史への道
第四章 新しい世界史の構想
終章 近代知の刷新
あとがき
序章では、歴史には力があり、現実を変える力があるはずなのに、現代の日本の歴史学と歴史研究者に元気がないことが指摘されています。
著者は、歴史学者の多くが、2,30年前の立ち位置にとどまり、研究テーマは細分化され、本人以外はほとんど誰も読まない論文を次々と生産していると、痛烈に現状を皮肉っています。
現代には現代が必要とする歴史認識があるはずで、今歴史学者が必要なのは、時代にふさわしい過去の見方、すなわち新しい世界史を提案することが必要だと述べられています。
以下、簡単に各章の内容を要約してみます。
第一章では、現代日本における世界史の理解の概略とその成立の経過が描かれています。
世界史の歴史です。
学習指導要領を読んで、世界史の大きな枠組みの特徴が記され、そこに描かれた世界史のあらすじが世界の見方と呼応していること。
私たちの世界認識を強く規定していることが指摘されています。
ここでは、戦前から今に至る歴史学と歴史教育の歴史が述べられています。
第二章では、我々が知っている世界史がなぜ時代に合わないのか、どこに問題があるのかが三つの観点から説明されています。
第一に、現行の世界史が、日本人の世界史である点。
第二に、現行の世界史が、自と他の区別や違いを強調する点.
第三に、現行の世界史は、ヨーロッパ中心史観から自由ではない点。
著者は、この三つの問題点の根は同一で、19世紀に成立した近代歴史学そのものが、この三つの性格を備えていたと結論づけています。
第三章では、上記の三つの弱点の克服のために、これまでに試みられてきた新しい世界史に向けての様々な取り組み(有効性と限界)が、中心史観からの脱却と共通性・関連性の重視という二つの範疇に区分して紹介されています。
第四章では、新しい世界史のための具体的な方法が説明されています。
その三つの方法として(1)世界の見取り図を描く。(2)時系列史にこだわらない。(3)横につなぐ歴史を意識する。が、提案されています。
終章では、著者は、我々が抱いている「世界」の全体のデザインの基本は、19世紀後半までに姿を現した「ヨーロッパ」対「非ヨーロッパ」という世界認識であると主張します。
そして、19世紀から20世紀初めにかけて形成された人文社会学系の学問の多くが、この二項対立的な世界観を内包して、理論・体系化を進め、整理や分析という区別のための方法論を整え、その見方に沿った知を今日至るまで再生産し続けていると述べます。
我々の世界を見る目を縛っている重要な要素の一つである世界史の見方を刷新する必要のあること。
そして、現代世界の諸問題の解決として、無意識に受け入れている世界認識の基本を変える必要があると述べています。
「世界史」を教えている者として、この本はとても刺激的で勉強になりました。
ヨーロッパ中心史観に対する批判なども、随分前から言われて来ていますが、高校の現場の教師にとっては、「新しい世界史」の授業を実践するのは、なかなか難しいかな、というのが正直な感想です。
しかし、言うまでもなく、現代の世界を正しく理解するためにも、こうした試みは必要だと思います。
古代ローマ市民の子供たち
古代ローマにおいて、生まれた子供が、ローマ市民の社会に迎え入れられるためには、まずローマ市民のファミリア(「家」)の一員として認められる必要がありました。
そのためには、家父長による認知が必要でした。
ローマの場合、家父長は子供以下のファミリアの構成員に対する生殺与権を有していました。その権限は、奴隷に対する主人の持つ権利になぞらえられています。
この認知は、「幼児の取り上げ(抱き上げ)」と表現されました。
この家父長による認知が必要なことは、逆に認知がなされない場合のあることを示していました。
実際、多くの史料から、様々な理由で、家父長によって認知されず、遺棄された嬰児に関する記述が見いだされます。
遺棄された子供たちが、死亡せずに拾われた場合には、拾った者の奴隷となりました。
その後、運が良ければ、解放されて市民となることもありました。
幸いにして、家父長に認知された子供は、出生後、八日ないし九日目に「浄めの日」を迎えます。
饗宴が催され、この日を境に、子供は名前で呼ばれます。
また、ブッラと呼ばれる魔除けの金のメダルを首からぶら下げます。
このメダルは、自由人として生まれたことの証明でもありました。
幼児期の子供たちにとって、大きな存在であったのが、乳母と家庭教師です。
もちろん、ある程度富裕な家庭に限られていたと思われますが、乳母と家庭教師、特に前者は紀元前後のローマ社会においては、広く普及していたようです。
ローマ市民の子供たちは、おおよそ七歳ぐらいまでの幼児期を、この乳母と家庭教師のもと、家の中で過ごしました。
さて、ローマ市民たちの子供が、初めて家の外の社会に触れるのは、学校、とくに初級の学校でした。
初級学校は、「文学学校」と呼ばれ、読み書きと算数を教えていました。
初級学校を終えると、一部の裕福な家庭の子供たちは、もっと上級の文法教師と修辞学教師のもとに通います。
ローマの市民社会では、ギリシアやヘレニズム世界の教育において重視されていた哲学、自然科学、歴史、地理などは重視されず、法廷での弁論や政治上の演説を行うための修辞学の修得が、教育の最大の目的でした。
このような学校を経て、ローマ市民は本格的に社会に巣立つことになります。
その時期は、現実には様々でした。
多くの市民は、せいぜい初等教育を出たのみで、早くから生計のために社会に出たと考えられます。
一方、上層市民の子弟は、文法教師・修辞教師の教育のもとでの教育を経て、社会に巣立ちました。
その時期は、年齢的には十六〜七歳で、ローマ市民の男性にとっての成人年齢とほぼ一致していました。
ローマ市民の男性にとっての成人とは、軍務につくことが可能となることでした。
十六歳になった少年は、魔除けのブッラを神殿におさめ、兵員名簿に登録されて、子供服から大人の服(市民服トーガ)へと衣をかえます。
成人となった男性は、さらに軍務や法廷での見習いの訓練期間を経て、本当の意味での成人となります。
政治を志す市民の場合は、公職者としてのキャリアを歩み始めることになります。
なお、女性は、結婚とともに成人と見なされました。
(島田誠著『古代ローマの市民社会』山川出版 1997年1月刊 p.66〜72より)
お姫様抱っこの起源
ローマ建国当初の話です。
男ばかりが増えたローマでは、女性不足の解消のために、隣国のサビニ人を祭りに招待し女性を略奪しました。
当然、戦いになりましたが、妻にした女性たちが間に入り和解しました。
女性を力ずくで奪ったローマの男にならい、欧米では、新郎が花嫁を抱き上げて、新居の敷居をまたぐ風習が残っています。
(坂本浩『知識ゼロからのローマ帝国入門』幻冬舎 2009年5月刊 31頁より)
坂本 浩著『知識ゼロからのローマ帝国入門』
坂本 浩著『知識ゼロからのローマ帝国入門』幻冬舎 2009年5月刊 190 頁1300円
目次は、以下の通りです。
はじめに
遺跡でたどる帝国の足跡
第1章 ―建国期― 都市国家ローマがイタリア半島を統一する
第2章 ―成長期― ローマの拡大とともに、社会が混乱してくる
第3章 ―転換期― ローマ帝国が誕生。大改革で繁栄の基礎をつくる。
第4章 ―円熟期― 名君・暴君のもと「ローマの平和」が200年つづく
第5章 ―衰亡期― 戦争と内乱があいつぎ、帝国が滅びる
タイトル・目次にあるとおり、とてもわかりやすくローマの歴史がまとめられています。
各章の最初には、ビギナー必読として「早わかりローマ帝国」、(年表・あらすじ)が明記されています。
本文の内容も、イラストを豊富に使ってあり、とても読みやすくなっています。
ただ、その分、情報量が少ないのは否めません。
2時間くらいで、かいつまんでローマの歴史を知りたい、そうした高校生等には有益な本かもしれません。
「カエサルは、妻に愛をささやいたか?」
本村凌二『ローマ人の愛と性』講談社現代新書、1999年。
この本は、愛と性の問題から、ローマの家族制度の問題を取りあげ、さらには、彼らの心性に切り込んでいきます。
「カエサルは、妻に愛をささやいたか?」(120頁)
著者の結論は、否です。
ローマ社会は「家父長の権力が絶大であった」といわれています。
著者は、家の名誉を重んじる気風は、相互の愛情や信頼に基づく夫婦あるいは家族という観念を育むことはなく、夫婦愛という観念はほとんど感知されていなかったといいます。
さらに、男女関係において、愛を語る対象は、同等・対等な人間関係でなければなりません。
ローマは、ギリシア(アテネ)と同様、男性社会です。
男と女は対等ではありえず、男女の差は歴然としていました。
夫婦愛に至る恋愛感情がめばえるには、男の世界が幅を利かせ、女の世界は片隅に追いやられていました。
つまり、夫婦の関係も同等・対等ではありませんでした。
カエサルはクレオパトラとの恋愛が有名です。
著者に言わせれば、彼女はエジプトの女王。
つまり、一個人として、カエサルと対等な関係が保たれたと考えられます。
カエサルは、クレオパトラには愛をささやいても、妻には愛をささやかないのです。
ローマ皇帝4題
妻の両腕にだかれながらの臨終。
初代ローマ皇帝アウグストゥスの臨終の言葉。
「リウィアよ、われわれの共に過ごした日々を忘れずに生きておくれ、さようなら。」後14年8月19日、76歳を目前にしての永眠でした。(232頁)
暴君ネロ最後の言葉。
「この世からなんと偉大な芸術家が消え去るのか。」(253頁)
民衆にサービスする為政者
皇帝ウェスパシアヌスの時代は、政治権力は安定し国家財政も健全になり、小麦の無量給付、様々な見世物が提供された。民衆にサービスする為政者の原像ができあがったが、死に臨んでも「余は神になりつつあるようだな」と冗談を飛ばすことを忘れなかった。(261頁)
晴耕雨読の皇帝
ディオクレティヌス帝は、引退後、田園の豪華な別荘に住んで野菜作りに熱心でした。後継者争いが繰り広げられていたので、復位をすすめる声があがったが、彼は「わしが菜園に植えたキャベツの世話にどれほど心をくだいているか、それがわかれば、そんな頼み事はできないはずだよ。」と答えただけでした。(311頁)
(本村凌二著『興亡の世界史第4巻 ―地中海世界とローマ帝国』2007年8月刊、講談社より)
本村凌二著『興亡の世界史第4巻 ―地中海世界とローマ帝国』
本村凌二著『興亡の世界史第4巻 ―地中海世界とローマ帝国』 2007年8月刊、講談社 388頁 2300円
目次
まえがき
第一章 前146年の地中海世界
第二章 世界帝国の原像を求めて
第三章 イタリアの覇者ローマ S・P・Q・R
第四章 ハンニバルに鍛えられた人々
第五章 地中海の覇者
第六章 帝政ローマの平和
第七章 多神教世界帝国の出現
第八章 混迷と不安の世紀
第九章 一神教世界への大転換
第十章 文明の変貌と帝国の終焉
最後の第十章の小見出し「ローマ帝国は滅亡したのか」(339頁~356頁)の内容が興味を引かれましたので、以下に要約してみました。
「ローマ帝国は滅亡したのか」
〇ローマ帝国他殺説
・ゲルマン人が容疑者―大挙してローマ帝国領土内に侵入・移住(ピガニオール)
・476年ゲルマン人傭兵隊長オドアケルによる国家転覆。西ローマから皇帝という地位が永遠に失われた。
〇癌による死亡説
・癌細胞はキリスト教―キリスト教が普及し優秀な人材が教会に吸収された。(モミリアーノ)
〇脳卒中説
・東西分裂の段階で東西のバランスが取れず、発展の差異が激しく、そのスト
レスによって生じた動脈硬化が半身不随を引き起こした。
〇生産力の枯渇と自然死説
・人的資源の枯渇―人口の減少、背景に気候変動。奴隷の枯渇など。
・農耕が減少したり痩せたりした面。
・奴隷や土地のように社会を成り立たせている生産力の骨格が身体に比べて細
くなってしまった。(マックス=ウェーバー)
・属州の活発な生産により、帝国の中心にあるイタリアが生産地としての主力の地位を失った。(ロストフツェフ)
・ローマ世界あるいは古典古代が天寿を全うした。老衰説。(著者)
※ 著者の見解
20世紀後半(1970年代)になると、上記のような考え方は欧米中心の考え方であると言う批判が登場。
これまでの衰退・没落史観というものを否定する見方、「古代末期」という時代が持つ意味を根底から再考してみようという動きが現れる。
・宗教的には西ヨーロッパにおいては、カトリック世界が築かれ、東ヨーロッパにはギリシア正教が生まれ、西アジアにはイスラム世界が登場する。
・三つの世界にはそれぞれ古層があり、古代末期にはローマ帝国統合以前の伝統的世界の復活が見られる。
・古代末期の宗教や文化に同時代性が現れるー壁画などに抽象芸術が登場する。
・古代末期の民衆の心性に注目すれば、3世紀から7世紀までの期間は、たんなる「古典古代の黄昏」の時代ではなく、一つの新しい秩序が生まれ、これまでにない考え方や感じ方が生じた時代である。
・古代末期を衰退や没落と考えるのではなく、人間の営みの時代として理解する。人間というものは、常に新しいことに挑戦しているのであり、そのような時代として見直すべきなのであろう。
古代ギリシアの同性愛について
古代ギリシアにおいて、少年愛、同性愛は日常的な普通の行動でした。
哲学者ソクラテスも少年愛でした。
少年を愛し、育てることは、一人のギリシアの男性としては、ごく普通のことでした。もちろん、そこには性愛の要素も含まれます。
そうした、男性同士の精神的、肉体的結びつきが、団結心に富む戦士集団を作りあげたと思われます
女性同士のレスビアンは、レスボス島の女流詩人サッポーが、女の子を集めて教えたことから、その島の名前が由来となっています。
ただ、ここでの同性愛は、あくまで、男性同士の問題です。
古代ギリシアは、男性中心の社会です。
女性は、アテネの場合、父親の言うままに、顔も知らない男性に嫁ぎ、女部屋で奴隷(女中のようなイメージです)を使い、家事をして暮らしました。
頻繁に外出をしていると、市民からは、はしたないと思われました。
ギリシアの同性愛は、キリスト教的倫理観を持った近年の欧米の学者には、とうてい受け入れられなかったようです。
もっと言うと、受け入れたくなかったのでしょう。
いわゆる、そこには同性愛に対する偏見があります。
以下は、ケネス・ドーヴァー(K.J.Dover)著 /中務・下田訳『古代ギリシアの同性愛』リブロポート、1984年。
<序文>からの引用です。
エーリッヒ・ベーテ(Erich Bethe)は、70年前に発表した論文で、「学問にとって不倶戴天の敵」である道徳的評価の介入によって、ギリシア人の同性愛の研究が損なわれてきた。」と評したが、今日でも事情は変わっていません。
トムソン(J.A.K.Thomson)は、
同性愛関係は、「ドーリス人の罪であり、アテナイでこれに手を染めるのはほんの一握りの者たちであった。
テイラー(A.E.Taylor)は、
「法的にも世論によって醜行と見なされていた。」
フラスリエール(Flasceliere)、マルー(Marrou)らは、
「同性愛」もっと言えば、「少年愛」は、ほとんどのギリシア都市において、
法律で禁じられていた。
こうした判断の根底には、アテナイびいきと同性愛に対する嫌悪があります。
ギリシアの文化一般に対する愛着が、その文化内でごく重要であった行動上の特徴を認めることが出来ない。あるいは認めたくないという気持ちが存在しています。
※ 歴史を見る上で、自分の固定観念とか、道徳観で見ることの危うさを端的に物語っています。
偏見にとらわれず、具体的な史料をきちんと読み、推論を行うという基本的な学問の姿が、性的側面に関しては、かくも容易に破綻しているのは、驚くべきことです。
エジプト史2題
ピラミッドについて。
ピラミッドは、かって考えられていたような王墓ではなく、王の葬祭および太陽信仰と関係の深い建造物だという指摘がされています。(10頁)
ピラミッドや後の王墓すべてが、上部構造と下部構造からなっており、合わせて一つの墓として機能していたこと。現世と関係が深い供養室(礼拝室)が地上かそれ近くにあり、個人を埋葬するための部屋は地下に作られたと述べられています。(156頁)
人体表現について。
次に、壁画に描かれた古代エジプト人の人体表現です。
それは、「正面性」の原則と呼ばれています。
著者によれば、古代のエジプト人は、一人の人間の中のそれぞれの部分に、永遠に残されるべき本質、ものの本来の性質や姿が含まれていると考えました。
「目」が「目」として一番よくわかるのはどこか。それは「前向きの目」、
「鼻」は横から、「肩」は前から、「胸」は横から、「ウエスト」は正面から、「足」は横からでないといけない。
つまり、この人体表現は、「永遠」を表現する様式であり、写実主義は、かれらにとっては、特定の時間、特定の方向から見た姿にすぎず、永遠にはふさわしくないと考えていたようです。(69頁)
あの墓室に描かれた独特の表現の古代エジプト人の人物や神の姿は、その見せる対象我々人間ではなく、神々であったようです。
(村治笙子著、仁田三夫写真『カラー版 古代エジプト人の世界—壁画とヒエログリフを読む』岩波新書 2004年11月刊より)
戦車の登場
ここで言う戦車は、馬に引かせる車両のことです。
西アジアにおいて、馬の出現は、ユーラシア北方の森林・草原地帯を原住地としていたインド=ヨーロッパ語系の武装集団が荒々しく侵攻した時期と重なっています。
具体的には、ヒッタイト人、ミタンニ人、カッシート人と呼ばれています。
彼らは、オリエントの文明世界がこれまで経験したこともない武器や武具を携えていました。
とりわけ、馬に引かせる戦車を持っており、強力な軍隊を組織していました。
初期の戦車は、弓を射る者の木製の台車に革と金属が張ってあり、スポークで支えられた軽い二輪の車輪からなっている車両でした。
遺物として最初の戦車(馬を繋いで牽引させる戦車)が登場するのは、アナトリアやシリアから出土する印章の図柄の中であり、前二千年紀初頭のものです。
それを担ったのは、先ほどのインド=ヨーロッパ語系の民族、なかでも、戦車を最初に重用したのは、ミタンニ人であると見なされています。
戦車は、世界史の舞台に登場した最初の複雑な武器でした。
車両の管理や馬の制御を専業とする戦士の養成には、長い時間と多額の費用が必要とされました。
このために、戦車に乗る戦士の気高さや勇気には敬意が払われ、彼らの地位は高まりました。
ここに、まさしく武人というエートスを身につけた人間類型が誕生しました。
このような新しい気概にあふれた人々が社会を変革する一翼を担っていたことは想像に難くありません。
新たな行動規範を持つ人々が出現するというのは、歴史の中で大きな役割を果たしたと思われます。
さらに、人類史の舞台に馬と戦車が登場したことは、新しい階層出現のみならず、人間の精神や意識の底流に、まったく新しい観念が刻み込まれました。
それは、「速度」という観念であり、それを通じて世界の広がりを感知できるものでした。
これまでにない速度で移動することによって、世界は思いもかけない広大な姿で登場してきたに違いありません。
ひとたび「速度」が人間の世界に浸透すると、世界史はめまぐるしく動きだします。
馬と戦車の出現は、世界史の速度をも速めることになったのです。
(本村凌二著『馬の世界史』講談社現代新書、2001年7月刊、第2章「馬と文明」より)
仏陀の愛について
古代インド史の一コマ。
現代人は、「愛欲」と「慈悲」を「愛」という一言で呼んで混同しています。
例えば、恋人は、自分の欲望を追求します。
“相手のために”、自分を犠牲にしている、と錯覚している存在です。
恋人は自分の献身が相手に受け入られないと、激高します。
恋愛が“自分のため”の行為にすぎないことを明らかにしているのに、
そのことに気づいていません。
つまり、「恋愛」は利己的な物であり、「慈悲」は利他的な物です。
仏陀の愛は、慈悲の愛であり、恋愛の愛ではありません。
この2種類の精神的現象を「愛」の一言で表現する現代人には、
ある意味で、人間の本質が見えにくいでしょう。
パングラティ界隈の思い出(エッセイ)
パングラティ地区は、アテネ市内の東南、中心のシンタグマ広場から徒歩で約 20 分程のところに位置しています。 アテネに着き荷物を解き、アパートを借りたのがこの地区のクリシラ通り9 番でした。 何一つ家具のないがらんとした部屋で、まだ使えそうなマットレスなどの家具を少しずつ拾い集めてアテネの生活が始まりました。
そして、帰国までの約 2 年 2 カ月をこの界隈で暮らしました。 アテネはのら猫の多い町です。住民は平気で街角に猫のために餌を置いて行きます。 向かいの家の堀は猫のたまり場になっていて、きれいな猫には「ビビ」とか、 いたずら好きな猫には「ドラエモン」などとかってに名前を付けて呼んでいました。 部屋は通りに面した 2 階で、夏などはべランダで夕涼みがてら食事をしていると、おこぼれに預かろうと何匹もの猫が集まってきました。
近くのプラスティーラ広場にアポロンというスーパーがあり、帰国して三年後、再び訪れたときにも、かっていたレジのおばさんが同じ様にまじめな顔をしてレジを打っていたのには懐かしさで一杯になりました。
アテネの生活で、欠かすことのできないのは、ライキ・アゴラ(大衆市場) です。
季節によって場所は移動するのですが、我が家の近くではプラスティーラ広場に接する通りでひらかれていました。 週に一度、通りが活気あふれる市場に変身します。 道路の両側にずらりと、にわか仕立ての季節の野菜・果物売り場が店を連ね、 お客は一週間分キロ単位でまとめ買いをしていきます。 ごったがえす店先で、我先にと買い求める客に対して、店の主人の方は「こちらの人の方が先だよ」と、結構正しく順番を覚えているのには感心しました。 毎週同じ場所に同じ店が出店していて、笑顔のいい大柄なギリシア人の店となじみになり、時にはウィンクをしながら多めに入れてくれました。
ある日、ライキ・アゴラが突然消えてしまいました。 いつものように買い物籠を持って通りに出かけて行きましたが、市場は開かれていません。 買い物にやって来た地元のギリシアの婦人たちが、呆然と通りに佇む私のような外国人に対して、「ライキはどこに移動したの」と大声で詰問する始末でした。
ライキ・アゴラの移動の情報は、最後まで私には謎で、いつのまにか季節が変われば別の通りで別のライキ・アゴラが開かれているといった風でした。
ライキ・アゴラの通りに隣接してスタディオンがあります。 現在のスタディオンは、第 1 回近代オリンピックの際に、古代のスタディオンを復元・修復したものです。 U字型をしたきれいなトラック競技場で、観客席からは大通りを挟んで北西左手方向にアクロポリスとパルテノン神殿が浮かび上がります。 夏の黄昏時、沈む夕陽を背景にバラ色の夕焼けに映える姿は印象的で、飽きることなくいつまでも眺めていました。 この時の景色は、今も鮮やかに蘇ります。 遺跡巡りからの長旅から帰ってきたときなども、バスの中から遠くにアクロポリスが見えて来ると、ようやく我が家に帰ってきたんだと感慨にふけったものです。
(『かいほう』No54 号 1996 年 4 月刊)
a:3899 t:1 y:2